風俗店の面接のあとに
翌日の夜に、みさきは電話の向こうで笑顔を作っていた。
「今日、忙しかった~」と、銀行でのことを話した。
放尿させたらベソをかいてフェラしたことは、何でもなかったかのようにしてる。
数日後には、上司の愚痴を言い始めたので聞いてあげた。
彼氏とはそれほど連絡してないと、チラリと言いもした。
寂しかったのかな、という気もした。
金曜日と土曜日の外泊届けは提出した、とのこと。
電話で言った通りに、外泊先は親戚として自分の家を記入している。
風俗をやる気になっている。
そして面接予定日の木曜日。
18時すぎ。
みさきの銀行の寮の近くの交差点に車を止めて待っていると「待った?」とみさきは姿を見せた。
向かった店は、渋谷の性感ヘルス●●●。
店長も店の造りも明るくて、風俗店というのを感じさせない。
軽快に有線放送が流れる店内の事務所で、みさきは面接の用紙に記入した。
とくに意味はないが、銀行員というのは伏せるように事前に言っといた。
信頼されてる女子行員が、風俗で働く・・・。
面接中、自分だけが知っている事実に密かに興奮していた。
それからポラロイド写真を撮ると、ロリっぽく清純そうに撮れている。
客が好みそうなタイプだ。
入店初日の土曜日は、13時から講習して、夜まで店に入ることになった。
みさきはたとえ風俗店のサービスのマニュアルでさえ、教育された女子行員の笑顔で真面目にこなすだろう。
スカウトバックは、出勤日数と本数と指名を換算したもの。
月にせいぜい4日程しか店に入れないので、大した金額にはならない。
面接が終わる。
2人で渋谷の街を歩いて、講習がすごく大変だから心配かななどと大げさに話したりしながら車に戻った。
「講習って大変だよ」
「なにするのかな?」
「シャワーの浴び方とか、イソジンの使い方とか。素股もかな。基本的なことだよ」
「大丈夫かな・・・」
実は、そんなに大変ではないのだけど。
その店は本物のチンポではなくて、バイブを使う講習なのだから。
「みさき、泣かないかな」
「前にも友達にもいわれたことある。すぐ泣いちゃだめだよって」
「みさき、フェラいたいし」
「したことないんだもん。・・・わたしね」
「うん」
「小学校の頃、男子にいじめられたの」
「なんだっていって?」
「学校の帰りなんだけど、男子が家までずーとついてきて、蹴ったり触ったりしてきて・・・」
「・・・」
「やめてって言ってるのに、もうね、泣きながら帰ったの」
「・・・」
「そしたら、お母さんが飛び出してきて、男子を怒ってくれたからそれきりだったんだけどね」
「うん」
「わたし、それから男子が苦手になっちゃって」
「・・・オレは怖い?」
「うーん。最初は怖かった。・・・最初に声かけられたとき、すごく大きく見えた」
「そっか」
「妹しかいないし、学校も女子高だったしなぁ。男の人がなんだか怖かった。ずっと怖かった」
「ふーん」
まだセックスの経験が少ないみさきは、男本位のセックスにとても忠実だった。
わざとベットに突き飛ばしてもなすがまま。
上半身は着衣のまま、脱がした下半身を開いてて舐めてもなすがまま。
ただ、反応にちょっと変化が出てきた。
押し殺すような声だったのが、甘い喘ぎ声になっている。
小さいクリトリスを舐めると、逃げ腰にならずに、自分の手をぎゅーと握ってくる。
シックスナインをすると、自分から肉棒を手に取り口に含んだ。
あそこは、分泌された汁にまみれている。
トロトロになっている。
生で挿入。
「中に出す」と言うと、うなずいている。
肉体を力を込めて突き抜いてから、お腹の上に射精をした。
それからまたすぐに四つん這いにして、お尻を鷲つかみにして、肉棒を突き立てた。
膣肉の締まり具合を味わうように、ゆっくりと抜き差しもした。
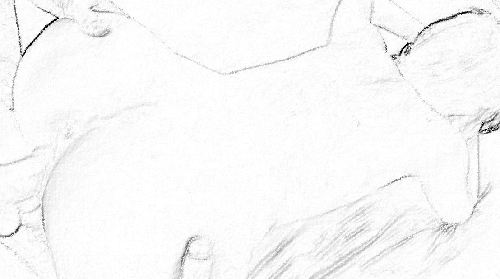
やがて射精をしても「勃たせて」と言えば、教えた通りに口と舌と指を丁寧に動かす。
何回目かの射精のときには、精液がでなかった。
外は夜の気配がした。
門限の時間だった。
寮まで送らなければいけない。
向う途中だった。
助手席のみさきが、そっと手を握ってきた。
いったい、みさきにとって。
自分の立ち位置は、なんなんだろう。
『彼氏』という訳ではないのは確かだ。
そんなふうに思って、いじわるを言ってみた。
「みさきさ、気持ちいいの?」
「・・・」
「オレとしてるとき」
「ん、・・・ん。・・・まあ」
「まあってなに?」
「・・・わたしね」
「うん」
「セックスってあまり気持ちよくないっておもっていた」
「ふーん。彼氏のときは?」
「ん。・・・痛かった」
「それは初めてのときでしょ?」
「2回目も痛かった」
「2回目も?」
「うん。ずーと痛いって言ってた」
「そっか」
「・・・そしたら彼氏もしようって言わなくなっちゃった」
「ふーん」
「・・・」
「みさきさ、中で出しても大丈夫なの?」
「うーん。・・・大丈夫じゃないけど」
「うなずいていたよ」
「うん。・・・どうするんだろっておもってたの」
きょとんとした顔のみさきを見て、立ち位置なんでどうでもいいかと思う。
金曜日は、ピンクローターの経験をさせてやろう。
騎乗位をさせて腰を振らせよう。
顔射も皆していると教えて、お掃除フェラも教えよう。
そのうち、銀行の制服も持ってこさせるか。
体験入店のまえに
そして金曜日の夜。
いつもの交差点で車を止めていると、タイトな白いワンピースで姿を見せたみさきだった。
初めて見るワンピースだ。
決して派手さはないが、黒髪とノースリーブから伸びているスベスベの二の腕が合ってる。
本人は意識してないのだろうけど、色白の胸の谷間も普通にエロい。
フェミレスに寄ってメシを食べながら聞くと、去年買って、今日はじめて着るワンピースだとはしゃぐような表情。
似合っていると褒めると、嬉しそうにニコニコしていた。
ウチに着いたあとは、当然のようにみさきにセックスを求めた。
肩を抱いて胸を揉んで、ワンピースと下着を脱がすと、みさきは表情を変えて甘い声を出す。
しなやかな身体で滑らかな肌の肉体は、抱き心地がいいものだった。
シックスナインからはじめると、教えた通りに太ももから舐め始める。
手の平に肉棒をとり、裏筋を音を立てて唇で吸うのも教えた通りだ。
フェラが気持ちがいいことを伝えると、大きく吐息を立てながら唇を這わせている。
男が喜ぶのを嬉しいのだ。
サービス精神は旺盛だ。
ピンクローターでクリトリスを責めて、何度も「イクッイクッ」と大きな声で言わせた。
イクと同時にピューとおしっこを漏らすほど、大きな声で喘いだ。
おしっこを吸い取ると、嫌がる素振りもなく、口元に笑みを浮かべている。
営業スマイルじゃない、エロい笑みだった。
寝るときに腕枕をしようと「こっちこい」というと、大げさに「きゃ」と身をすくめたみさき。
そうか、男と一緒のベッドで一晩寝るのがはじめてなのか、と気がついた。
戸惑っているみさきを抱き寄せた。
「ね。腕って痺れないの?」
「うん。痺れない」
「ふーん。わたし、痺れると思っていた」
「伸ばしたままだと痺れるけど、こうすればいいの。で、ここに頭を乗っけてみ」
「あぁ、いやぁ」
「なにが?」
「え。ちょっと恥ずかしい」
「恥ずかしいことないよ。もう、ケツの穴まで舐めあう仲なんだから」
「いやぁ」
「さっき漏らしたおしっこだって、しょっぱかったよ」
「あぁ、いやぁ」
「いやぁって、おしっこ漏らしたのは誰よ?」
「ああぁ、やだぁ、いわないで」
そのまま頭を抱いて寝て、朝起きてからは、朝の光に映えているみさきの身体をよく見た。
清潔感がある黒髪に、陽に当たったことがない白い肌は、吹き出物がなくスベスベ。
ピンクの乳首に、処理をしてないのに薄い陰毛。
客には喜ばれる肉体だ。
セックスと軽く寝るのを繰り返すと、13時の出勤に間に合うようにウチを出る時間になった。
みさきは、腕枕で体にもたれている。
何気なく訊いた。
「お店、大丈夫?」
「ンンン・・・」
「どうしたの?」
「まだ、ちょっと戸惑いがある・・・」
少しの笑みでモジモジしながら呟いている。
ここまできて、まだそんなことを言うみさきに、また加虐な勃起する。
腕枕を解いベットに転がして、白いパンティーを剥ぎ取って、すぐに生で挿入した。
すぐに甘い声を出して、大きく呼吸をして、腰に手を回してくるみさき。
腰を打ちつけながら、みさきと目を合わせながら淫語を言わせた。
「カレシよりも気持ちいいって言え!」
「えっ」
「言え!」
「・・・あぁ。・・・カレシよりも気持ちいい」
「もっと違う感じに」
「・・・気持ちよくてすごい感じる!あぁぁ」
「お客さんのチンコをたくさんなめるって言え!」
「お客さんのチンコをたくさんなめる!」
「もっと違く!」
「チンコたくさんなめる!・・・いっぱい舐める!」
「もっと!」
「あぁぁ、・・・いっぱいペロペロする!」
射精の瞬間、みさきの身体をまたいで口に肉棒を持っていった。
昨晩に教えた通りに、みさきは口を開けて舌を出した。
一晩分の精液が、口元から頬まで勢いよく振りかかった。
亀頭から垂れている精液を唇と舌でぬぐいとったみさきは、まぶたを閉じて、喉を鳴らした。
大きく鼻で息をしてから「飲んじゃった」と頬に精液を付けたまま、開けた目を細めて笑んだ。
良識は奪わない
ベッドから抜け出して、急いで身支度をしてウチを出た。
程なくして渋谷について、パーキングに車を入れる。
相変わらず人が多くて、熱い日差しだった。
すぐに日に焼けてしまう、強烈な日差しが降り注いでいる。
白いワンピースから伸びている白い肌の二の腕に、その強い日差しが反射してるかのようで、えらく眩しく感じた。
陽に焼けて、変色するのがもったいない白さだった。
とくに会話することなく歩いていたら、みさきが首を振りながら髪を後ろにまわして、あの営業スマイルではない笑みを浮かべて自分を見た。
色っぽい目力をしている。
なにかが、みさきのなかで変わった。
109の地階ではカラオケコンテストをしている。
誰かが『hitomi』のなんとかいう曲を歌っている。
みさきがそれを口ずさんで、やはり会話することなく歩いているうちに店についた。
エレベーターで上がるところまで見送った。
23時になる。
人気のなくなった109の脇に座り、みさきを待っていた。
店にいるみさきには、自分からは連絡はしていない。
放置している訳ではない。
嫌な客もいるだろうから、下手に連絡をすると、みさきの場合は泣きが入ってしまう気がしたからだった。
とっくに閉店している109の地階には、さほど人はいない。
1人のスカウトマンが目の前で動いている。
ギラギラと目が輝き、物色するように辺りを見渡す彼は、常人には感じられなかった。
やはり、自分も含め、スカウトマンはどこかおかしいのが多いのか・・・。
そんなことを思っていると、みさきから「いま、店おわった」と電話がはいる。
道玄坂を上がっていくと、白いワンピースとミュールのみさきの姿が見えた。
若者がナンパみたいに声をかけたが、みさきは無視をしてこちらに向かい歩いてくる。
2、3言交わして頭を抱くと、身体全体からボディーソープの匂いがする。
「スシでも食べるか?」というと「たべたい!」と即答した。
萎びた暖簾の寿司屋にひょいと入り、握り2人前と瓶ビールを注文した。
「どうだった?」
「うん。・・・ちょっと疲れた」
「いやな客いたか?」
「ううん。みんないい人だったよ」
「客は大事にしないと。・・・みさき、ウチらにとって客ってどういう存在だと思う?」
「エ・・・。わからない」
「この仕事やる以上は、みさきもわかってないといけないけど、・・・客はただ金を持ってくる存在なんだよ」
「ウン」
「外で会おうって客いただろ」
「ウン、いた」
「いやな客もいただろ。・・・本番させてとか」
「ウン・・・。いた・・・」
「ある意味、客は敵なんだよ。そう思わないから、みさきは疲れたかもしれない。・・・でも、難しいか?」
「ウウン」
「・・・なにかもう少し、握ってもらうか。なにがいい?」
「イカ食べたい」
みさきは、家庭でも学校でも職場でも、良識ある教育を受けていた。
そして、この教育には、従順さという危険も含まれているのではないのか?
みさきにとっての良識さえ奪わなければ、まだ、まだ、動かすことができるのではないのか?
いずれにしても、みさきほどスジがいい女は、スカウトだけでは放したくない。
金を獲ってもいい。
そのためには、客という共通の敵の存在も必要になると漠然と感じていた。
さらに接触して、もっとみさきに関わっていくことが必要だった。
みさきはどんどん変わってしまうだろうから。
どのようにして動かそうか。
彼氏と別れさせるか。
銀行も辞めさせるか。
でも預金課の女子行員だし。
今後、何かをおこしそうな予感がした。
– 2001.8.20 up –