スカウトの収入と経費

映画看板前からスカウト通りを見て。
イタトマで合っていたのは、北新宿のAVプロダクションのマネージャー。
前月分のスカウトバックを受け取り、領収証を切った
スカウトバックは下がってきていた。
2件のAVプロダクションと2件の風俗店を合わせて、今月は50万を切ろうとしている。
そのほかには、3件のAVプロダクションに入れ込んでもいる。
が、所属しているすべての女のコは、スカウトバックが発生する期限の1年を過ぎているか、本人のやる気がなくて稼いでないかだった。
もうあと3件の風俗店には、すでに1人も在籍がいない。
サボりすぎていた。
50万だとキツイ。
スカウトするのにも経費だってかかる。
経費といっても、お茶代とタクシー代といった細々したものだったが、それだって月にすれば10万はかかる。
女のコによってはメシ代くらいは使う。
そのほかにも佐々木やヒロシなどと飲みにもいくし、外食ばかりでついでにビールの1杯は飲んでしまうし、メシをつくってくれる智子に2万か3万づづでも渡すし、エンゲル係数というのが異様に高い。
贅沢をしているつもりは全くないけど、生活費の支払いを済ませると、50万でも手元に残らないものだった。
打ち合わせをしていると昼に。
イタトマを出て、マネージャーと別れた。
はじめるか・・・と少しだけ心の準備をしながら、ブラブラと東口に向かう。
ワールドカップが近づいていた。
駅前も、歌舞伎町も、騒がしさが増している雰囲気。
サッカーがわからない者でも、楽しい気分になるような気がする。
晴日も続いている。
暑くもなく、寒くもなく、蒸してもない時期。
いい季節だけど、スカウトのやる気は落ちていた。
ここのところ、スカウト通りに毎日はきてなかった。
スカウトなど、日雇いの土方と同じだった。
いくらでも休めるし、休めば収入にならない。
日雇いの土方のほうが気が楽かもしれなかった。
やる気などなくても、現場にいけば確実に収入にありつける。
気分が沈んでいても、明るくやり続けないと収入にならないのがスカウトだった。
強引に足を止めるのは迷惑条例に抵触する
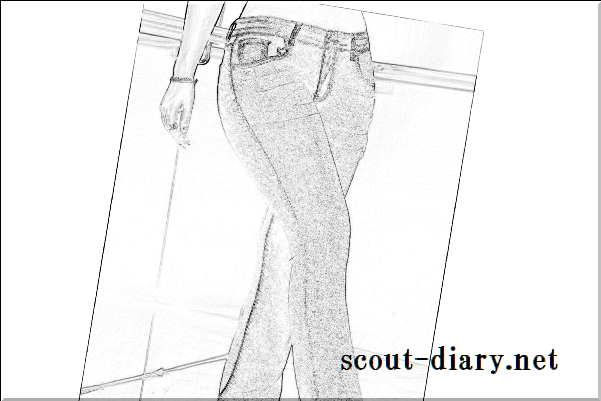
東口のスクランブル交差点に差しかかると、横断信号が青にかわった。
信号待ちしていた女のコが、ローライズのデニムで渡りはじめたのが目に入る。
明るい午後の表情。
なにかいいことがあったか。
自分が足を向けると、それだけで彼女は気配を察したようだ。
向けた足を進めると、彼女は早めの足と腕の運びに合わせて、ワンテンポだけチラッと目を向けた。
そうくると思っていたから、自分も手の平を軽く挙げた。
「どーも」
「・・・」
声は届いてないが、すぐにプイッとして目線を反らした。
表情も足先も変わらない。
まばらな横断者をやり過ごすと、彼女の手前だった。
足を止めて、彼女の視界の端に手を差し出して、もう1度声をかけた。
「こんちわ」
「やらないよ!」
歩くテンポに合わせて、手で追い払うようにして明るくあしらう。
普段から声をかけまくられている様子。
「聞いてよ、AVだから」
「やらない!やらない!やらない!」
そのまま通り過ぎようとしてるローライズに合わせて、自分は足を後進させた。
断りを連呼する彼女だったが、お互いの歩調は合っていた。
早口に対しての、緩い口調も合っていた。
「やってみようよぉ」
「ダメダメダメ!」
「ちょっと待ってよぉ」
「ダメダメダメ!」
肩から下がるトートバックの端に指先をかけた。
それを手前に引いたのがブレーキのように、彼女の足元は歩道の手前で止まった。
「あああ、ごめんなさぁい!」
「ちょっと、指!指!」
「ごめん、なんか引っかちゃったみたい」
「もう!」
強引さを詫びながら前に回り込んだ。
文句はいってきたが、クッキリとしたメイクの顔立ちは気にしてない様子。
思わず、もっと無礼に突っ込んでしまう。
「ニューハーフじゃないよね?」
「ひどーい!」
「ゴメン、背高いし美人だからキレイだなって意味でね、そうなのかなってさ」
「で、なに?10秒だけね」
「20秒にして」
「じゃ、20秒」
「うん、やっぱキレイだからさ、脱いでみない?」
「ダメダメダメ」
「なんで?やっぱりオレがあやしいか?」
「うん、だし、やっぱりできないでしょ?」
「バレたら誰に怒られるの?」
「彼氏」
「もちろん彼氏には内緒でさ」
「できないできないできないできない!」
明るいままのノリはいいが、聞き流している返事。
掴みどころが探せない。
「ちょっとは裸に自信あるでしょ?」
「ないないないないない」
「今すぐじゃないから」
「ぜったいできない!」
肩から胸元を露出しているこの着衣は、オフショルダーという名称でいいのか。
その露出には意識して目は向けてはないが、彼女は断りながらオフショルダーの胸元を指先で軽くつまんで、何気なく整えている。
「考えてみてよ」
「ダメダメダメダメダメ」
断りながら、胸元の着衣を1センチくらい引っ張っている。
露出を無駄に隠そうとしているのが可愛い。
「そう?平気ってコ多いよ。明治時代じゃないんだからさ。死んじゃうわけじゃないし」
「わたしはダメ。そういうのは」
「じゃ、ちょっと打ち合わせしよ」
「ムリ!もう20秒たった!」
澱みがない即答は、こちらの間をとらせない。
会話は回らなくて反り合っていく。
「カレシと結婚するんだ?」
「うん、来年ね」
「やめちゃえば?」
「ぜったいする!」
アタリだ、という感触が湧かない。
そろそろしつこいし、すでに見極めは赤信号だ。
「冗談だよ。ゴメンなさいね、いきなり」
「フフ。いいよ」
「それじゃ」
「うん、それじゃあね」
彼女は新宿通りをマルイの方向に歩いていき、デニム後ろ姿を少しだけ見送った。
断りには違いないが、1人目からこんな反応の日は、このあとにスカウトできる日だ。
大金に興味を示す女性の傾向
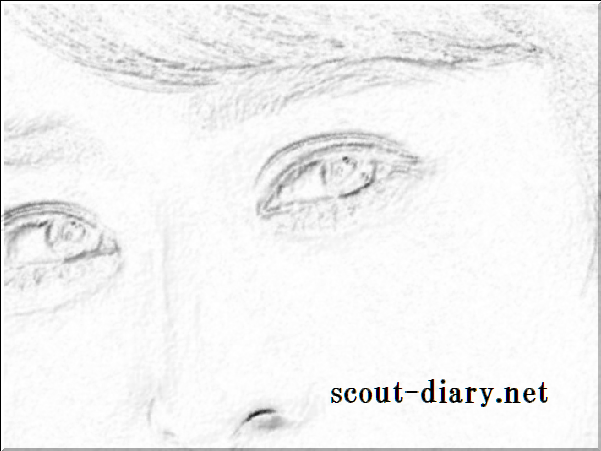
その断り具合から、ヤル気度の判断ができるときも多い。
東口交番前に歩いた。
昼を過ぎると、青空と微風が少しだらけた土曜日の空気になったようだ。
いつも通りに、手を挙げてみたり足を進めたり声をかけたりを繰り返した。
いつもと同じように、怪訝そうな横目。
横目だったらいい。
目の端の端の端で見てくる横目だったらだめだ。
そんな横目の早歩きと、見向きもしないでの無視と、顔を反らしてからの素通りが連続していく。
次に足を止めた女のコは、10人以上に声をかけたあとだった。
「AVだけど」と切り出すと、はしゃいだような声をあげて「ムリムリ!」と手を振りながらあしらう。
足は完全に止まっていて話し込める。
名前は愛美。
面白半分の相づちと、スカウトが慣れている様子から、歌舞伎町で風俗をしているのは早めに当てた。
AVプロダクションには、まだ所属してない。
それらを明かしてきたあと彼女は訊いてきた。
「ギャラっていくらくらいなの?」
「まなみ次第。もちろん高いほうがいいでしょ?」
「うん。だいたいいくらなの?」
「いくつか訊かせて。条件による」
お金の問いが出てくるのが早すぎる。
話は早いが、期待するほどのスカウトバックにはならないパターンだ。
「200万だったらやるけど」
「1回で?」
「うん」
「200万だったら2日撮りになる。だったら1日で100万ってのは?」
「200万じゃないとやらない」
「パッケージできる?」
「ムリ!」
この反応は、すでに幾人かのスカウトから話を聞いている。
しかも、適当な話を吹き込まれている状態だ。
オーバートークだったら動かせるかも。
話を変えるために人を変える。
そのワンチャンスを試すか。
が、そのまえに確かめたいこともある。
大金に興味を示す女のコは、父親にわだかまりを持つ傾向があるからだ。
200万にこだわる彼女には、そこを確かめてみたかった。
「バレたら誰に怒られる?」
「え、彼氏」
「え、お父さんは?」
「え、べつに・・・」
彼氏に怒られると返ってくるのはわかっている。
そこをあえて「誰に」と訊いてみる。
そうすれば「え、お父さんは?」と、さりげなく1回だけは聞きなおせる。
「え、怒ったりしない?」
「怒りはしないけど・・・」
目も普通のままだし、頬も揺れないし、口元も声も変らない。
この反応はやる気はない。
大方の風俗嬢というのは、父親が大好きなのだ。
AV嬢と比べると、なんのかんのいっても、という補足がつくが。
「そもそも、お父さんはAV見ないか?」
「見ないよ」
彼女はさすが風俗をしてるだけある。
男の性というものに、うまく折り合いをつけている。
「見ないんだったらバレないんじゃない?」
「でも、バレたらイヤ!」
200万が無理なのはわかっているんだ。
やる気もないのにスカウトを困らせて楽しむ女のコもいるのだった。
あとは時間の使い方の問題。
というか判断。
ワンチャンスを試すべくもっと時間をかけてみるか、それともその時間を他の女のコを見つけるのに振り替えるか。
いずれかを自分の都合のみを優先して決める。
今日の流れからすると、見込みがある女のコは続けて現れるものだった。
彼女は後回しでもいいか。
店が歌舞伎町だから、後日にも見かけることだろうし。
頃合をみて話を切り上げて、また今度と番号交換だけして、バイバイして後ろ姿を見送った。
メール交換はすべきか?
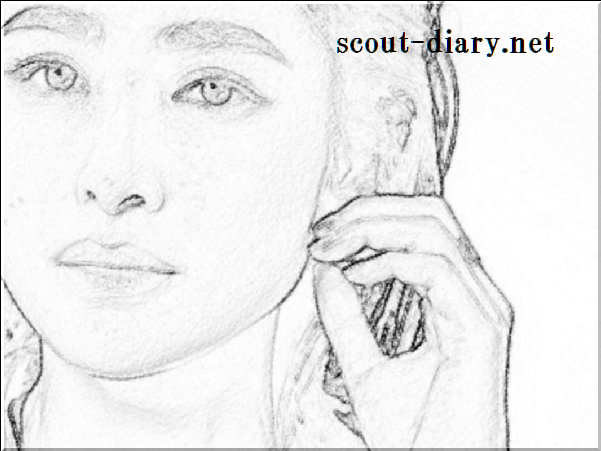
ムキになればなるほどいい。
その次に声をかけた女の子も足を止めたが、警戒が溶けない表情。
「AVだけど」と切り出すと、目線が落ちた返事。
「あやしくてスミマセンでした」とバイバイするときに初めて浮かんだ笑みからすると、よほど自分があやしくうさんくさく見えたのだろう。
彼女のバイバイの手の振りを見て、もうちょっと話せばよかったか・・・とも感じたが、1度バイバイしてしまったものはしょうがない。
『やっぱ、また話きいてください』と軽くいけるような男になりたい、と一瞬うなだれた。
ミスかもしれないけど、気持ちの勢いはついてきている。
歩調と口調の拍子の具合も良い。
そんなコンディションのとき、こちらに歩いてくる空色の薄手ジャケットが目に入った。
白のパンツが、歩く太腿にぴったりと張り付いている。
正面から歩み寄っても気がつくことない。
斜め上に青空に目線を向けて、肩まである髪を指先ですいている。
少し手前になってから、こちらに気がついた様子。
軽く手を挙げた。
「どーも」
「・・・」
3歩ほど大股で近づいて足を止めた。
彼女も足を止めた。
「こんちわ」
「・・・」
「あやしい者ですけど」
「・・・」
警戒というよりも。
戸惑い気味なのが伝わった。
「AVだけど」
「エ・・・」
「うん、AVのスカウトしてるの」
「・・・」
彼女は息を飲み込むようにして、目を見開いて驚いている。
驚きすぎだった。
AVと風俗は未経験者だというは伝わってきた。
「そんなにビックリしないでよ。あやしいのは顔だけだからさ」
「エ・・・」
「きょうは話だけ聞いて。ヒマなところわるいけど」
「エ・・・」
突然に声をかけられることに慣れてない。
たまたま新宿には来ただけパターンか。
「これから待ち合わせ?」
「・・・はい」
「アッ、あのね、ハイとか、そういうかしこまったのよそうよ。なんか疲れるから」
「・・・はい」
目には警戒は浮かばず、足は逃げにはなっていない。
注意しながらの微苦笑がでたとき、このコは押せるな・・・という感触がした。
「あ、ここさ、人通るから、こっちで話そうよ」
「・・・」
返事はなかったが、歩道の脇に1歩だけ寄りながら、彼女のパンプスの足先を視界の端に入れていた。
パンプスの足先は、戸惑い気味に動いた。
「通る人の邪魔になるし、1分くらい」
「・・・」
さっさと背を向けて、映画看板の前まで歩く。
彼女は後ろをついてきた。
「ちょっと、タバコすわせて」
「・・・」
タバコを取りだして、ゆっくりと火をつけた。
大人コーディネートだけど、まだ20代前半か。
「で、名前なんていうの?」
「え・・・」
「いや、名前きいたからって、どうこうないから、オレ、田中ね」
「小林です・・・」
「ああ、ちがう、下の名前」
「・・・」
「どうしたの?名前くらい普通でしょ?」
「真紀です・・・」
下の名前で呼ぶのには応じた。
敬語の短い返事だった。
「やっぱバレが気になるの?」
「やらないです、やらないです」
「バレたら誰に怒られるの?」
「え、誰って・・・」
「うん」
「べつに・・・」
AVへの理性からの拒否や、生理的な抵抗は少ない。
少ないというより、異業種の自分に対する警戒のほうが大きいのかもしれない。
「え、彼氏は?」
「彼氏いないもん!」
「あぁぁ、やっぱり!」
「え」
「いないとおもった!」
「なんで!」
「いちおう聞いてみただけだし!いるわけないか!」
「ひどくない!」
神経を逆撫でされたかのように、彼氏がいないと口にしてきて、それを指を差されてまでいじられた彼女だったが、急に噛みつくような笑顔を見せてきた。
もともと気分よく歩いていたのだ。
それに、ムキになった女の子は反応が大きくなる。
すぐ嘘だと訂正して、失礼は丁寧に謝り、彼女がもったいぶって許してくれたときには、とっくに1分は過ぎていた。
敬語もなくなっていた。
本当に時間がないのだろうなとは感じていたので、タバコ半分だけ話した。
「もっと聞いてほしいんだけど、時間とらせてもいけないし」
「うん」
「今日はさ、こんなことがあったっていうことで番号交換してさ、こんどはケーキ食べよ」
「ケーキ?」
「うん。で、そのときにダメならダメで断ってよ。なにがなんでもお願いしますってわけじゃないから」
「うーん、でも、やらないけど」
「かまわない。オレ、断られるのは慣れてるからさ」
「・・・うん」
「こう話してると、オレも普通の人でしょ?ぜんぜんあやしくないんだよってわかってもらえたらそれでいいからさ」
「・・・うん、じゃ、はなしだけね。でも、やらないからね」
小さなうなずきがあって、小さな約束ができれば、もうスカウトは半分成功したようなもの。
いや、半分は言い過ぎか。
ともかくもだ。
あとは押せるタイミングを待つだけ。
「じゃ、そういうことで、また、こんどね」
「うん」
「番号交換しよ。オレからワン切りする」
「メールでいい?」
「ああ、メールか。たぶんメールは送らないだろうな。苦手でさ」
「・・・」
番号交換ではなくて、メール交換だったらいいよという女のコも多かった。
メールのほうが気軽に応じてくれるのは確かだった。
けっこうメール交換はしていた。
だけど、やはり気軽な分だけメールだと動きがわるい感触がある。
やり方が上手くないだけかもしれないが、自分にとっては電話のほうがいいようである。
メール交換のみの女のコは後回しにしてるうちに、手付かずとなるのがほとんどだった。
どうせ手付かずとなるのだからと、メール交換にこだわる女のコは、そのままバイバイするようになっていた。
「もし気が変わったときとか、口もききたくないってときは着信拒否でいいし。見かけたときには石ぶつけてもらってもいいし」
「はは」
「もう、そういうのオレ慣れてるから。しつこくしたりなんてしない」
「ふーん・・・」
「そうだな、夜の10時過ぎとか電話しても平気?ひょとして寝てる?」
「起きてるよ」
「オレからワン切りするよ。・・・何番?」
「うん、ちょっとまって」
彼女は番号を言いながら、バックから携帯を取り出した。
携帯のメモリーに小林真紀と登録。
20代半ばの大人コーデ、未経験、夜に電話、とは後でメモにした。
相手からの質問がないと主導権がとれない

勢いで当日に所属させたのと、考える時間があってから後日に所属するのでは、後者のほうがスカウトバックは大きくなる。
5日後の夜に電話すると「はい」と彼女は出た。
出たはいいけど、果たして話が進むかどうか。
「田中といいますけど、・・・この前、新宿で声をかけた」
「あぁ、はいはい」
「先週だったかな、覚えてます?」
「はい」
「いま、電話、大丈夫?3分ほど」
「・・・うん」
「もし都合わるかったら、また、かけ直すけど」
「そうじゃないけど・・・。あ・・・、もう大丈夫。いま妹がいたから」
「いま、おウチなんだ。なんだかわるいね。そんなときに」
「うん、大丈夫」
少し話し込める感じで、すぐにお互いの口調がくだけてきた。
いいときに電話できた。
「で、彼氏できた?」
「ううん」
「残念」
「そんなすぐにはできないよ」
「ごめんね。・・・でさ、このまえ新宿にはあまり来ないっていっていたでしょ?」
「うん」
「通りかかったりする?」
「ううん。会社、品川で京浜東北だから」
「そうなんだ。こんどさ、新宿くるときあったら、ヒマなときにでも電話ちょうだい」
「なんで?」
「あのとき立ち話だったし、突然だったからさ。ズバズバと言っちゃったけど」
「・・・うん」
「失礼のおわびのケーキで。このまえ時間もとらせたしさ」
「・・・うん」
自分への警戒は、随分と溶けた様子だった。
好奇心は感じるが、それ以上の引っかかりをは感じない。
内容やお金については、彼女の口から出てこない限り、まだ自分からは触れないほうがいい。
和んで親しくなる必要がない

「何を言うのか」は限られているから「いつ言うのか」のほうが重要となる。
また後日の電話で、平日の夜の早い時間に、東口で待ち合わせる約束ができた。
電話も約束も、タイミングが良く進んだ。
うまくいくときは、なにをしてもうまくいく。
流れからすると、彼女は動かせるのではないか。
今月1人目のスカウトか。
そんなことを思い込みながら、東口交番前で人通りを眺めて彼女を待っていた。
ワールドカップは開幕されていた。
観光客ふうの欧米人が目立つ。
頬にペイントしている者もいる。
歓声が上がる騒がしさのなか、手にした携帯が鳴り、東口の階段から彼女が見えた。
今日も、白のパンツがぴったりと太腿に張り付いていた。
「どーも」と軽く手を挙げると、彼女はクスクスという含み笑いをする。
「じゃ、イタトマいこうか?」
「ははは」
「アルタ裏にあるの」
「ははは」
「え、なにかおかしいの?」
「ははは」
「オレの顔がおかしいの?」
「ははは」
自分もなんだか意味もなくおかしい気分だった。
で、イタトマは満席。
彼女のスカウトは無理かも・・・と頭によぎった。
スカウトできる流れのときには、まず席がしっかりと空いているものだった。
今の時間で空いていそうな窓際のカウンター席で思いついたのは、歌舞伎町のホテルケントの2階のカフェ。
靖国通りを渡ってセントラル通りを歩いた。
路上に満ちているワールドカップの騒がしさが、お互いに笑って話をさせたようだった。
「真紀さ」
「うん」
「彼氏できた?」
「ははは、できないよ!」
「やっぱり!」
「そんなすぐはできないよ!」
「会社の人とかは?」
「ははは」
「え、なにかおかしい?」
「ははは」
コマ劇をすぎるころには、ちょっと彼女の笑顔とは和みすぎた気がした。
和みすぎるのは、スカウトの邪魔になる。
ある程度は和んで安心させるなかにも、上下関係にも似た緊張感を作って維持しないと言うことをきなかくなる。
その緊張感に反応するうちでなければ脱がすことができない。
ズバッとビシッとバシッと・・・というテンポに、和みすぎるのは噛み合わないのだった。
そのテンポが面白くないような顔をしてる自分の方法だと分かっているのに、彼女とコマ劇の広場を歩く間には、ちょっとしたことで笑いがあった。
ホテルケントの2階のカフェは久しぶりだった。
窓際のカウンター席は空いていた。
日が落ちると照明が落とされてロウソクが灯るようになったらしい。
えらくムーディーになっている。
こうなっていたとは知らなかった。
席についてすぐに『失敗したかも・・・』とうな垂れた。
歌舞伎町の騒がしさから、一気に静かな店内に場所が移ると、2人の間の空気が変わる。
「おしゃれだね」と彼女は言ってるが、お互いの話し声が小さくなったようだった。
いかに騒がしい雑踏が、2人の会話を弾ませていたことか。
弾みが小さくなった会話を再び大きくできるほど、自分は話術は達者ではないのはわかっていた。
スカウトの失敗

それほどオシャレでも、どれほど良質なメニューだとしても、スカウトでは静かな店内は避けたい。
ロイヤルミルクティーなどオーダーした彼女だった。
カウンターにカップが置かれてから、彼女が座る位置を直したとき、不注意でソーサーに指先が触れたのが、会話のつまずきだったかもしれない。
わずかに触れただけだったが、まだ口もつけてないせっかくのミルクティーが揺れて、カップからはけっこうな量がこぼれて、ソーサーの白い底を浸した。
「あぁぁんっ」と彼女はふくれた。
自分が紙ナプキンを3枚ほどソーサーの底に敷いてあげると、たちまち茶色くビダビダに浸された。
茶色い液がしたたる紙ナプキンをつまんで取り除いて、新たな紙ナプキンでソーサーに残るこぼれを拭いてあげたとき、彼女は恥ずかしそうな表情をした。
違うかもしれないが、ロウソクに照らされた表情は恥ずかしそうに見えた。
拭いてあげたソーサーは、元とおりに白くなって、またカップは乗せられた。
それだけのことだった。
スカウトは半ば諦めていた。
もう彼女は、AVの話など聞かない気がした。
「あーあ」
「どうしたの?」
「AVのこと話すつもりだったのに」
「だって話だけでしょ?」
「そんなわけないじゃん、で、いつ事務所いく?」
「ぜったいやらない」
ぜったいに力を込める言い方だった。
それからは、どこにでもある話を、・・・例えば「ベッカムすごいよね」などと、どうでもいい話をしただけだった。
自分の中途半端さにうんざりする。
あきらめてこのまま帰そう・・・と思えてもきた。
ミルクティーを口にしていた彼女が「ねえ、みて」と、突然にバッグから取り出したのは薄い冊子だった。
勤め先であるソフトメーカーの社内報だった。
ページを開くと、社内の業務コンクールで、課員30数名のなかで彼女が優秀な成績を収めたことが載っている。
褒めればいいのだろうけど、安易に褒めるのは気をつけたい。
安易な褒めには小さな満足が生じるみたいで、小さな満足は話を聞かなくさせるようでもある。
とくに自分の場合は、褒めすぎると嘘っぽく聞こえるらしい。
むやみに褒めない理由

褒めるポイントってある。
本人の努力や頑張りが見える部分は褒めない。
成績にしてもそうだし。
おしゃれしても、メイクにしても、髪にしても。
すでに、備わっている部分も褒めない。
顔立ちもそうだし、仕草もそうだし、持ち物もそうだし。
彼女の場合だと勤め先が上場企業なのもそうだし。
たぶん、学歴も能力も当てはまる。
誰も気がつかない、誰も気がついてない、誰にも言えない、そんなふうにこっそりと隠れている部分を探して褒めてみる。
そこが探せななかったら、ちょっと変だなぁ・・・という部分を探して、あえて褒めてみる。
変な部分なのだ。
どういうことなのか説明すると、まず、AVプロダクションに所属するときに、記入するほとんどのプロフィールには《チャームポイント》という項目がある。
以外なチャームポイントを記入する女のコが目立つのだった。
例えば、明らかにタラコ唇なのにチャームポイントに《 唇 》と記入する。
まぶたが裏返っているほどのアイプチ失敗している目なのに、チャームポイントには《 目 》と記入される。
眉毛のカットや描きかたが変なのに、チャームポイントには《 眉 》と記入される。
棒のような脚なのに、チャームポイントは《 脚 》と記入される。
ちんちくりんな髪なのに、チャームポイントは《 髪 》と記入される。
他人からすればちょっと変に見えても、当人にすれば重要な意味があって、大切な部分ってあるのだった。
だからチャームポイントを拡大解釈して、ちょっと変な行動とか失敗なども範囲に含めて、それらも褒めるのも試してみる。
当人の中にしかない基準ってある。
その基準がどのようなものだとしても、そこを探って見つけて褒めることが一番の効果があるのは、その後の喜びようからわかる。
話の主導権もとることができる。
優秀な長女タイプはAVや風俗に目立つ

電話のとき「妹がいて・・・」と話した彼女が長女であることは、すでにさりげなく確かめてあった。
長女であって、成績優秀を喜んでいる彼女の場合は、なおさら褒めのポイントには注意したい。
以外なことに、優秀な長女タイプはAVや風俗に目立つ。
経緯を聞いてみると、以外なほどにダメ男に寛容でもあり、どうやら褒めの耐性が弱いような傾向がある。
同じく長女の智子がいうには、長女というのは、下の子の面倒をみて当たりまえ、やるのが当たりまえ、できて当たりまえ。
親も最初の子は育てるのに慣れてなくて、褒める余裕もなく、厳しくしてしまうという。
そのような背景があるからか。
褒めポイントを探ることができて、さりげなく試してみて、長女タイプがくすぐったいような笑みを見せたときには、・・・くすぐったいような笑みでなければならなくて、ともかく、その笑みを見せたときにはスカウトが成功する感触がある。
でも彼女の成績は、安易に褒めた。
小さな満足でもよかったし、嘘っぽく聞こえてもよかったし、褒めポイントを探すのが時間の無駄にも思えた。
ミルクティーさえこぼれなかったら。
試していたのに。
「うわ、すごい。なんか最優秀ってなってる」
「うん」
「真紀って優秀なんだ。すごい、すごいよ、すごいな!」
「ふふ」
社内報の他のページを開いてみた。
前期対比の伸長率、来期の事業計画、スローガンのような社是、それらが社員向けに記載されている。
また自分は、うんざりするような気持ちになる。
いつまでこんなふうに、まともな社会生活にしらけているのだろうと、自分自身にうんざりしている。
2人の窓からはコマ劇前が見えた。
突然のようにして、周辺が騒がしくなっている。
サイレンのパトカーが3台ほど到着していた。
「なんだろうね」と話しているうちに、さらにパトカーと消防車が追加で何台も到着しているらしく、赤色灯と消防士と人だかりが入り乱れてる。
警官がハンドマイクで「立ち止まらないください!」とのアナウンスしてるのが、窓越しに微かに聞こえてきた。
「どこか遊びいこ」
「・・・なんで?」
「真紀さ、なんでってよくいうね」
「そうだね」
こんなことじゃあ、今月のスカウトバックも下がる。
あきらめの、ため息がでそうだった。
スカウトの方法で迷いがなくなっていくのは、仕事としていいことだった。
が、単調に感じてきて、面白さはなくなってきていた。
「なんでっていわれてもな・・・」
「・・・」
「理由はないな。たださ、このまま帰るのもつまらない気がしたからさ」
「うん」
スカウトの方法が迷わなくなったのは、女の子たちが少しづつ態度で教えてくれたからだった。
路上で、せわしなく交わす会話の中から教えてくれた。
教えてくれたのが一定の量を越えると、ある日に突然にして『自分はなにをいうのか?』に気づく。
『自分がどういう人間なのか?』も、おぼろげにでもわかるときでもあった。
そうすると方法に迷いがなくなってきた。
迷いがあるからできたのであって、迷いがなくなるとできなくなるのは、自分の性格もあると思われる。
もっと稼ごう・・・という意気込みも乏しくなってきて、日常は惰性になっている。
つまりは、サボってばかり。
「なにかへん?」
「ううん」
「それにAVやらないでしょ?」
「うん、やらない」
「ほんとに?」
「うん、やらない」
窓の向こうは、回転する赤色灯ばかり。
「いたづら通報です!立ち止まらないください!」と警官がハンドマイクでがなっているのが、窓越しから聞こえてくる。
集まった野次馬が便乗してるのか。
いくつかのロケット花火が飛ばされた。
それらを眺めていると、いつまでスカウトをやるのだろう・・・と、ここ最近の疑問がまた湧いてきていた。
– 2003.11.24 up –
