キツネ顔で冷めたような女

1週間ほどして。
風が冷たい平日の午後。
スカウト通りでは、先に他の連中が使っていた。
自分は遠慮して、東口でスカウトをしていた。
寒さに弱くなっているのか。
今日帰ったら、股引を押入れから出そうと密かに決めていた。
程なくして、佐々木がふらりと姿を見せた。
佐々木は、この月末でスカウトを上がる。
六本木のキャバクラの内勤になるのだった。
お互いに用件もなくイタトマでお茶をするのは、ここ4年ほどで何百回と続いていたが、これからはそれもなくなるのだった。
カップが空になってから、テーブルの携帯がバイブレーションした。
ディスプレイで、この前の彼女だとすぐにわかった。
彼女から電話がくるのは以外だった。
番号交換をしてそれきりだったから。
「もしもし」
「田中さんですか?」
「どーも」
「わかります?」
「うん。ひとみでしょ? わかるよ。どうしたの?」
「いま、新宿にいるんだけど、仕事中?」
「ううん、サボリ中。じゃあ、会おうよ。この前のところ、わかる?」
「うん、わかる」
「5分くらいでいく」
「うん」
それを見ていた佐々木も、タバコの火を消した。
空のカップと灰皿をトレイに乗せながら言う。
「そろそろ、オレもいくかな」
「じゃあ、また」
「また、適当に寄るよ」
「うん」
2人でイタトマを出て、冷たい風に当たりながら歩く。
スカウト通りに向かいながら、佐々木が続けた。
「そのコ、見込みがあるの?」
「いや、まったくない。ただ、いい女でさ」
「ははは。田中さんのいい女ってビミョーだよなあ」
「いい女は、いい女だよ」
「どちらかと言えば、キツネ顔で冷めたような女でしょ?」
「ちがう、ちがう」
「うーん、あっ、わかった。不幸な感じ?ダマされたり、暴力ふるわれてるような。あと家出中とか」
「ちがう、ちがう」
「あっ、30代人妻?それか子連れバツイチ。そういうのも好きでしょ?」
「ちがう」
「40代主婦?ひょっとして50代の熟女いっちゃった?」
「アンタ、ナニいってんだよ!モデルだよ。青山の●●所属の」
そんなことを話すとスカウト通りだった。
立ち止まって、駅の方向に目をやりながら話していた。
「そんなのどこでスカウトしたの?」
「ここ歩いてた」
「うーん、なんちゃってモデルじゃないの?実は歌舞伎町のデートクラブ嬢だとかさ。ありえない?」
「うん。ありがちだけどさ。でもね、やっぱり雰囲気あるんだよ」
「クラスは?」
「B上だね」
「そんなもん?」
「目鼻は整っていてさ、表情が豊かでね、肌と髪がキレイなんだよ。それが自然にスッキリしすぎてるの。それを引くからB上かな。でもね、目一杯にイジれば雰囲気は出せるコだし、ラインもいいから、脱げばAまでいく自信あるな」
「夜、店やらないかな、そのコ」
「オレも一瞬、紹介しようかなって思った。だけどそれ以前に動かせないコだからね。でも接客のイメージないなあ。かわいらしさや愛嬌なんかの男好みする部分がないんだよ。それに夜ってさ、なんていうのかな、マニアックなハデさとか、病的な色気だとか、あと不健全なキレイさとか、そういうのがウケるじゃない。そのコはそういうのがないんだよ」
「うーん」
「見てみる?紹介はしないけど」
「うん、見てみる。・・・ふーん。ここで、そんなコがスカウトできるんだ」
「あれは、偶然だなあ」
人がまばらなスカウト通りの向うに、彼女がわかった。
まだ自分には気がついてないらしい。
今日も黒の上下とあの髪で、いい姿勢の彼女だった。
寒さなど感じさせない姿勢でも。
本当に女のコはわからない
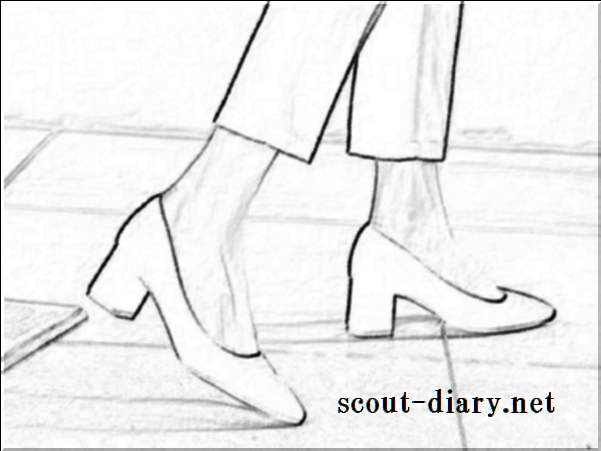
スカウト通りは、新宿駅を上にして緩やかな坂になっている。
若干、歩いてくる彼女を見上げるような目線になっている。
カッ・・・カッ・・・とヒールの音が離れた場所からでもわかるようで、歩く姿とまとまりが出来ていた。
1人のスカウトが、すかさず声をかけた。
何事もなかったかのように、素通りする彼女。
それを見ていたもう1人のスカウトが、声をかけようと足を進めた。
が、気圧されたように、足は立ち止まる。
そして彼女の後姿を見送っている。
彼女の歩くスタイルは、黒の上下になびかせた髪、すました顔やヒールの音だけでなくて、周りの視線や空気までを取り込んで、それらすべてを統制している。
そんな険しさのある基準があった。
彼女が気がついて手を振ってきた。
すました顔に、突然びっくりするくらいの豊かな笑みが浮かんだ。
自分も軽く手を挙げて応じた。
そのまま彼女は、自分の前まで歩いてきて、スッーと立ち止まる。
自分は、思わず『くゥ~』と、うなりたい気持ちもした。
スカウト通りから、少しでも離れた場所だったら、そんな気持ちは沸かない。
あくまで平静を装い、彼女と2言3言交わす。
後ろにいた佐々木に振り返ったときは、自信満々の顔をしていたのかもしれない。
いろんな意味で以外だったのだろう。
それにしても、あんなアホな顔をした彼は初めて見た。
そして佐々木は「それじゃあ」と駅に向かっていった。
「今日はどうしたの?」
「新宿にいたの。ヒマな時に電話してっていったでしょ?」
「うん、そうだね。・・・また、マン喫?」
「ちがうよ。紀伊国屋いってきたの」
「本買ったんだ?」
「うん」
「なんの本?」
「デザインの専門書」
「あー、むずかしそう」
「ねえ」
「ん」
「どこか座らない?」
「あ、そうだね。・・・時間あるの?」
「うん。1時間ちょっとぐらいだったら」
「そっか。・・・じゃ、プリンスのラウンジいこうよ。ケーキおいしいし、ソファーあるし」
「うん」
歌舞伎町交差点を渡るときには、いつものクセで考えていた。
ヒマだから電話した、とは言うが、それだけではないだろう。
かといって『オゴって』などと、ガツガツしてる訳でもない。
まさか彼女と、AVや風俗の話になるのだろうか。
実は援交していてとか、高級ヘルス探してるのぐらいは言い出すかもしれない。
愛人やってみたいとか、女王様やってみたいなどと、突飛もないことも考えられる。
いや、そのくらいだったら、その通りでスカウトしてれば普通のパターンだ。
彼女の場合、そんなことはないだろう。
でもわからない。
本当に女のコはわからない。
だから何を言っても驚かない。
などと心の準備をしながら、彼女とたわいもないことを話していた。
自分に似たタイプがスカウトできる

アナウンスと催事で騒がしい西武新宿駅前を歩いた。
西武新宿駅の上階が、新宿プリンスホテルになる。
エレベーターで25階に降りると、騒がしさは耳に届かない。
女連れに対しては、窓際のソファー席に案内をするウェイターだった。
大きな窓を隔てて、歌舞伎町の雑居ビルの屋上面がいくつも見えるのに、静けさと青空とソファーが気持ちを落ち着かせた気がした。
「あれから誰かスカウトできたの?」
「ボチボチ」
「ねえ、何人くらいスカウトするの?」
「ははは、なんでそんなこと訊くんだよ?」
「興味があるの」
「えええっ、AVに!」
「ううん、スカウトに」
「そっか。そうだよね。うーん、まあ、いいか。手のウチ見せるのはイヤなんだけど。ひとみをスカウトできるわけじゃないし」
自分はしっかりとマヌケに驚いていた。
ただ単に、スカウトに興味があるだけのようだ。
テーブルに置かれたケーキに、今日は3つめかと思いながらフォークを入れた。
「何人くらいだと思う?」
「うーん、月に10人くらい?」
「お、いいとこだね。10人連れ回して、2人か3人AVで動くって感じかな」
「どうやって連れていくの?」
「声かけて、ちゃんとAVの事務所だけどって言うよ。それで、裸の宣材写真撮らせてって連れていくよ」
「それでついていくの?お金とか払うの?」
「お金なんて払わないよ。宣材写真だから。お茶くらいはオゴるけど」
「ねえ、見てわかるの?そういうコって」
「いや、まったくわからない。よく訊かれるけどね。話してみないとわからないよ。いかにもっていうコでも、話してみるとダメなときもあるし、ぜったいに脱がないだろうなってコがOKになったりとかね。だからまず話してからだね」
「ダマしちゃうの?」
「ダマしとはちがう。ダマしってのは、もっと違うものだよ。それに簡単にはダマせない」
「じゃあ、なんて話すの?」
「ははは。この前、ひとみと話したことと変わりないよ。AVだけどって言って、名前きいたり、エロ話したり、天気の話したり、うーん、つまらんギャグも言うし」
「それでAVにでるの?」
「いや、最初から出ますなんてコは、まずいないよ。うーん。どう言えばこうなるとか、なにを言えばこうなるとか、そういうのはあまりないなあ。うーん。オレ、うまくまとめて話すのが苦手なんだよ。いろいろ話とんじゃうから。もし、話がズレたら突っ込んでくれる?ズレてる、ズレてるって」
「うん、突っ込む」
「むずかしいな。だってさ、100人スカウトがいれば、100通りの言いかたがあるわけだし、女のコも100人いれば、100通りのタイプあるからさ。それにやるコだって、この前はよくても今はダメとか、そういうのあるじゃない」
「うん」
「それで、いざやりますってときでも、やっぱり本番は、あっ、大丈夫?こういうこと言っても?」
「うん、大丈夫」
「そう。まあ、中出しとか、大丈夫?こういうこと言っても」
「だから、大丈夫だって」
「うん。本番はイヤですとかあるし。だからね、声かけてからは、こっちが考えているようにはいかないんだよ」
「そうなんだ」
「うん。そうだな、何を言うかよりも、いつ言うかっていうのは注意してるよ。そういうスカウトの流れや動きっていうのは意識してるけど」
「うーん」
「結局、自分に似たタイプがスカウトしやすいんだろうね」
「似たタイプ?」
「うん。そう思うな。オレの場合で言えば、好奇心が強くて、スケベで、変わり者の女のコあたりかなあ。ひとみはB型?」
「わかるの?」
「あ、じゃあ、AV嬢の素質あるな」
「ちょっとー」
「ゴメン、ゴメン。ヘンな意味じゃない。好奇心が強い感じだし、モデルもやっているからさ、そんな気がして。あのね、実際、10人AV嬢がいるとするでしょ?」
「うん」
「そうすると、5人か6人以上はB型なんだよ」
「ええ、ホント?」
「うん。ホント、ホント。だけど血液型なんて、アテにはしてないけどね。B型ってさ、我が強くて、個人プレーの人が目立つでしょ? それでAV嬢ってさ、なんていうのかな、もっとワタシを見てーとかさ、あとは自分は自分で他人は他人だからっていう、そんな攻めのノリ? 自分勝手? うーん、おバカ? そんなのがあるからさ、B型と合うじゃないかな。まあ、血液型じゃなくてさ、ひとつのタイプとしてね。ちなみにオレもB型だけど」
「ははは。あとは、どんなタイプがあるの?」
「うーん。あとはオレの場合だと、マジメな女のコかな。自分で言うのもなんだけど、オレってけっこう真面目じゃん」
「そうなの?」
「そういうことにしといてください」
「ははは、わかった」
「ありがとうございます。ねっ、真面目でしょ? ま、だからさ、真面目な女のコがスカウトできて、真面目にAVやっちゃうんだよなぁ」
「ふーん」
「最初のころは、やっぱり初心者の女のコがスカウトできたし。いいかげんにスカウトすると、いいかげんな女のコがスカウトできるし。慣れてくると慣れている女のコがスカウトできる。なんとなくわかるでしょ? 何をどうやってとか、相手をどうしてなんていう理屈じゃなくてさ、自分が感じたことをそのまま話してさ、それで相手が、うん、そうだねって言うあたりが大きいんじゃないかな」
「うーん」
「でも、おだてたりもするし、適当なことも言うけどね。ズッこけて笑ってごまかしたりもするし」
「ふーん、もっと理論的に話すのかと思った」
「理論的か。うーん、むずかしいな。オレさ、情けないことに中学と自動車学校しか、卒業できなかった男だよ。アッ、あと、珠算3級なんだ。これ小学校だな」
「あっははは」
「ウケすぎだよ。まあ、女のコって、理屈っぽいのはあまり好きじゃないみたいだね。だからね、そんな理屈でやり込めてもさ、その場はいいかもしれないよ。でも、また後で十分に考える時間があるわけだからさ。で、女のコってそれほどバカじゃないでしょ? とても理詰めで撮影現場までは動かないよ」
「うん。でも、信じられないな」
「なにが?」
「だってね、そういうコって、結局、お金のためにAVやるんでしょ?」
「そうだね」
「よくできるね」
「うん。むずかしいな、お金のためにってさ。あのね、ひとみもさ、モデルでおカネを手にした限り、お金のためにって言えるよね?」
「それとこれとは違うでしょ?」
「でしょ? だから、むずかしいんだよ。お金のためにってさ。そうだとも言えるし、違うとも言えるし。ひとみだけじゃなくって、例えばサラリーマンだってさ、お金のためだろって言えば、そうだとも、違うとも言うだろうし。だからいきなりお金のためにって結びつけるのは、ちょっと乱暴な言いかただね」
「・・・」
「でもひとみの言いたいことはわかるよ。確かにAV嬢とお金のためって納得できるし、説得力もあるしね。けど、スカウトのときは、それほどお金のためにって言わないなあ」
「どうして言わないの?」
「うーん。どうしてかって?やっぱりむずかしいから。お金のためってさ」
「どこがむずかしいの?」
「うーん。まあ、3万でも300万でもおカネだし。AVのギャラだってお金だし。でもお金はお金だからさ。それで、なんていうのかなぁ。理由っていうのかな、うーん、価値っていうのかな」
「がんばれ」
「もう、そろそろ、頭から煙が出てくるな」
スカウトするときには、強い理由が必要になる。
しかし、おカネの為にという理由は、以外に脆くて弱い。
簡潔に言えなかったのは、彼女の質問が難しく感じたから。
こうして日記に書かないといけないなんて、鈍くさいこと、我ながらはなはだしい。
自分は何を言うか

「あのね、オレが、お金って大事なんだよっていうでしょ」
「うん」
「ホントにそう思ってるんだなって気がしない?」
「うーん、どうかな?少しはするかも」
「するとすれば、オレがお金で何度も失敗してるから。それがね、オレがフェラーリに乗りながら、お金って大事なんだよって言ったら、嘘っぽくない?ダマしてる感あるでしょ?」
「まあね」
「だから、言葉じゃないんだよ。何を言うだとか、理論だとか、そういう言葉じゃなくて、誰が言うかなんだよ。そうだな、自分は何を言うかだな」
「自分は何を言う?」
「うん、そうか。お金とかの話じゃない、そっちじゃないか」
「・・・」
「このまえ、ひとみさ、ラウンドガールのオーディション、その最終選考、あれデート最後まで、それがダメだって言ったよね?」
「うん」
「で、オレ聞いた。なんでダメなのって」
「うん」
「そのとき、お母さんって言った。即答で、迷いなく」
「そうだもん」
「そこなんだよ。そのとき考えたり、迷ったり、彼氏だと言ったりだったら、もっとAVの話してた」
「え、彼氏って怒らない?ふつう?」
「そうなんだけど、もっと反応を見たい」
「なんで彼氏がダメなの?」
「性教育なんだよ。母親からの」
「・・・」
「性教育ってマンコにチンコが入るっていう知識じゃなくてね。生理がきたら子供ができるでもない。セックスのときゴムしなさいとかの話でもない」
「・・・」
「セックスをしてお前が生まれた、ね、好き同士でセックスをした、で、お前が生まれて本当にうれしい、それでお前が生まれてきたのはすごいことなんだと」
「・・・」
「お前が生まれたのはほんっとうに意味があるんだっていう生、生きるの生ね、そういう意味の生教育。これをひとみは受けているんだよ」
「・・・わたし、お母さんにそんなこと言われたことないよ」
「だから言葉じゃない。言われなくても、ひとみは感じることができている。オレには表情から透けて見える」
「わかるの?」
「わかる。特にひとみはすっごくわかりやすい。あのね、温かさなんだよ。寒いときとか、そういう時に温かさって感じるよね。そういうのって実感しないとわからないんだよ。ひとみは温かさを実感してる表情だよ。だからモデルもできる」
「モデルは関係あるの?」
「ある。まず自分。まず自分が100パー。まず自分が温かさを十分に感じることができてないと。内側からね。胸あたりだね。ポッカポカに。それから初めて他人を温かくすることができるんだよ。そういうのって」
「そうなのかな?」
「心が冷え冷していて人に何ができる?頭では理解してるとか理論的にとかで温かさが伝わる?自分が実感してるから伝わるんだよ」
「うーん」
「あのね、実際にいるんだよ。頭がよかったり育ちがよかったりしてもAVやるコって。それこそおカネに困ってなくてもね」
「いるね」
「あれ生教育を受けてないんだよ。生きるの生ね。その部分は育ちとか学歴とか、職業だとか金持ちとか関係ない」
「ふーん」
「で、男から間違った性教育を受けちゃうんだよ。やらせろっていう性教育ね。だから彼氏に悪いってコには、もっとAVの話する。ちょっとでも考える素振りだったら見込みはあるよ」
「・・・」
「なに言ってるのかわかる?」
「なんとなく」
「あ、そう。オレはもう、訳わからなくなっちゃったよ」
「ははは」
「ま、ケーキ食べよ」
「うん」
「といっても、いつまでもできないなぁ。こんなスカウトなんて」
「ふーん」
ちょっと話すぎたかも。
彼女自身は、その温かさがこもっている笑みの強さには、気が付いていないのだろう。
自分には大切な価値のある笑みにも見えていた。
しばらくして新宿プリンスを出た。
途端に歌舞伎町からの雑音と、日が落ちたあとの冷たい風が体に当たる。
彼女とは新宿駅まで歩き別れて、冷たい風でバラけた黒髪とヒップラインを見送った。
もうそろそろ、帰宅途中の通行人が増える時間帯。
ぶらぶらとスカウト通りまで歩いて、人混みの中で立って背筋を伸ばした。
長い休憩時間だったけど、あとは1歩踏みだせば仕事開始。
彼女にあんなこという自分も、温かさを感じることができるようになったのはここ最近。
智子のおかげ。
スカウトのおかげでもある。
女に対して、いや人に対して、広い気持ちが持てるようになった気がする。
でも致命的なことがある。
30代に差しかかって、やっと感じることができたということ。
だから今、地を這いずり回る、文字通りの底辺の仕事をしてるのかも。
でもそんなことはいってられない。
人並みぐらいには感じることができる人間だと自分でわかることができたから。
これからは、ちょっとは女を大事にしていく。
で、ちょっとは温かくしてあげたい。
– 2003.12.15 up –
