自分はなにをしたいのか決める
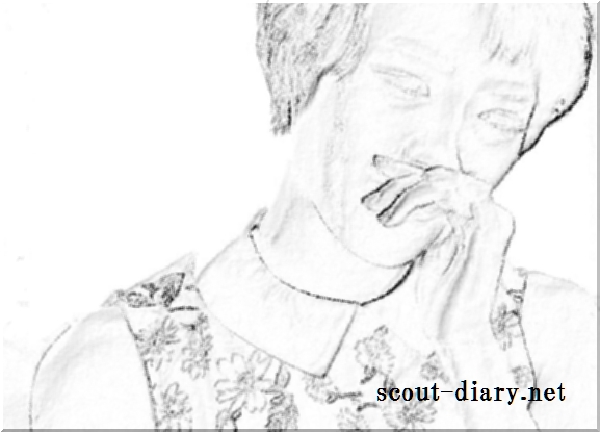
翌日は、午後の半ばからスカウト通りに集まった。
昨日の勝負はつかなかった。
いけそうだった、おしかった、と1時間ほど繰り返したところで、雨が降ってきたのだった。
サンパークのチキンカツ定食は、ビール付きで3人にふるまった。
遠藤の敢闘賞としてだった。
声をかけた女の子の足が止まったのだ。
電話番号は交換できなかったが、とりあえずは話せた。
キャバクラだったらやってもいい、という女の子だった。
この「キャバクラだったら」と引っかかる女の子は多い。
当然、スカウトバックは安い。
この場合は、自分の都合で押してダメなら切っていく。
余計な1人に時間をかけずに、広く浅くスカウトしていかないといけない。
が、遠藤は。
相手の要望とおりに「どこかキャバクラってありませんか?」と、こちらにUターンしてきた。
こうなったら、スカウトは行き止まりになる。
スカウトってのは、そんなメッセンジャーのような、キャンペーンのような、バイト情報サービスみたいなことをしていたら意味がない、というのをメシを食べながら言って聞かせたのだった。
「どう話せばいいのかわからなくなったっす」と遠藤は首を傾げる。
どう話すかよりも、まずは自分がなにをしたいのかが決まってない。
声をかける前に、そこが決まってないからわからなくなる。
あれもしたいこれもしたい、あわよくばこうしたい、と話そうとするからわからなくなる。
こちらがわからないまま話してれば、女の子は絶対についてこない。
目的が始まりを決める。
目的から逆向きに追ってきて、今はなにを話すか決めていく。
とはいっても、結局のところは習うより慣れろだが、目的の方向と距離は教えてあげないといけない。
遠藤の今の目的は、おっぱいパブの面接に連れていくこと。
しかし近いうちには、AVプロダクションに入れ込みたい。
そういう遠藤に、方向と距離が想像できるようにスカウトの実例をいくつも話したのだった。
紹介をアテにしていたらスカウトで食っていけない
天気は薄曇り。
いいのではないか。
今の季節、スカウトするのには、快晴よりも薄曇りのほうがあがる。
平日の午後となったスカウト通りの女の子はまばら。
遠藤と谷口は、もうスカウト通りにいた。
街路樹の支柱にペットボトルを置いて、その傍らに2人して立っている。
「ちょっと遅れます」と、島田からは電話があった。
女の子を1人、吉原のソープへ面接に連れていくという。
昨日から、電話でやり取りしていた元ホストからの紹介。
島田のスカウトは、かなりの部分が紹介で成り立っているようだ。
顔を合わすと、待ち構えていたかのように、谷口が質問してきた。
「声をかけてもダメだった女の子に、誰か紹介してって頼むのはどうですか?」
「紹介はオマケ。最初からはしないほうがいい」
「なんでですか?」
「紹介をアテにしてるスカウトなんて食えない」
疲れる質問でもあるけど、すべて答えようと決めていた。
教えるのが楽しくもあったからだった。
2年間、スカウトから離れていたことで、方法が整理されている気がする。
で、紹介だけど、そんなのをアテにしていたらスカウトは進まない。
基本は街頭でのスカウトだ。
女などその辺で捕まえることができる、いつでもできるんだ、という力がスカウトの源泉。
女の子へのお願いは、そこに両立しない。
昨日、メシを食べながら、スカウトってのはキャンペーンじゃないって力説したのに。
なにをきいていた、といいたいが、まあいい。
自分の数字を持つ

遠藤にとっては、昨日は悔しかったらしい。
メッセンジャーだの、キャンペーンだの、と評されて。
あれから、夜間のうちに3時間の発声練習をしてみて、朝イチで100均にいって計数カウンターを買い、さらに、公園で2時間の発声練習してきたばかりだという。
発声練習の効果は目にみえていた。
昨日とは違い、やみくもに足音をたててダッシュしてない。
すすすっと相手の視界に入り込む。
足の運びから、手の振りから、声の出し方にリズムもある。
背筋を伸ばしているのがいい。
距離をつめて「こんにちは」と声をかけるときには手の振りをつけている。
「スカウトですけど」と相手の歩調に合わせて続けて「キレイなんで声かけました」と背筋を伸ばして言えている。
びしっと相手の顔を指差してそれを言う。
そのときには水平に指先を動かしているのが格好つけているようにも見える。
が、むさくるしい風体の遠藤がこれをやると、なんだかコミカルさが帯びている。
パンチが効いているというのか。
目の端でちらっと遠藤を見た女の子は、すぐに顔をぷいっと反らして早歩きして通り過ぎていくが、その背中が笑っている。
こうなると、スカウトできるのは時間の問題だ。
あとは、自分の数字を持つことをアドバイスしたい。
「ここだったら、1日100人ペースで声をかけてみな」
「100人すか!」
「数字があってさ」
「はい」
「まあ、だいたい10人か、いっても20人だったりもするけど、それくらいに声かけたら、1人くらいは足が止まる」
「はい」
「で、AVのスカウトですって話すと、ほぼ全員が断りだけど、その断りが2人と3人と続くうちに、今すぐじゃないから考えてみてよって電話番号を交換できる女の子もでてくる」
「はい」
「この1人が見込み。で、この見込みが10人になると、1人はAVに持っていけて、風俗をやるのが3人が目安かな」
「そうすか」
「うん。だから、結果から追っていくと、1日に100人には声をかけたい」
「100人なんて、声かけれるかな・・・」
自分でも、あれっと思った。
100人に声をかけるは正確な言い方ではない。
「そっか、100人に声をかけるっていう、言い方がよくないな。100人に当たるだな」
「当たるすか?」
「だから、昨日話した、正面からの視線と、初動で見極めるのが必要になってくる」
「はい」
「いい、ここで相手に声が届くなんて50センチくらいだよ。周りもうるさいし。せいぜい手が届くくらいの距離しか声は届かない」
「はい」
「その状況で100人全員に50センチまで近づいていって、どーも、なんて声をかけるところからやっていたら時間が足りない」
「はい」
「だから、向こうから歩いてくる100人の中に、こっちに気がついている女に当たるっていうのか、目と手で合図してから様子を見れば、50センチまで近づいて声かける必要がない」
「はい」
実際に100人に当たってみる
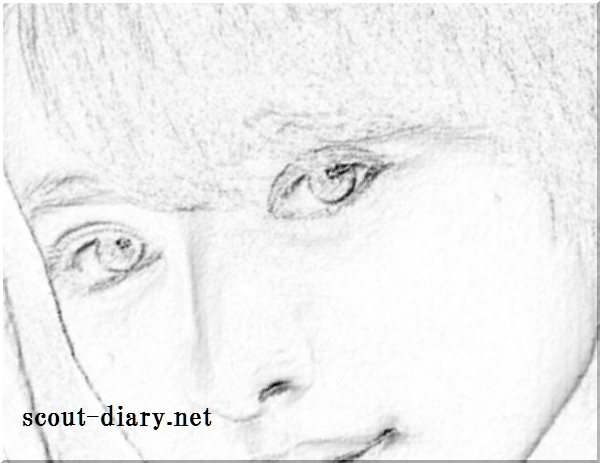
実際に100人にやってみようと前を向いた。
2本目の街路樹の向こうに、元気がいい足取りで歩いてくる女の子がいる。
やはり、元気よくチラ見をしてきた。
「あの女、もう、こっちに気がついている」
「はい」
遠藤に言いながら、女の子に対しては、胸の前に挙げた手を小さく左右に振った。
また彼女はチラ見。
すぐに目を反らした。
拒否をあらわにした不機嫌な表情で、そのまま歩いてくる。
「ちょっといってくる」と1歩進めると、彼女は目の端で見ている。
ゆっくりと3歩も進むと、彼女と向き合うほどの距離に。
「どーも」
「・・・」
彼女は無視を決めこんでいる。
どんどんと早歩きとなっている。
「こんにちわ」
「・・・」
歩く前に手の平を差し出したが、それを跳ね除けて素通りしていった。
自分は足を止めて、白のピタパンのヒップラインを見送った。
街路樹に戻ると、すぐに次の女の子は現れた。
細いデニムの歩きが固い。
「ほら、あの女」
「はい」
「見た目はいい」
「はい」
「ほら、チラ見してきた」
「はい」
隣の遠藤と話ながら、向けてきたチラ見に合わせてすぐに手を挙げた。
途端に、警戒の表情で早歩きとなる。
けっこうな早歩き。
こちらの歩調が追いつかない。
というか歩調を合わせて距離が詰めれない。
「今から、あの女に近づいていって声かけるのはさ、いけるかいけないかってよりも、時間のロスでしょ」
「はい」
「あえて、そこいかなくても、女はまだ歩いてくるし。だから次。これで、2人に当たったと」
「あ、はい」
その後ろから姿を見せた女の子は、大きめのサングラス。
目は口ほどにものを言うとは本当だ。
反応がわからないから、サングラスはやりずらい。
しかしスカウトは、先入観と違うことをやると以外とすんなりいくものでもある。
「あの、デカサンの女・・・」
「はい」
「やるだけ、やってみるか、3人目」
「はい」
3歩進んで止まり、通行人を2人やり過ごして、デカサンの女の子の目前で「どーも」と手を挙げてみるが、前を向いたまま素通りされかかった。
後ろに大きく1歩下がりながら、もう一度、「こんにちは」と手をかざすが、デカサンの顔は少しもこちらを向くことはない。
自分は足を止め、女の子は無視のまま通りすぎた。
歩調と心臓の動悸って同じ
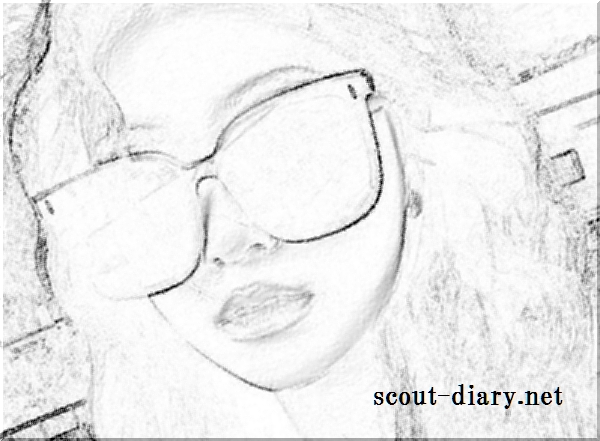
デカサンの女の子の後ろ姿を見送る。
元の場所に戻った。
「まあ、デカサンの女はこんなだろうな」
「はい」
「イヤホンしてる場合は外すこともあるけど、サングラスは外さないな」
「はい」
次に姿を見せた女の子は、アルファベットがプリントされたカットソーで、俯いたまま歩いてくる。
チラ見もしてこないし、こっちにも気が付いてない様子。
手振りするまでもないし、こっちに気が付いてない相手にいきなり声をかけても、驚かれるところからはじめないといけない。
中には、声が耳に入っても、自身に声がかけられていると気がつかない場合もある。
「あの女、アルファベットの女にいってもいいけど・・・」
「はい」
「その後ろの女、ジャケットの、いま、チラ見してきた」
「してきました!」
すぐに自分が手を挙げて、1歩だけ足を進めた。
アルファベットのほうは、やはりこちらに気が付かないまま歩き続けている。
ずっと後ろを歩いているジャケットのほうは、もう一度、チラ見をしてきた。
ジャケットはオフホワイトのロングで、サイズ感がいい。
アルファベットの女の子は見送りだ。
ジャケットの女の子にまた手を挙げて1歩進むと、えっという目を向けてから、随分とわざとらしくぷいっと反らした。
すっすっとしている歩調は変わらない。
いい歩調をしている。
このときの歩調と心臓の動悸って同じだと、自分は勝手に思っている。
警戒で心臓音がドクドクしてれば早い歩調で、気分がよくトクントクンしてる心臓音だと、いまの彼女くらいのすっすっしている歩調。
AVや風俗はやらないにしても、とっかかりさえあれば話は弾んでいく。
「ちょっといってくる」と1歩だけ踏み出した。
ジャケットの彼女の歩調は変わらない。
そのまま歩いてくる。
顔は反らしたままだが、視界の端でこちらを見ている。
通行人を1人やり過ごして、ゆっくりと1歩寄ると、彼女とすれ違う目前だった。
その足元の動きを目のどこかに入れながら、前に手を差し出して、手の平を上下させた。
思いきりマヌケそうに言ってみた。
「どーも」
「・・・」
うつむき気味の横顔の口角は、わずかに上がっている。
ぐいっといこう。
「こんにちわ」
「・・・」
言いながら前に回り込んで、対面したまま、手でストップのゼスチャーをしながら2歩3歩下がった。
彼女の足元がすすっと止まったのが、目のどこかで見えた。
「とつぜん、ごめんね」
「・・・」
「時間とらせない」
「・・・」
強引に足を止めけど、表情には警戒も嫌悪も浮かんでない。
まつ毛がカールした大きな目が、ぱちっと瞬きしただけだった。
「あやしい者ですけど」
「・・・」
小さく鼻先でくすっとしたのはいいけど、なんの問いも目にはでてこない。
足先は完全に止まっていて、急ぐ素振りはない。
これは、スカウトの類をあしらうのに慣れている女の子だ。
「お店やらない?」
「・・・」
咄嗟の断りが出てこないし、わずかに小首をかしげただけ。
目には問いの陰りすらも差さない。
これはもう、すでに店に勤めている女の子か。
平日の今に歌舞伎町に向かっているから、専業で現役の風俗の女の子か。
出勤前だろうけど、急いでいる素振りは見せない。
話はきくつもりだ。
「これから、お店いくところだ?」
「・・・」
「どこだろ?○○○かな?」
「○○○・・・」
「中通りのソープだけど」
「ちがう、ちがう」
まだソープは抵抗あるの、と言いたげに首を振っている。
店は教えないという彼女に、じゃあ当てるとヘルスを2店ほど確かめていると彼女が止めた。
「まって、そんなにもいったら当たるでしょ」
「うん、わかった。じゃ、きかないけど」
たぶん、次に確かめようとした店あたりに在籍しているのだろう。
彼女は片足に重心をかけた。
あと1分は、話しを聞くつもりだ。
「今、お店っていそがしい?」
「うん」
「どうかな?ウチのお店でがんばってくれないかな?」
「ムリムリ、やめれない」
どこの店かも訊いてこず。
条件も確かめようともせず。
その気がないのか。
この場合は、まだ詳しい内容は話さないほうがいい。
「わかってる。そうじゃないかなって思ったけど」
「残念だね」
「まあでも、今、すぐじゃなくってさ、待ってるからさ、そのときは連絡ちょうだい」
「やらないよ」
「そうか。あきらめるしかないか」
「そうだね」
「じゃ、番号だけ交換しよ」
「あきらめるんじゃないの?」
「そうだけど、1週間後に1回だけ電話させて」
「なんで1週間?」
「状況かわることだってあるでしょ?」
「ないない」
「気だって変わるでしょ」
「変わらないし」
「それでも、まったくダメだったら、そのときはハッキリと断ってよ」
「・・・」
「もう、口もききたくないってときは着拒でいいし。そしたら、もうあきらめる」
「1週間ね」
「うん、1週間。今ぐらいの電話でだいじょうぶ?」
「たぶん、だいじょうぶ」
普段は店は遅番から。
今日は写真撮影のために、早めに出勤するところだという。
気分がよさそうだったのは、その辺だったのかも。
番号交換したのが区切りとなって、バイバイした。
100人に声をかけるというより通り過ぎていく100人に当たる
元の街路樹に戻る。
足元に置いてあるペットボトルの水を一口飲んだ。
さっそく谷口が訊いてきた。
「どうでした?」
「ムリだった」
「え、ムリでした?」
「んん。あの女、今、歌舞伎町でヘルスやってるって。今度、見かけたら声かけてみ、AVやろって。撮られるの好きそうだし」
「引き抜きはしないんですか?」
「本人にその気がない。店だって離さないでしょ。強引はよくない」
「せっかく話したのに、なんかもったいないす」
「それこそ浅く広くだよ。それにさ、今の店が稼げないって、すぐにスカウトできる女って、すぐに同じこといってやめるよ」
「そうすか?」
「うん。すんなりと話を聞いたり、簡単にやりますってついてくる女もいるけど、トビもすぐだから、そういう女って。後回しでいい」
「そういうものすか・・・」
「やってればわかるけど、けっこういる。そういう女も適度に切っていかないと、いい女があげれなくなる」
やはり狙うのは、ちょっとイヤイヤしている女の子。
ムリとか、ダメとか、ツンツンしているくらいのほうがいい。
さっきのジャケットの女の子にしても、1週間後に電話して出たとしても断りだろうけど、おわびにケーキをゴチしたいからはじめてもいい。
なぜなのか谷口は訊きたがるが、話を元に戻した。
「最初の早歩き、2人目も早歩きだったか。3人目がデカサンか。4人目がアルファベットの女で、5人目が今のヘルスの女か」
「はい」
「5人目で、足が止まって番号交換だったらいいペースだな。こっちの用件だけは伝えての番号交換だから」
「はい」
「まずは、ここまでできれば、半分はスカウトできたもんだよ」
「ホントすか?」
「半分はいいすぎか。でさ、5人っていっても実際に声かけてないのも人数にいれてるけど、まあ、1日100人ってのは、通りすぎる100人っていうのか、目安っていうか、ペースをみるための100人だね。数えてるわけじゃないし。このペースだったら100人だなって感覚の100人か」
このスカウト通りだったら、100人というと平日の昼間だったら3時間弱となる。
1時間30分経ったから、あと1時間30分やろうと目安になる。
「でも実際は100人いかずに、20人から50人も当たれば、どうしようかなっていう女にぶつかるけどね」
「そうすか」
「それでも、ダメな日もあるから、そんな日は100人当たったから、その日はあきらめるっていう目安の数字になる」
「なんで100人なんですか?50人でもよくないですか?」
「まあ、50人でもいいんだけどな。でも100人ってキリがいいし。3時間っていうのもキリがいい。ペースがわかりやすいし」
「あ、はい」
確かに100人に近づくにつれて、相手の反応もわるくなる。
100人以上に声をかけて試してもみた。
何日も試してみた。
結果としては、さらに反応はわるくなるだけだった。
数字をこなすだけの惰性になってしまってるのが、相手に伝わるのかもしれない。
ちょっとしたことなのだと思う。
とにかくも。
100人というのは、なにかある数字なのは確かだ。
スカウトの上達は階段状となっている

遠藤はまだ実感してないだろうが、スカウトの上達は階段状となっている。
坂道を登るように上達する、という実感はない。
声をかけても無視ばかり。
足が止まった女の子にAVや風俗を推しても断られ続ける日が重なる。
それがある日。
突然に変わる。
今まで進展しなかったことが、なぜかあっさりとできるようになる。
見えていた次の階段に足をかけることすらできなかったのに、ある日からは次の階段にすんなりと上がれるようになっている。
上がってみると気がつく。
今まで足踏みしていた、下の階段を見下ろすことができるのに気がつく。
少し前の自分と、今の自分を比べることもできるようになる。
その階段を上がった実感を4回か5回ほど。
いや、5回もない、3回か4回も重ねれば、もうスカウトの方法で悩むことはなくなる。
それまでは、数字を追いかけるのみだ。
100という数字は目標から外せない。
– 2022.1.9 up –