すんなりと止まる足はよくない

暗くなりかける時間帯だった。
スカウト通りの人通りは、新宿駅東口から歌舞伎町方面に向かう流れとなっている。
多数を占めているのは、西武新宿駅への乗り換えの帰宅者。
その一団が大きな足音を放っているのは、スカウト通りが緩やかな坂になっているのもある。
新宿駅側が高い。
歌舞伎町側が低い。
緩やかな坂であっても勢いがついて、全体がつられて、昼間と比べて歩調を早くさせている。
そんな時間帯だった。
声をかけても無視の素通りが連続していた遠藤だったが、昨日の勝負の続きを言ってきた。
勝つつもりでいるらしい。
「じゃ、あれだな、店でもなんでも、すぐにやるとかじゃなくても、考えるでもいいし」
「はい」
「そんな話して、さきに電話番号を交換したほうが勝ちな」
「はいっす」
勝負が開始された。
遠藤は新宿駅方面に向けて、足早の通行人をかわしながら歩を進めている。
谷口は1歩も動かない。
自分は歌舞伎町方面を向いていた。
すぐに、向こうから歩いてきた女の子と目が合い、少しばかり手を挙げてみた。
声をかけるのに、コツもなにもない。
最初の1人目くらいは、いってみればウォーミングアップのつもりで軽くやってみる。
そのつもりだったが、彼女は表情も歩調も警戒に切り替わらない。
自分が足を2歩ほど進めただけで、まだ間があるのに向こうの足は止まった。
足が止まるのはいい。
が、すんなりすぎる。
「あやしい者ですけど」
「・・・」
声をかけると、くすくすと笑っている。
笑ってくれるのはいいが、すんなりすぎる。
見たところ20代前半。
ジャケットとチノパンの整った服装に、肩からのトートバッグ。
勤め人だろうな、との見当はついた。
もしかして歌舞伎町の風俗嬢で、店をあがっての帰りがけかなとも頭にかすめた。
が、しっとり具合の髪にも化粧のノリにもシャワーの形跡はない。
反応がすんなりすぎるのは、ナンパ慣れしてるからか。
好奇心からの冷やかしか。
でも街路の光で頬がかざされて、軽く酒が入っていると気がついた。
「あれ、少しほっぺが赤いけど、お酒でも飲んだの?」
「うん。ちょっとだけ」
「ちょっとって、日本酒3杯くらいかな」
「ビール1杯だけ」
飲んだ帰りか。
すんなりは、仕事終わりの解放感だったのかもしれない。
いずれにしても、お友達口調のすんなりすぎる女の子には遠慮はいらない。
「風俗やってみない?」
「・・・」
「とつぜんですけど」
「・・・」
「お店は歌舞伎町ですけど」
「・・・」
瞬間だけ、目が開いたのは驚き。
咄嗟の断りは出てこずに、今度は吹きだして笑っている。
この驚きを誤魔化した笑い方からすると、風俗は未経験に見てとれる。
「じゃ、明日からやってみる?」
「ちょっと、まってよ」
「あ、ここさ、人通るからさ、こっちで話そ」
「・・・」
「どうせ、ヒマなんだから」
「ヒマじゃない!」
『ちがう』というような表情でムキになった女の子は、多めに話す。
話が転がっていく瞬間となる。
女の子が多く話そうとした瞬間はいったん止めて、道端に寄ってみる。
そうすれば、あと3分は話せる。
その間に、こちらの言いたいことだけは言えばいい。
自分が街路樹まで下がると、彼女はすんなりと寄った。
この様子だと、ここからはゆっくりでいい。
先の街路樹の脇では、自分の状況に気が付いた遠藤と谷口が、一緒になって成り行きを見ている。
「彼氏に怒られる」との断りは期待できる

彼女は仕事帰りだったが、なんの仕事かまでは言わない。
お友達口調で応えてくれるが、どこまでどうやって帰るのかも一端ですら明かさない。
口元は楽しそうに笑んでいるのだけど、目には好奇心が浮かんでいるけど、どこにも疑問が潜んでいない。
「じゃ、話だけ聞いてよ」
「聞くだけね、やらないけど」
「うん、もちろん、今すぐにじゃないから」
「あとになっても、やらないよ」
「そうだろうけど、ちゃんと話を聞いてから、1回、考えてもらえる?」
「考えても、ぜったいやらないよ」
「いいよ、それでも。ムリにとか、なにがなんでもとか、ないから」
「でも、やらない」
はやり疑問を出してこない。
これじゃ、店の話をしても右から左。
内容を詳しく話す必要はない。
好奇心からの冷やかしだったか。
「うん。今の仕事やめて、お店でがんばろうなんていわないから」
「いってるっ」
「そんなこといわない。お店の面接いつにしようなんて、口が裂けてもいわない」
「いってるよっ、もう」
しかし、お店の面接といっても自分がするのだから、この言い方だとなにか変だ。
もし面接となったら。
『実は私が店長でしたぁ!』と明かして、いきなり脱いでチンコ出してみるのも面白そうだ。
まだ店がないから、そのくらいしてもいいだろう。
いずれにしてもだ。
今は細かいことはすっとばす。
「まあ、そうだよね。誰に怒られるの?」
「怒られは・・・、しないけど」
「え、彼氏は?」
「怒られる・・・、ってよりも、できないでしょ?」
「そう?変わってるよね?」
「ふつうでしょ」
『誰に』の問いの答えが『彼氏に怒られる』だったら、まだ先には期待できた。
その答えを口にするとき女の子の目には、さっと走るなにかがある。
影が走った気配がする。
目の奥にわずかに影が走るのだ。
感情が走るのだというのは、その後の声の変化から感じる。
理性や常識で『できない』と断っていたところに、得も知れない感情が紛れ込むのだった。
相手は感情的になってくれたほうがいい。
取り繕った返事よりも、より本音に近い話に進む。
実は、彼氏がいないだけかもしれない。
が、彼氏の反応を気にしてない彼女は、十分に理性と常識で断ってきている。
少しは感情的になってくれないと先が厳しい。
ただ、今の彼女の目にあるのは好奇心で、これがある限りは、もう少しは先を試してもいい。
好奇心は風俗への十分な原動力になる
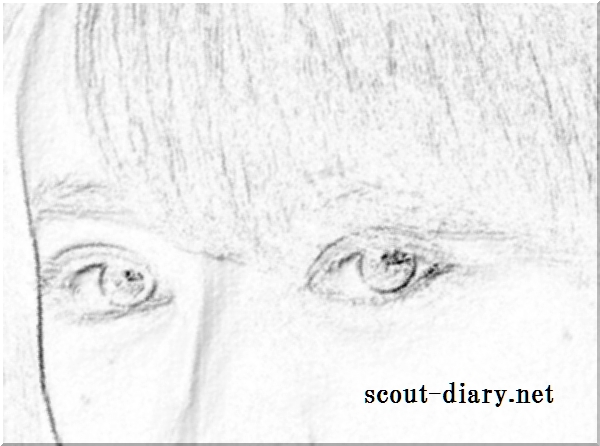
好奇心は本体を振り回すもの。
風俗への十分な動力になる。
知らないことに飛びつく、思い切りの良さも伴う。
この場合は、他人事を楽しんでいるだけかもしれないが、もう少し度合いを確かめたい。
彼女の足元も動く素振りがない。
「新宿駅から帰るところだったんだ?」
「うん」
「ごめんね、ヒマなところ」
「ヒマじゃない」
この時点で、なんらかの感触が少しでもなければ、このあとお茶をしようが、2時間話そうが3時間話そうが、スカウトできないのは目に見えている。
彼女の場合は、お茶くらいは応じてくれるだろけど、無駄になる率は高い。
おしゃべりして仲良くはなれるが、彼女のような相手だったらそれは楽しいことだが、いずれの態度もスカウトと両立しない。
「でも話してみると、それほど、オレってあやしくないでしょ?」
「ううん、やっぱ、あやしくなった」
「適当なことはしない、約束する」
「そうかな」
少し笑の笑みがひそめられた。
少し首をかしげて、じっと目を見てきた。
ここからは2択だ。
この先をダメ元で試してみるか。
後日の約束をして、電話番号を交換をしてバイバイするか。
ここの選択は、相手がどうのというより、ただ単にこちらの時間の使い方の問題。
最初の1人目でこれだったら、いいリズムに乗れている。
そのリズムを止めてまで、ダメ元の女の子と話して1時間が過ぎるのは悪手。
その1時間を今のリズムのままで動いて『いけそうだな』と感触が得られる次の女の子に当たる確度のほうを取ったほうがいい。
リズムがいいときは、感触がつかめる女の子に連続して当たるものなのだ。
そうなのだけど、先の街路樹の脇では、遠藤と谷口が成り行きを見ている。
「じゃ、どこか、座って話そ」
「う・・・ん」
「だって、まだ、名前もきいてないし」
「う・・・ん」
「そのときにダメならダメで、はっきりと断ってよ。オレ、断られるのって慣れてるからさ」
「う・・・ん」
「どうせ、ヒマだろうから、3時間くらいだいじょうぶでしょ?」
「ムリムリ、ヒマじゃないし」
「じゃ、30分」
「ほんとに30分?」
「うん、約束する」
「う・・・ん、約束ね」
「うん、おいで」
「おいでって・・・」
「おいで」
「・・・」
しっかりと後のことを念を押してくる彼女には、思いきり子供扱いして「おいで」と手招きをしてやった。
背を向けて歩いた。
ちらと見ると付いてきていた。
街路樹の脇に立って見ている遠藤と谷口の前まで歩いて「彼女、店の話をきくっていうから、ゆっくり話してくるわ」と言い放った。
これをやりたかっただけだった。
冷やかしなだけでスカウトはできないだろうな、という見当はついていたが、2人との勝負に勝ちたいがために。
2人は黙ったまま、目は開き気味にして頷いている。
勝負には勝った。
速攻で。
気分がよかった。
照れ笑いと受身の態度を確かめるのもコツといえばコツ

座って話そう、とは言ったがどこにしよう。
今の時間はイタトマは混んでいるからなと、ちょうど青信号になった歌舞伎町交差点を彼女と渡った。
ドンキホーテのテーマ曲が聞えてきた。
「名前、なんていうの?オレ、田中」
「田中さんね、わたし、小野」
「ちがう、下の名前」
「え、わかな、だけど」
「ああ、わかなって感じがする。すっごくカワイイね」
「てきとうだし」
「うん、ほんとに。すごくカワイイよ」
「ほんとに、おもってる?」
「うん、おもってる。わかなって呼んでいいでしょ?」
「うん、いいけど」
『カワイイ』に対しての照れ笑い。
呼び捨てOKからの照れ笑いもしている。
さっきの子供扱いの『おいで』にも照れ笑いしていた。
このあたりに、こんな反応する女の子は、受身の態度をしてくれる。
もっと、ずうずうしく接しても失礼にはなりずらい。
横断歩道を渡りセントラル通りに入ると、歌舞伎町の騒がしさが押し寄せた。
「あのさ、わかな」
「ええっ」
「どうしたの?」
「やっぱダメ。呼び捨ては」
「えっ、なんで?」
「なんか、呼び捨てになったら態度が変わった」
「そうかな、気のせいだよ」
「ううん、急に変わった」
「あ、そう。じゃあ、わかなちゃんだ」
「・・・」
「わかなちゃん」
「やっぱ、ちゃん付けもダメ!」
「ええぇ、じゃあ、オマエな」
「それもヤダ!」
「じゃ、きみ?」
「それもへん!」
「なんで?なんでなにも呼ばせてくれないの?やっぱ変わってるっていわれるでしょ?」
「いわれない」
「え!かなり変わり者だよ。オレがびっくりだよ」
「もう、こんな人はじめて。歌舞伎町の人って、みんなこうなの?」
「歌舞伎町は関係ないでしょ?」
「ある!」
自分の非常識な言い分を、いかに街路にこもっている騒がしさが後押ししてくれていて、彼女をついてこさせていることか。
外見と話し方だけで、彼女を連れて歩けていると思うほど自信家ではなかった。
今、座って話すのにいちばんいいのは、街路の脇の縁石か鉄柵。
ジャケパンを着こなしている社会人の彼女が、それを許すのならばだけど。
かといって店内に場所が移ると、街路の騒がしさが絶たれて、この段階の2人の空気は平坦に戻って、話の続きに弾みがつきにくくなる。
たとえお洒落な店だったとしても、上質なオーダーができたとしても、それよりも今は騒がしさの継続のみが必要だ。
弾みを失った会話をまた大きく上振れさせるのは難しい

座って話すのが店だとすれば、ざわつきのある店がいい。
席も大事。
テーブル席に対面して着席したものなら、ざわつきのある店だとしても、2人の間の空気が変わってしまう。
あやしい話をするには、ざわつきがあり、かつ、横並びで座れるカウンター席がいい。
小さな丸テーブルの立席もいい。
ここを間違えると、席についてしばらくしてから、あれ、ここにくるまでは話が弾んでいたのに、と焦ることになる。
1度、弾みを失った話をまた大きく上振れさせるのは、さほど会話が上手ではない自分にとっては難しいこともわかっている。
「わかなでいいでしょ?」
「う・・・、ん」
「歌舞伎町だし」
「やっぱ関係あるんだ」
「うん。でさ、わかな」
「う、うん」
「え、まさか、照れてんの?いい大人が。だっせぇ」
「もう、やだ」
「おい、わかな」
「もう、こんな人やだ」
彼女は文句をいいながらも、結局は呼び捨てでいいとなって、セントラル通りを歩くうちには、開き直ったように明るく応じるようになった。
彼女は24歳。
彼氏あり。
中央線沿いの実家住まい。
そんな話をしながらコマ劇前に差しかかったとき、前からの通行人をかわすように見せかけて2歩ほど下がり、彼女のヒップラインを確めてみた。
前から見ると太腿にはチノパンがピタリと張り付いていて、これを後ろから見れば、さぞかし良型で肉感があるヒップラインをしてるのだろうな、と気になっていたからだった。
無性にお尻が気になる季節ってある。
季節の変わり目だから、これは発情期の名残かもしれない。
ともかくだ。
彼女のヒップラインは丸い形をしていて、左右にわずかに揺れて、曲面は張りのある肉感を包んでいた。
あろうことかだ。
うっすらとフルバックのパンティラインを浮かばせてやがる。
いや、浮かんでいた。
このままヒップラインを視姦をしていたい気持ちを、1秒くらいで振り切った。
「わかな」
「えっ」
「クラブいくぞ」
「えっ」
「すぐ、そこにあるから」
「うん、まかせる」
「じゃ、こい」
「なんで強気なの?」
コマ劇の5階にある『CODE』までエレベーターで上がるときには、最初にした30分だけの約束は、お互いに気持ちよく破棄された。[編者註60-1]
– 2022.3.12 up –