「バレる」という断りの重要さ

自分の話し方を丸ごとパクリたいと遠藤はいう。
パクリでやってみたいという。
「オレの場合だと・・・」
「・・・」
「なんだろう・・・」
「・・・」
「そうだな、まずはバレだな」
「バレ?」
「んん、AVのスカウトのときは、まずはバレを持ち出さないとだな」
「バレっすか?」
AVには多くて、風俗やおっパブには少ない断りの理由が『バレ』だ。
この断りの違いに気がついてから、AVのスカウトがやりやすくなったのを問われて思い出した。
公序良俗がとか、社会規範がとか、倫理や道義や道徳や宗教、衛生面や医学的見地、学術的視野などの断りの理由を全て足してみたとしても『バレ』のほうが断り理由としては飛びぬけて多い。
ということは『バレ』さえ取り除けば、ほどんどの断りは解消できることになる。
最初から『バレ』だけを見定めて話せば、それほど的外れではない。
「最初のダメとかムリが出てきたら先回りして、バレたらマズいの、とか訊いてみる」
「はい」
「そうすると、ほとんどが、当たり前でしょっとかなる」
「はい」
「ほとんどっていうのは、このときに2つに分かれるから。このときにバレに対して反応が割合と浅いようだったら、裸の仕事の経験者かもしれない」
「はい」
「おっパブも含めてだな。裸ってよりも、男がらみの仕事の経験者ってことか」
「はい」
経験者ともなると、そうそうバレるものではないとわかってくるから、未経験者と比べると『バレ』の反応が浅くなる。
仮にバレたとしても『裸になったくらいで、裸を見たくらいで、なにを騒いでいるの』という自負を見せもする。
「経験者だと確めれたら、もう条件を話してもいい。ショートカットで。金額の話にもなりやすい」
「はい」
「慣れれば経験者はやりやすい。けど、そこだけ狙っていたら、スカウトバックは大きくはとれない」
「はい」
経験者の自負はプロの頼もしさがあるけど、今の遠藤のスカウトの段階では、とりあえずプロの1群は後回しにする。
狙っているのは、未経験の女の子の1群の中の1人だ。
限定されている『バレ』
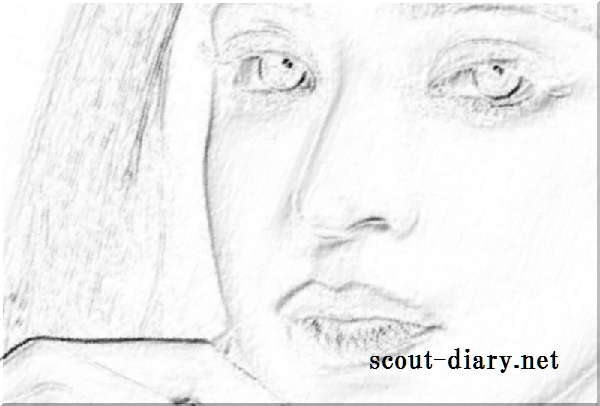
ひとつの事実として、それだけ『バレ』を気にしている未経験の女の子でも、AVプロダクションの宣材撮影で脱ぐときには、もう『バレ』は言わなくなる。
『バレ』ないという実例で、・・・たとえば、これだけメイクや写真で変わるとか、ほとんどが友達に話してしまうからとか、本人だと確めるつもりで観ないとわからないとかいう実例でわからせたのもあるが、同時に、もし万が一、バレても・・・という覚悟も少なからずできているものだった。
彼女らの気にしている『バレ』というものは、世間や近所や将来や学校や職場などといったつかみどころのない広範囲を指しているのではなくて、もっと限定されていた。
『誰か』に限定されていた。
終わりが始まりを決める。
とすれば『バレ』の背後にいる『誰か』を始まりから探ったほうがいい。
『誰か』に対しての『バレ』の解消を目指す。
「で、最初から1分で、足が止まってからの断りからの立ち話をしてる間の1分で、『バレたら誰に怒られるの?』って話に持っていく」
「バレたら誰にすか?」
「そう。バレたらカレシにってのはわかってるけど、あえて『誰に?』って。どうなるとかじゃなくって、『怒られる?』ってことだけ」
「怒られるすか・・・」
「で、このときに、誰にってのもハッキリしてなくて、怒られるには首をかしげたりしている女は、もう、まともに話を聞くつもりがない場合が多い」
「そうすか?」
「ひやかしかもしれないし。AVなんてバカにしないでよってプライドもあるのかもしれないし。まあ、そのあとの話が通じないかもしれないから、時間のムダになるかなって、この1分で切りかなって見当をつけるかな」
「なんでだろ・・・」
「カレシに怒られるって、女のほうから言ってもらいたいんだよ」
「・・・」
「どうしてすか?」
「感情を確めたいのかな。女がカレシに怒られるって言うときには、色んな表情が出てくるからさ」
「・・・」
「いい?最初は、AVだけどって言うと、警戒とか驚いたりとか、反射的にダメムリできないって99.9%がなる」
「はい」
「やっぱ、誰にだって、理性とか常識があるからさ」
「その断りに感情が交じってくると、話しやすくなる。よくさ、感情的に話すのはよくないっていうけど、スカウトは感情的に話さないと。相手も感情的にさせないと」
「感情的っすね」
「つっても、大声を出したりとか激しいことはダメだよ。静かにゆっくりと計画的に感情的に。あくまでも、理性的なのを装ってさ。理性のある断りに感情を寄せていく。そのとっかかりに、バレたら誰に怒られるっていってみる。むずかしいか?」
「う・・・ん」
『バレたら・・・』には、いろいろと組み合わせて試してみた。
たとえば、『カレシに』とか『お父さんに』とか『学校に』とか『会社に』から、『わるいの?』や『どうなるの?』や『マズいの?』や『恥ずかしいの?』や『気まずいの?』や『ケンカになるの?』などを組み合わせて反応を試した。
すると『誰に怒られるの?』との組み合わせが、割合とわかりやすい結果があった。
『怒る』は大きくてわかりやすい反応がある

遠藤は、よくわからないというように「うーん」と首をひねる。
谷口は、よくわかるというがごとく大きくうなずいている。
「それじゃ、遠藤さ、たとえばでいこう。実際にありそうな反応でいこう」
「じゃ、たとえば・・・、え、でも、そもそも、カレシがいないって女がいってきたら、どうするんすか?」
「そこまで、いってくれる相手だったら、もう、フツーに話していいんじゃないかな」
「フツーにっていうと?」
「ああ、やっぱりって意地悪いったり、やっぱカレシいないよねっていじってみたり」
「あ、そういうの得意っす」
普通に話すといっても、彼氏がいないことを最大の不幸とする女の子の気持ちのけば立ちを、それはそれで逆撫でしてみる。
彼氏いないの返事に限らず、女の子の気持ちを逆撫でしてみるのは、1回くらいは軽くしてみる。
女の子は『ちがうっ』とムキになるときは多めに話す。
「まあ、10人中、8人か9人は彼氏いるっていうよ」
「ほんとすか?」
「うん、ほとんどがカレシいるよ」
「カレシいても、AVやるんすね」
『バレ』に次いで多い断りの理由は『カレシにわるいから』という、生理なのか理性なのか罪悪感だかが交じった漠然とした理由。
この理由を口にする女の子も『バレ』と同様に、立派なAV嬢予備軍だ。
上位ふたつの断りの『バレ』と『カレシ』を最初から取り込んで話す。
「じゃ、なんで、最初から『カレシに』じゃなくて、あえて『誰に?』って訊くかっていうと、これは、もう、慣れとか勘になるけど・・・」
「・・・」
「多くがカレシに怒られるという。んで、そのときの表情だな。目の色っていうのか、目の光っていうのか」
「・・・」
決して上級ではない感情の『怒る』という言葉が、いちばん大きい反応がある。
ポーカーフェイスが得意な女の子だったら、この手は通用しない。
しかし、たいがいの女の子は『カレシに怒られる』と口にしたときは変化がある。
「それまでとは違う、なにかスッとしたものが目の中を通る。なにかが走るっていうのかな。それが、感情が振れたとき」
「・・・」
「それをね、こっちもアレッと感じるときもある」
「・・・」
目を開いてみたり、細くしたり、
目線が背けたり、落ちたり、流れたり、にらんでみたり、泳いだり、集中したり。
上を見たり、下を向いたり、傾げてみたり、首の振りが小刻みになったり。
ビクッと体を震わせてみたり、手を振ったり。
明るく笑んだり、曖昧に笑んだり、寂しく笑んだり、楽しそうに笑ったり、ただ単に笑いとばしたり、冷笑したり、ねじけたように笑ったり、逆に笑みが消えたり。
困り顔をしたり、不安な顔をしたり、泣き顔をつくってみたり、悩ましい顔をしたり。
口調も変わる。
嬉しそうだったり、どこか自身に問うていたり、迷いながらだったり、逆にカレシに怒っていたり。
詳しく確めなくても、それらの変化から、うっすらと彼氏との関係や状況が透けるときもある。
親しい相手だからこそ、怒ったりも怒られたりもするもの。
彼氏がいると言ってるだけなのか、付き合って長いのか、ごっこ遊びしてるだけか、形だけなのか、一方的な想いだけなのか、手をつなぐ程度なのか、生計まで一緒なのか、結婚まで考えているのか、よほどの絶対者なのか、などの関係や状況が透けるときもある。
もちろん、すべてがわかりはしないが、ここの変化が第一の橋頭堡。
散々と突撃を繰り返したあげくの、ついに確保できた橋頭堡。
生と性の関係を探る
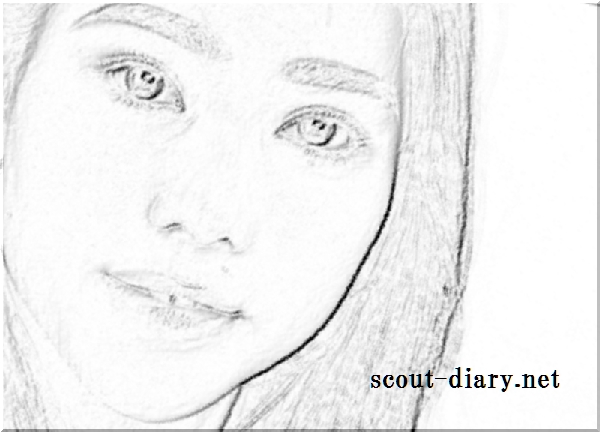
会話の橋頭堡を確保したら、ここから先を探りたい。
さらに進める機会を覗いたい。
「その、アレッとしたときに、カレシに怒られるってどうなるのって、関係とか状況を確めることもできる」
「はい」
「で、女の目と声なんかで、アレッと感じたはいいけど、ちょっとわかりずらいなってときもある。ぼんやりしてるっていうのか。関係とか状況がね」
「はい」
「そのときに、誰に怒られるって訊いていたなら、もう1回、突っこめる。カレシに怒られるって答えてくるのに、え、お母さんは?とか滑り込ませれる。口ごもっていたら、やっぱ、お父さんのほうかって自然にいい直せる」
「どういうことすか?」
「ここ、むずかしい。違う方向から確めてみるっていうのか、なんていうのか、角度を変えてクロスチェックをするというのか・・・」
「クロスチェック・・・」
「むずかしいか?」
「むずかしいっす」
「とりあえずは、実践で言ってみるだな。誰に怒られるのって。そこまではできるでしょ?」
「はい」
「そうだな、要は、なにをしたいのかっていうと、何気なく話しながら、その女の男性観っていうのかな、セックス観っていうのかな。その女が、どれほどの生教育を受けているのかってのを探っているんだよ」
「性教育すか?」
「うん。けどね、普通の性教育じゃあない。マンコにチンコが入って精液がでると子供ができますっていう性の知識じゃない。オレがいってるのは、生きるの生教育」
「生きるの生教育・・・」
「どうして生まれたかの生。どうやって生きたのかの生。この生教育は、ひとりひとり違う」
「でも・・・」
「でも、なに?」
「そこまで、関係あるんすか?」
自分は、生と性は関係があると信じている。
性衝動の遠因には生がある。
人の倍以上は性欲がある自分だから、ここははっきりとわかる。
AVをやりやすい女性とは?
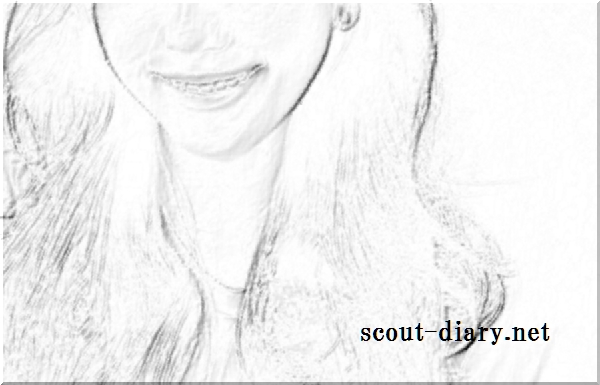
谷口は「生と性」ですね」とつぶやいて、わかるというように大きくうなずいている。
が、とりあえずは首をかしげている遠藤だ。
「その生と性は関係はある。だから生から性を探るんだよ」
「・・・」
「最初から性のことは、りっしんべんの性ね、この性のことはなかなか明かさないし、本人だってよくわかってない場合もある。でも、生のほう、生きるの生ね、こっちは明かしやすい。生から性を探れる」
「ん・・・」
「いい?女の子が普通の性教育を受けるのは、カレシと母親と父親でしょ?主に。あとは、兄とか弟もあるけど。友達もいるな。学校でも教わるけど。知識としてね。ネットとか、雑誌でも知ることもできるな」
「はい」
「でも、やっぱ、生きるほうの生教育となると、母親と父親からが大きいでしょ?」
「はい」
「で、なにがしたいかだけど、『誰に怒られる?』の変化から、3言4言のやりとりで、なんていうんだろ・・・、その3者、カレシと母親と父親のパワーバランスっていうのかな、影響の度合いっていうのかな。どれだけグラグラしているのか、それをサラッと想像できるかだな」
「・・・」
想像ってよりも、想像という広い考えではなくて、このくらいはグラグラしてるなと読む。
一点読みだ。
想像ではなく。
生教育のぐらつきだけを、一点読みする。
「これが重要で、そうだな・・・」
「・・・」
「カレシが女に性教育をしようとする。りっしんべんの性教育ね。でも、すでに母親が女に正当な生教育をしていれば、これは生きるの生教育ね、で、この生教育があれば、逆にカレシのほうが女によって感化される。母親の生教育がいちばん強大だから。こっちは生きるの生教育。ややこしいな」
「・・・」
「まあ、ややこしいけど、その母親の生に対してバランスをかけているのが、カレシと父親を合わせた性。この全体がパワーバランス。カレシの性が女に感化されているという状態は、このパワーバランスがたとえ傾いていてもしっかりとしている状態。これはAVにスカウトしずらい女」
「よくわからないすけど、・・・じゃ、AVしやすい女ってどうなんすか?」
「カレシも母親も、それほど生の塊みたいなものを持ってない場合がある、この生は生きるの生ね。こうなるとパワーバランスがグラグラしている。平らに見えていても、実はグラグラしている。これはAVやりやすい女」
「う・・・ん、よくわからないっす」
遠藤は首をかしげている。
度々、大きくうなずいているスカウト評論家の谷口が質問してきた。
「その、母親の生教育って、生きるの生のほうですけど・・・」
「ん」
「なにを教えるんですか?」
「なんだろ?一言でいえないな」
「・・・」
「正しさみたいなものかな?」
「正しさ?」
「正しさじゃないな、なんだろ?まあ、正しさか。自分がこうしたらこうだ、自分がこうだからこうなるといった、なんだろ、悪いことの対になっている正しさじゃなくて、どっちが正しくてどっちが悪いとかでもなくて、なんていうんだろ?」
「一方の正しさの対となるもう一方の正しさ、とでもいうんですか?」
「おおお、そうなの?谷口、わかるのか?」
「はい、わかります」
「おお、そっか。谷口、学者になれ」
ますます大きくうなずいている谷口に、生教育を探るのが唯一の秘策だと思われたら嫌だが、今は仕方ない。
話している自分がよくわかってないのだから。
なにを言えばこうなってスカウトできる、という秘策はない。
100人のスカウトがいれば、100通りのスカウトの方法がある。
それを自身で見つけないといけないよと、学者の谷口には後でいっておこう。
必死こいてスカウトしてみてわかったこと
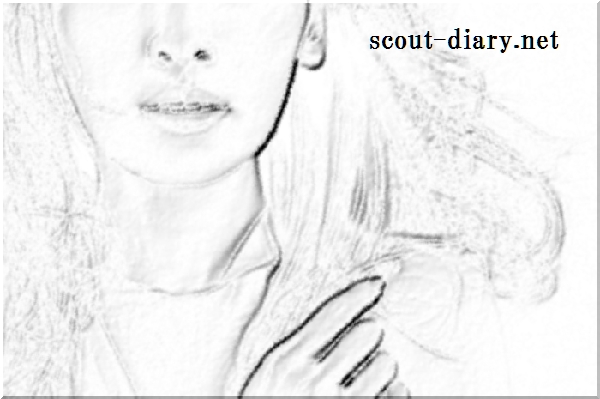
遠藤は、わずかにうなずいてはいる。
これはもう、感覚でわかるかわからないかの話なのだ。
寒さを知らない人間に寒さを説明しても伝わらない、・・・いや、貧乏を知らないだったか、孤独を知らないだったか、・・・ともかく矢沢栄吉もそんなようなことを言っていた。[編者註65-1]
「むずかしいな、うまく説明できんな。とりあえずは、実践で試してみ。誰に怒られるのって。繰り返せば違いがわかってくる。そうすればだんだんと読みが当たってくる。一点読みだけすればいい」
「うーん・・・」
「実際の話でいくか」
「はい」
「たとえば、お金に困ってなくても、AVやる女っている」
「はい」
「実家が高級住宅地にあってバイトをしたことがないっていうのに、AVはやる女もいる」
「はい」
「すごく社会的に立派な仕事していても、AVやる女っている」
「はい」
「あとは、国立大学卒業の秀才でも、AVやる女っている」
「はい」
「家庭もしっかりしていて両親もちゃんとしてるのに、AVやる女っている」
「はい」
「なんていうんだろ、不思議っていうのか、アンバランスを感じない?」
「感じるっす。頭がいいAV女優っているっすよね」
「お金に困っていたとか、お金のためにとかだったらわかるけど」
「そうすね」
「とくにAVやる必要もないのに、やる女っている」
「はい」
「これが、一見して平らに見えていても、触ってみるとパワーバランスがグラグラしている女」
「ああ、はい」
「これね、全員とも、生教育が、生きるの生教育ね」
「はい」
「その生教育を受けてなかったからスカウトできた」[編者註65-2]
「へえぇぇ」
「頭が良いとか悪いとか、常識があるとかないとか、あとは家が裕福とか貧乏とか、学歴があるとかないとか、そういうところとは別に生教育ってある」
「・・・」
「女の反応から、ちょっとでも生教育にアレッとグラつきを感じれば、そういう女こそ時間をかけてスカウトすると」
「はい」
生に疑問を持っていると、性にも疑問が出てくる。
『誰が?』その疑問に答えるのか?
生と性への疑問と『AVやろうか』の一言が、女の子の頭の中でどう掛け合わされるのかは知らない。
どのように、辻褄があう内容となっていくのかもわからない。
必死こいてスカウトしてみてわかったことは『誰が?』とあるところに、全くの他人が足を踏み入れる余地があるということだった。
– 2022.8.12 up –