無視されたらどうしようと声をかけるから冷たい目も向けられる
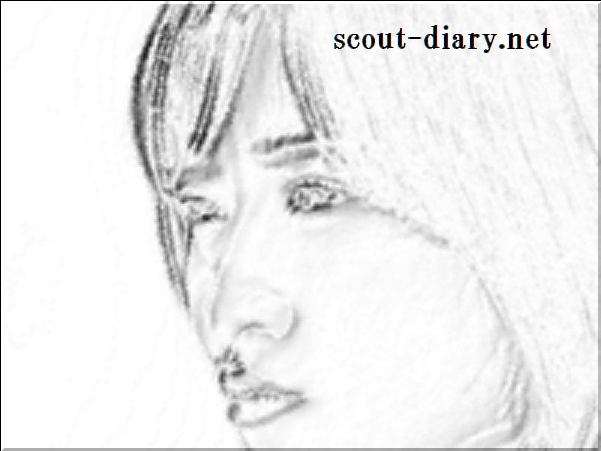
それにイケメンだと、女性のほうが照れが出てしまって、あとがスムーズにいかない。
スカウトマンという職業は、テクニックよりも慣れが必要だった。
完全に無視。
早歩きや小走り。
目の端で見られる冷たい視線。
敵意のある睨み。
蔑んだ目線。
捨て台詞で立ち去られたりもした。
これらには、早い段階で慣れた。
騒がしい人波の中には孤独感もあった。
もうダメなんじゃないか・・・、やっぱできないんじゃないか・・・という絶望感も絡まる。
3ヶ月経つころには、すべて上記には慣れていた。
ただ単に、打たれ強さだけはある自分だった。
キャバクラには10名以上は面接して、そのうち何人かが出勤。
AVプロダクションに所属した女のコにも、撮影が始まっていた。
慣れてきたのと引き換えに、飢え死にしない程度の収入は得ることができた。
しかし、店のことやAV業界の事もよくわかっておらず、佐々木やマネージャーのフォローなしでは女のコを動かしきれていない。
そもそもの話、女性というものもよくわかってない。
接すれば接するほど、ますますわからない。
わかってきたのは、女のコと話すのにはテクニックは必要がないということ。
路上で声をかけると、ほとんどが無視をする。
立ち止ったのはいいけど、警戒の目を向けたり、驚く表情をしたり、何気ないことで笑ったり。
そんなことを繰り返していれば、話を聞いたり、入店したりする女のコもいるだけのこと。
実も蓋もない言い方をすれば、ある程度の声をかけていれば、スカウトが成り立つことはわかってきていた。
案外と臆病なのは男。
度胸があるのは女だった。
無視されたらどうしよう・・・と不安がって声をかけるから、冷たい目も蔑んだ目も向けられる。
駄目なんじゃないか・・・とおっかなびっくり声をかけるから、敵意ある目も向けられるし、捨て台詞も吐かれて立ち去られる。
そんな、コツみたいなものもわかってきた。
スカウトできるタイプに共通点を感じてきていた
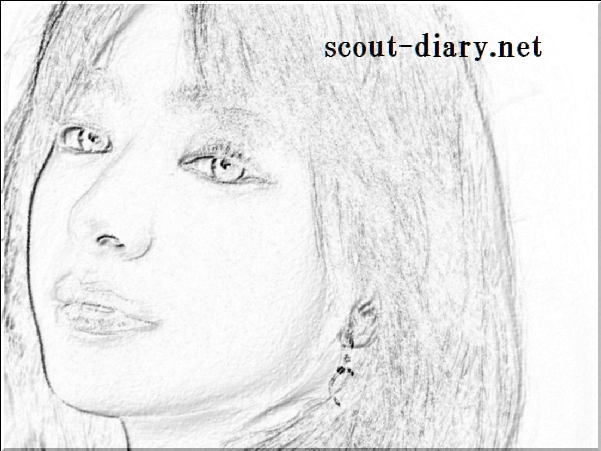
まず目。声をかけたときの瞬間の目。相手を確かめるような目を向けてくる。警戒ではなくて、商用の目。“ 客 ” という男性を持つ女性が街を歩くときの目。スコーンと外れるときもあるけど。
その日も、いつも通りに渋谷センター街でスカウトをしていると、ポケットの携帯が振動した。
ディスプレイから、以前に声かけた女のコだとわかった。
彼女の名前はしおり。
年齢は19歳。
歌舞伎町の風俗店で働いていると覚えていた。
1週間ほど前に、渋谷センター街で、いつも通りの無視の状態が続いていたときに見かけて声をかけたというのも。
しなやかそうな細い脚にスリムジーンズで、水色のミュールをガランガランと音をさせて歩いていた。
「ちょっと、いいですか?」
「・・・」
「・・・」
ミュールの音が緩んだ。
無言でこちらに目を向けた目には、警戒の色はなくて『ナニ?』と言っている。
目は口ほどに物を言う、とは誰が言いはじめたのだろう。
「アッ、突然ゴメンね」
「・・・」
「あやしい者なんですけど」
「エッ!じゃあ、いいです」
「ウソです。誠実な好青年です」
「フフ」
口元に笑みをつくった彼女が立ち止まりと同時に、自分は前に回りこんで向き合った。
こちらを真っ直ぐに見ている目は、自分が何を言うのか待ってる気がする。
「ウチの仕事手伝ってよ」
「・・・なんですか?」
「AVの事務所なんだけど」
「・・・」
彼女は学生なのだろうか。
カジュアルな服装。
控えめな栗色の髪。
顔立ちも化粧も派手ではない。
肩に大きな紙袋を下げていたから、買物帰りがわかる。
「・・・」
「・・・ううん。・・・ちょっと」
「やっぱり、抵抗ある?」
「・・・」
「考えてみてよ」
「・・・てゆうか、私、そういう仕事してるから」
「エッ、もうどこか、所属してるの?」
「ううん、・・・ヘルスだけど」
「そうなんだ」
こんな事が何回もあった。
不特定多数に声をかけているから、外見からわかるのは、おおよその年齢、後は場所や時間帯や服装から、学生なのか、社会人なのかくらいしかわからない。
実際にのところ、渋谷センター街の入口の人ごみのなかでは、ほとんどが学生や社会人で、風俗嬢の割合はほんの一部だと思う。
しかし声をかけて立ち止まり、話しはじめると「実はわたし・・・」と風俗嬢であることをいうコが不思議に目立った。
性感ヘルスだったり、マンションヘルスだったり、デートクラブだったり、ソープ嬢だったり。
これだけ人が多くて、不特定に声をかけてるし、ほとんどが立ち止まらない。
それに外見で対象の選別をしてないから、この風俗嬢の確率は奇妙に感じた。
偶然とは思えなかった。
ということは。
スカウトできるコは、風俗嬢にする事ができるのか?
そんなことも思った。
で、その彼女の電話の用件は「渋谷で風俗店を探してる」とのことだった。
彼女には折り返すといったん切って、すぐさま佐々木に電話して風俗店の紹介を頼んだ。
また彼女をやりとりをして、翌日に、佐々木が道玄坂の風俗店に連れていくことになった。
前の彼女が気になってスカウトしてるだけかも

そこに気がつくまで、むやみに鼓舞をして、圧し掛かかる自己嫌悪を跳ね除けて、背中を押して、スカウトは続いていった。
翌日。
ここ何日かは、青い空が広がる快晴が続いている。
歩いているだけで気持ちがいい。
モヤイ像の前で待ち合わせることができた彼女を、程なくして合流した佐々木に紹介した。
佐々木は彼女を連れて道玄坂に向かう。
自分はスカウトをしようと、渋谷センター街に向かった。
そのときだった。
・・・ あれッ!
あの横顔!
エリだ!
思わず走り寄って、人波を掻き分けた。
彼女の背後から肩を「ちょっと!」と手前に引いた。
突然のことに、驚いたように振り向いた彼女は、まったくの別人だった。
「知り合いに似てたものだから・・・」と、驚かしたことを丁寧に詫びたが、怪訝そうな目を向けながら、彼女は逃げるように歩き去っていった。
今までもスカウトしているときに、別人の横顔でハッとする事があった。
道端に座り込んでからは、うな垂れて「情けない・・・」との思いでいっぱいだった。
エリのことを、「バカ女!」なんて思っていても、心の何処かで、偶然を装ってでも、またエリに会いたいんだ・・・とはっきりとわかったからだった。
会ったところでどうするのだろう?
ひょっとしたら、エリとの生活をまた望んでいるのかもしれない。
・・・ 女ひとりも吹っ切れないのか!
いい年して情けない!
なにやってんだろうな、オレ!
クソクソクソクソ!
どんなに鼓舞をしてみても、自己嫌悪が圧し掛かかる。
スカウトもできずに立ち尽くして、しばらくセンター街の人通りを眺めて、明治通り沿いのイタトマに行く。
恋愛経験もほとんどないといってよかった

当の女性もそれがわかっているから、スカウトでは逆効果の言葉となる。
どのくらい経っただろうか。
佐々木から電話がある。
しばらくすると、イタトマに姿を見せた。
「彼女、入店したよ。明日から」
「どーも、すみません」
「スカウトバックは、月締めだから、受け取ったらすぐ割るよ」
「全部とってください。手間かけたんで」
「いーよ」
「たまたま、電話あっただけだから」
「田中さん、風俗店の店長を紹介するから、直接やってもらってもいいよ」
「・・・うん」
「・・・田中さんって、明るいときと暗いときの差があるね」
「そう」
「前々から思っていたけど、暗いときは顔がちがう」
「そう」
なんだか会話が進まず、佐々木も変に感じたのだろう。
だから佐々木に話した。
結婚を前提に、4年近く同棲していた彼女に逃げられたこと。
ショックだったのは、その彼女が内緒でAVに出演していたこと。
未だにどこかで、わだかまってる自分が情けなく思うこと、・・・など。
さすが、佐々木は聞き上手だった。
「そういうことがあったんだ」
「ん・・・」
「だから、スカウトをね。・・・だけど、そういうのってあるかもね」
「・・・」
「田中さんって、AVや風俗に罪悪感があるの?」
「そういうのはない。・・・道徳的にとかっていうのも全く無い。ただ、どこかで引っかかるけど」
「ウーン、単に、良いか、悪いかってこと?」
「そういうんじゃない。職業自体をどうこういうつもりもないし。・・・ただ、オレが引っかかるというのは、そんな理屈じゃなくて、・・・なんていうのかな」
「田中さん、考え過ぎだって」
「いや、難しいことは考えてない。・・・誰だって彼女がAVで乱交していたり、・・・彼女が風俗で働いたりしたら、気持ちがいやでしょ。ただ、それだけ。引っかかるというのは」
「うーん、それはね。・・・だけど、本人らは納得して働いているんだよ。無理やりだったらともかく」
「・・・」
佐々木は、飲食店や風俗店での職歴が長いので、気にならないのだろう。
いや彼に限らず、案外、現場での本人らは全然気にしてないのかもしれない。
自分自身で、独り善がりで考えているだけかもしれない。
ふと、そんなふうにも思えた。
「たしかに、本人らは納得して働いてるよ」
「うん」
「それでいて、人間は素直でいいコが多いでしょ。なんというんだろ」
「うん」
「だから、なおさら引っかかる」
「なるほどね」
いったい自分はなにが引っかかるのか?
なにが言いたいのか?
「なんていったらいいんだろう」
「あ、わかった」
「なに?」
「彼女つくったほうがいいよ。いま、いないでしょ?」
「・・・そうか」
自分がうな垂れるとしばらく沈黙になった。
新しく彼女をつくろうとはしていた。
今度、久しぶりに会う約束をしてる女のコもいた。
名前は大野真由美。
素直でいいコ感ある女のコ。
大野真由美は、自分がブローカーをしてる頃に知り合った。
久しく会ってなかったが、この前、電話をして会う約束になっていた。
学生の一団なのだろうか。
ひときわ騒がしい明るい声で「カレシが・・・」と女のコが話してる。
恋愛話だというのがわかる。
「オレはさ・・・」とロン毛で茶髪の男のコが応じる。
恋愛話が延々と続くのではないか・・・と思えるような勢い。
若い彼らの会話が耳に入り、佐々木には真由美との出来事を話したくなった。
しかし、話すと長くなるな・・・としばらく黙っていた。
なんだか、気が滅入ってくるだけだった。
イタトマを出て佐々木と別れた。
果たして、自分は軽快な恋愛などできるのだろうか?
– 2001.2.12 up –