人任せな断り
翌日の日曜日。
陽も落ちかけてる頃。
快晴だったのだが、自宅でFMのj-waveを聴きながら半寝していると、枕もとに置いてあった携帯が鳴った。
ディスプレイを見ると、みさきだった。
どうせ止めますっていうことだろう・・・という気がした。
やはり歯切れが悪い言いかたで、彼女は話す。
「それで、友達と相談したんですけど・・・」
「うん」
「やめたほうがいいっていわれて」
「そう。友達はそういうだろうね。マネージャーには連絡した?」
「ウン。だけどつながらなかった」
「そうか。今日は日曜日だからね。・・・みさきは、いま、何してるの?」
「勉強してました」
「少しだけ時間取れないかな?メシでも食べてさ。それで、止めるのはかまわないから、それならそれで、あしたオレがマネージャーに話さないといけないし」
「・・・ウン」
「いま、オレ、自宅だからクルマで近くまでいくよ。どこだったけ?」
「●●」
「1時間くらいでつくからな。そうだな、●●駅でいい? 着いたら電話する」
「・・・ウン」
この「やめます」という電話がマネージャーに入っていたら、プロダクションを辞めることに関しては自分は口出しなかった。
それと、昨日から意識のどこかに引っかかっていた女子行員という関心から、会おうと思った。
もちろん、会ってメシを食べるだけではない。
考えなおさせるつもりだ。
「友達がいったから・・・」という人任せな言葉を聞いたことで、彼女は動くという手応えは感じた。
自分の感じた事をぶつけてみて、ダメならそれでしょうがない。
彼女に言葉をぶつけたときの反応のバランスというか、うまく言えないが、こう言えばこうなるだろう、というのが掴めた気がした。
しかし、昨日と同じではダメだろう。
ベットから起きた。
シャネルのエゴイストを胸につける。
髪にジェルをつけ櫛を通す。
カラーシャツを着て、カフスをつけ、黒い大盤の腕時計をはめ、ネクタイをつける。
黒スーツをきて、チタンフレームの眼鏡をかけ、少し前に磨いた靴を履き、クルマのキーをもってウチをでた。
日曜日だけあり、道路はすいていた。
郊外の●●駅には1時間はかからなかった。
彼女に電話すると、しばらくして彼女は昨日と同じようなシンプルな服装できた。
彼女は自分のイメージが昨日と違うからだろう、一瞬「あれっ」とした顔をしたことがわかった。
挨拶は笑顔だった。
が、女子行員の営業スマイルだった。
助手席に乗せてからは「少し走るよ」とすぐに発進した。
お金は良いのか悪いのか?
新宿のランプから、首都高速にあがる。
流れは混んではいないし、電光掲示板には渋滞は表示されてない。
j-wave のボリュームを上げ、スピードを加速した。
環状線を左に折れ東京タワーを左にみて、レインボーブリッジ方向へ曲がる。
巨大なレインボーブリッジを走り抜けるときには、東京の灯が夜景となって広がっていた。
彼女は無言のまま、ずーと夜景を見てた。
そのまま、一気に台場ランプをくだった。
人気のない夜のお台場をはしり抜け、グラン・パシフィックホテルの地下駐車にすべりこんだ。
閑散としたフロントを通り、エレベーターで最上階のスカイラウンジで降りた。
ドアの向うは薄暗い。
ラウンジは8割ほど席は埋まっていたが、ウェイターは窓際の席へしっかりと案内した。
窓には、先ほど通り抜けたレインボーブリッジが、今度は夜景の一部になり収まっている。
レインボーブリッジの向うには、東京タワーと赤色灯の着いたビル群が広がる。
他の客の適度なざわつきに、夜景がとても静かに映ってる。
オーダーがおわる。
「夜景、キレイだね」
「ウン。こういうところ初めて・・・」
「会社の上司は、連れて行ってくれないの?」
「ウン」
「乾杯しよう」
「ウン」
「おつかれ・・・、でいいか?」
「ウン」
彼女は自身で納得すれば、しっかりと動くタイプだと感じていた。
理詰めで説得したほうがいい。
理屈を生理的に嫌う女にはこの手は逆効果になる。
が、勤勉な女子行員の彼女には要素がある筈だ。
まず、視点を変えさせなければならない。
その為に、どのようなことであれ、一つ一つ事実を認めさせなければならない。
彼女の本心を引き出せればと思っていた。
それが出来なかったら、彼女はあきらめよう。
「みさきは今の仕事があるから、辞めるならオレはしょうがないと思ってるよ」
「ハイ」
「本人の自由だからね。だけど、この仕事は一人でやる訳じゃないから、皆で決めたことは、皆で守っていかないと」
「すみません・・・」
「いいんだよ、べつに。責めてる訳じゃないからね。・・・それで、みさきはお金を稼ぐってことを、どう思ってる?」
「ウーン。考えたことない」
「お金稼ぐってことは、別に悪いことじゃないんだよ。・・・お金には良い悪いなんてないからね。だけど、キレイごとでは稼げない場合はあるけどね。でしょ?」
「友達は、仲がいいんだ」
「ウン」
「別に友達を悪くいうつもりはないけど、あのね、みさきが稼ごうが稼がまいが、やっぱり人ごとなんだよね」
「ウン」
「友達がポンッてお金出してくれるわけじゃないし。それに実際に直接話をしてないから、だから簡単にやめたほうがいいっていえると思う」
「・・・ウン」
薄暗い照明の中、彼女は自分をまっすぐに見ている。
頷きながら聞いている。
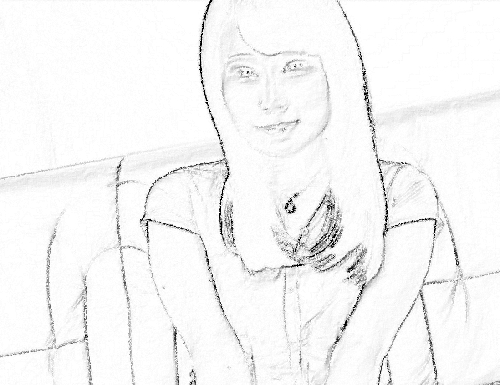
ピアノの弾き語りが始まった。
「なにか食べよう」と、オードブルをオーダーする。
ドレスアップした女性シンガーが、何処かできいたことのある洋曲を、見事に歌いきった。
余韻が残る歌声だった。
拍手が鳴り止むのに時間が必要なくらいに。
「お金はね、良い悪いでいえばどっちだと思う?」
「・・・わからない」
「いいものだよ。お金は。同じお酒一杯飲むのも、その辺の居酒屋で飲むのと、こうして飲むのとは違うでしょう。金額じゃなくてね、気分がちがう」
「ウン」
「お金を得てみないと、わからないこともある。・・・オレはハッキリいうと、みさきにがんばって欲しいって思ってる」
「ウン」
「もちろんオレの仕事として、売上つくりたいっていうのもあるよ。だけど、みさきは100万、200万を稼いでみたら、また今とは違ってくると思う」
「そうですか・・・」
「でも今の仕事があるからね。だから目標を決めてウチの予定をしよう。それであがる、・・・あがるって辞めるって意味だけど、そうするか?」
「ウン」
「・・・会社は何関係?」
「ウン・・・。金融機関です」
「いろいろあるけど」
「銀行です」
「そうなんだ」
昨日の面接のときから銀行員というのは知っていたが、彼女の口から聞きたかった。
勤続2年目になるという彼女に、自分がお金の話を聞かせるというのも、おかしなことに思えた。
目標額は200万
その銀行の支店は郊外のとある駅近辺で、部所は預金課。
彼女は銀行の寮に住んでおり、基本的には外泊は禁止されている。
外泊する場合は、寮長に外泊先と連絡先を記入した届出を事前に提出しなければいけない規則。
1回だけ嘘の届けを出して、マンガ喫茶で外泊したことがあるとうれしそうに言う。
もう、自分からはそんなに話さなくてもいいかも。
「聞いてください。寮の門限が夜8時なんです。今どき」
「えっ、今日、間に合うかな」
「あっ、今日は大丈夫です。過ぎますって言ってきてますので」
「ああよかった。遅れたらどうなるの?」
「夜8時なんて守れないですよ。みんな8時は過ぎてますけどね」
「そうなんだ」
「だけど連絡だけはしないと寮長に親に電話されちゃうんです。で、親に怒られるんです」
「厳しいね」
「親が安心するってだけですよ。門限は」
その銀行は、父親に「ここに行け」と言われた就職先。
コネ入行というものか。
本当は4年生の大学に進学をしたかったけど、父親のいいなりで短大から入行したとのこと。
父親も金融機関勤務。
で、半年ほど前に、先輩の女子行員に紹介された男が彼氏。
中小企業の製造業とはいえ、3代目の社長となる8歳年上。
その彼氏とは、日曜日の昼間に会って食事をする程度。
あとは勉強に追われて、出歩くこともあまりないという。
出身は静岡県で、女子高を卒業したとのこと。
それから銀行と寮の生活だから、彼女が世間知らずにも感じるのだろう。
昨日は、たまたま渋谷にいったとのこと。
銀行は辞めれないけど、1人暮しをしてみたいし、服も買いたいと控えめに彼女は言う。
願望に優劣は関係なのだろう。
「じゃあ、目標額決めよう。どのくらい?」
「うーん」
「ざっくりと」
「・・・50万円?」
「50万じゃ1人暮しできない。家具だって必要だし。・・・そうだな、150万は必要だけど、せっかくだから200万にしよう」
「エッ。200万ですか」
「うん。2ヶ月くらいかな」
「ウン」
彼女は「200万貯金するまでがんばる」と控えめに笑んだ。
気持ちは固まっているのだけど、実際問題、AVで動くかどうか?
エロ本を見ただけでびっくりしてるのに、AVの現場は大丈夫なのか?
寮が厳しすぎるし。
いろいろ引っかかる。
どうしようかと思いながらも、遅くならないうちにとラウンジを後にする。
主導権はある。
けどなんかはっきりしない。
台場ランプから首都高に乗った。
レインボーブリッジからの夜景を見ながら「 わたしって何も知らないんだなぁっておもった・・・ 」と彼女がつぶやいた。
つぶやきを聞いて、ウチに連れ込むことに決めた。
皮をかぶった小さなクリトリス
首都高を抜けて、新宿ランプを降りた。
銀行の寮に送る前にウチでちょっと渡したい物がある・・・といって駐車場にクルマを止めた。
玄関の明かりをつけ、靴を脱ぎ「こっち入って」と彼女の手を引く。
奥の部屋のドアを開けた。
暗い部屋の中央にダブルベットが据えてあるのが、背後の明かりでぼんやり照らされた。
彼女は何が起きるかわかり、突然で驚いたのだろう、ハッとしたように立ち止まった。
そんな彼女に「すわって・・・」と優しく声をかけてベットに座らせて、部屋のドアはバタンと乱暴に閉まった。
暗くなった部屋で、自分は無言のまま上着を脱ぎラックに掛けた。
外した腕時計をコトッと置いた。
ネクタイを解いて、シャツを脱いだ。
彼女は座ったまま視線を落として固まって、1点を見つめてる。
ゆっくりとベルトを外してズボンも脱いで、雑に靴下を放った。
自分の鼻息の荒さを、彼女は耳にしてはいる。
しかし、パンツだけになった気配を見せても、視線を落として1点を見つめたまま。
『渡したい物ってなに?』と、騒ぐのを予想していたのに。
そしたら『これだよ!』と、明るくチンコを見せるつもりだったのに。
おとなしくしている彼女が、鼻息を荒くさせた。
彼女の脇に座っても視線を落として1点を見つめたままで、頭を抱くと「あっ」と息をつめた。
キスをされながら押し倒されて、仰向けになった彼女は、身を縮めて目を閉じた。
思っていた通り、彼女は経験が少ない様子だ。
なすがままの彼女のすべてを乱暴に剥ぎ取るように脱がすと、想像通りの肉つきの体型。
大きな胸とお尻と太ももには、上質というような張りがある。
手になじんで抱きやすい、天然の肌艶と肉質。
乳首を口に含むと、突然、イヤイヤと首を振る。
かまわず股間に手を伸ばすと、薄い陰毛の感触。
指先には、内襞がそれほど出てない割れ目。
彼女は「んんっ」と声を押し殺している。
大きく足を広げると、再度のイヤイヤを始めて、股間を手で隠そうとする。
「手、どけろ!」と大きめに叱声を出すと、全身の力が抜けたようにおとなしくなった。
ぷっくりした割れ目を広げて、皮をかぶった小さなクリトリスを剥き出した。
その小さなクリトリスを舌先でほじくった。
とたんに「イヤッ」とお尻を浮かして逃げ腰になり、体を仰け反らせる。
舌打ちをして「いいから!」と叱声を浴びせ、乱暴にまんぐり返しにして抑え込んで脚を開いた。
剥き出したクリトリスを丹念に舌先でほじくると、きつく目を閉じて肩をすくめている。
すべてがしょんべん臭い。
シックスナインの体勢にはとまどって、後ろに伸ばした手でお尻の穴を隠そうとしている。
生で挿入しても、手をベットに置いて目を閉じたまま。
「中に出す」と言い放った。
が、目を閉じたまま軽くうなずくだけ。
マグロもいいところ。
抱いた身体を突き抜くように、全身の力を込めて腰を打ちつける。
子宮の感触を先っぽで確かめながら、さらに突き抜くように勢いよく腰を打ちつけた。
押し殺すような声を漏らす彼女。
そしてお腹の上に射精をした。
放尿してアナルして
性欲に忠実な男を目の当たりにして、驚いた様子の彼女。
無言のままの彼女を浴室に連れていくと「トイレにいきたい」とだけつぶやいた。
ここで放尿するように強く言うと、彼女は黙ったまましゃがみこむ。
シャーと飛沫の音がすると同時に、彼女はベソをかき始めた。
その様子が、なにかを刺激させてまた勃起させた。
半泣きで放尿する彼女の前に仁王立ちになり、両手で頭を掴んで、勃起物を目の前に突き出した。
勃起物を咥えさせると、慣れない唇の動きで、歯もあたって痛い。
「舌使って。・・・歯を当てないように。・・・そう」と独りごとのように言い、頭を掴んだまま、腰をゆっくりとグラインドしてると、放尿の音が途切れた。
生温かい足元の尿からは、微かにアンモニアに匂いが上気した。
そのまま続きをさせる。
「こっちの手をこう」
「・・・」
「指をこうして」
「・・・」
「ここを舐めて。・・・もっと舌使って」
「・・・」
「ここも舐めて。もっと舌を出して」
「・・・」
指示に従い、膝をついてフェラチオする彼女は、礼儀正しい預金課の女子行員・・・、そのものだった。
彼女のフェラチオでは、射精まではいかない。
勃起が収まらない。
簡単にシャワーを浴びてから体を拭き、ベットまで手を引く。
「寝て、・・・うつぶせに。・・・そう」
「・・・」
「お尻をあげて、もっと突き出すように、もっとひらいて」
「・・・」
ぎこちない四つん這いをする彼女に、思いきりお尻を突き出させた。
ベットの脇のスタンドをつけて、お尻の肉を両手の親指で広げると、毛の1本も生えてないアナルが。
舌を突っ込むように舐めると、キュッとすぼまった。
「ここ、なめられたことある?」
「・・・」
「手をこっちに貸して。・・・こうやって自分で広げて。チカラぬいて」
「ンン・・・」
「今、どこ舐められてる?」
「ンン・・・」
四つん這いのまま、両手を使いお尻の肉を左右に広げさせられた彼女は、何度も首を横に振る。
すでに彼女の常識の範囲を超えているのだろう。
わざと音を出してアナルを舐めると、彼女はベットに顔をつけるような感じで、かすかに声を出した。
「どんな感じがする? ・・・もっとチカラぬいて。ローションつけるよ。ちょっと冷たいよ」
「ンン・・・」
「すこし指いれるから。・・・チカラぬいてもっとお尻突き出して」
「ンン・・・」
少しも痛がることはない。
ローションもたっぷりと使い、人差し指の第一間接まで入れて抜く。
今度は第二間接まで入れてゆっくり動かす。
そうも時間はかからずに、指は根本まで埋まった。
「イタくない? ・・・どんな感じがする?すこし動かすよ。・・・イタかったらいって」
「・・・」
「ちょと奥まで入れるよ。・・・チカラぬいて。イタくない?」
「・・・」
「もう少し、ローション塗るか。・・・入れるよ。・・・ホラ、根元まで入ってるのわかる? チカラぬいて」
「ンン・・・」
呼吸からすると、本気で素直にアナルの力を抜こうとしている。
教育とは強制でもある、と誰かがいっていた。
教育されるのが真っ当な行為である彼女は、知らないことを教わるということを無条件で受け入れている。
処女アナルは指を2本飲み込むようになって、動かすとくちゃくちゃとローションまみれの音を出している。
2本指が入れば、勃起も挿入できる。
張りのある丸いお尻を鷲つかみにして、生の勃起に力を込めてアナルに押し入れた。
「あれ?アナルしたことあるの?」
「ン・・・」
「あるの?」
「ない・・・」
「はじめてなのに、すっごい・・・」
「・・・」
「すっごい、ズボズボと入ってる!ほら!こんなに!すごいよ、みさき!」
「ンン・・・」
こんなにもすんなりと、アナル処女を奪ったのははじめてだった。
これほど簡単に、ズブズブと根本まで挿入できた経験は今までになかった。
早めに動かしても痛がることなく、むしろさっきの生挿入とは違う甘い声を出した。
「あぁ、すっごい・・・。ね、お尻、もっと突き出して」
「ンン・・・」
「あぁ、きもちいいね」
「ンン・・・」
「きもちよくないの?」
「わかんない・・・」
素直に突き出されたお尻を強く掴んで、思い切りアナルを突き抜いた。
射精感はすぐにやってきた。
根元まで挿入したまま、宙を見て「ア~ッ」とうめきドクドクッと射精した。
抵抗なしに風俗嬢にはならない
しばらくピクピクしてたチンポを引き抜いたあとは、処女喪失したアナルはぽっかりと開いていた。
アナルに表情があるとすれば、ぽかんと口をあけて放心しているみたい
やがてアナルが閉じられてからは、軽く疲労感があったから、お互いしばらく横になっていた。
「みさき」
「ン・・・」
「フェラして」
「ン・・・」
「そこにウェットティッシュがあるからふいて」
「・・・」
サイドボードに置いてある、ウェットティッシュを手に取る彼女。
さっきまで自身のアナルに入っていて、微かに茶色の付着がある肉棒を、嫌がるそぶりも見せずに、丁寧に指を添えて拭き始めた。
それを見てると、おそらく職場でもこのような忠実な仕事ぶりなのだろう、と思った。
「みさき・・・」
「ハイ」
「どのくらい、セックスしたことある?」
「・・・」
「今のカレシが初めてか?」
「ウン・・・」
彼女は3ヶ月前に処女を失い、今までに2回しかセックスをしたことがないという。
クリトリスを舐められたのも初めて。
シックスナインも今日が初めて。
フェラもアナルも今日が初めて。
8歳年上の彼氏とは、最近では1ヵ月に2回ほど会って食事をするだけとのことだった。
「さっきはびっくりした?」
「ウン・・・。突然だったから」
「ごめんな」
「・・・」
「フェラして」
「・・・」
素直にすぐにフェラに応じた彼女だった。
ぎこちないフェラだが、扱いには優しさがある。
「そこを舌でチロチロってしてみて。・・・そう、うまいよ」
「・・・」
「くちびるで挟むように舐めて。そう、そういう感じで。・・・続けて」
「・・・」
「みさき。・・・返事して」
「・・・ハイ」
「みさきは、男の人にサービスする仕事がいいかもしれない。・・・風俗してみるか?」
「・・・」
「続けて。そう、うまいよ。・・・こうすれば、男ってすごく喜ぶんだよ」
「・・・」
「土日だけ、月に3日か4日ぐらいでさ。・・・50万は稼げる。来週、面接いくか?」
「・・・」
「どうした?」
「・・・でも」
彼女のいうことはわかっていた。
初心者の女のコをスカウトしてAVや風俗に入れ込むときに、彼女だけでなく、ほとんど例外なく皆いうことだ。
いくら世の中が乱れてるといっても、最初から何も抵抗なしに風俗嬢になるコはいないのではないか。
いたとしたら、白痴に近い。
「カレシに悪いか?」
「ウン・・・」
こういう場合、そんな言葉はでてくるだけで意味がない。
フェラを止めさせ、体勢を入れ替えた。
「みんな、そうだよ・・・」といいながら、彼女の足を開いて2回目の挿入をした。
肉棒をゆっくり出し入れ、ときどき思いきり腰を打ちつけながら話を続けた。
「カレシと別れてとか、銀行を辞めてという事はいわない」
「・・・ン」
「あのね、店の中だけで、客にサービスするだけだから。・・・こうして、セックスするんじゃなくて、フェラだけだったらできるでしょ」
「・・・ン」
「カレシのこと好きなんでしょ?」
「・・・ウン」
「だったら大丈夫だよ。・・・客と付き合うって訳じゃないから。・・・こうして、オレとできたからさ、みさきだったらできるよ」
「ア・・・」
「・・・」
「ア・・・、ア・・・」
要するに “ お前は悪くない ”と言って欲しいだけ。
そう思う。
何でもいいから、いい訳をつくってあげればいい。
「店の中だけ」とか「セックスをする訳じゃない」とかの。
それでも、やはり女のコは抵抗感や罪悪感がとれない場合が多いが、あとは稼ぎとのバランスだろう。
感覚的にそんなことが、最近わかってきた。
そして女は強い・・・というのを実感していく。
セックスを終えてからは、門限に間に合うように、銀行の寮の近くの交差点まで送った。
泣いたカラスがすぐ笑うというような感じの笑顔も戻ってきて「貯金できるまでがんばる」と小さくて可愛い気合も入れている。
その風俗店の面接は、来週の木曜日。
渋谷にある。
銀行が終ったあとに、店まで一緒にいくことにした。
初出勤は、土曜日の早番から。
銀行の寮には外泊届けを出しておいて、金曜日の夜からウチに泊まるのもすんなりと決まった。
しかし来週の木曜日の面接まで「やっぱり・・・」と気が変わらないか?
大丈夫だとはいいきれない。
連絡とれなかったら銀行にいく、ぐらいのネジを巻いといたほうがいいかもしれない。
しかし、そんな悪意の心配も無用だった。
– 2001.7.10 up –