調書合わせ
留置7日目。
房の外廊下のくもりガラスの窓の向こうには、今日も快晴の日差しがある。
留置されてからは、30度超えの夏日が続いているようだ。
蛍光灯が常時点灯のエアコン完備の空間がつまらなく感じる。
供述調書は、昨日の続きから。
人的な繋がりについて。
村井が店長として処罰されるのは癪ではある。
その代わりにオーナーには捜査が及ばないことがはっきりとわかり、気が楽になったのは確かだった。
バインダーのメモ、供述調書の束、ボールペンがバックから取り出された。
すぐにペンをとった係長は、供述調書を書きはじめた。
「じゃ、聞いてくれるか?」
「はい」
「本日、平成16年8月12日、本職が新宿警察署において内心の意思に反して供述する必要がない旨を告げて取調べをしたところ、次のように任意で供述した」
「はい」
「私は、黙秘権があることを、刑事さんから説明を受けて十分に理解しました」
「はい」
「じゃ、話した内容を書くからな」
「ええ」
大きめの字は、筆圧が強く、黙々と書かれていく。
自分はそれを見て座っているだけ。
ミンミン蝉がいよいよ盛んに鳴いているのが、背後の窓から耳に入ってくる。
供述調書の内容は、おおよそ以下である。
<今日は、営業をはじめたいきさつについて話したいと思います。今年の1月の半ば頃だったと記憶してますが、
・岡田洋二
という者から携帯に電話がきました。
岡田とは、以前からの知り合いです。3年ほど前からと記憶してます。
知り合った〔加除修正 追加 5文字〕当時、私は、いわゆるスカウトマンをしていたので、岡田から女性の紹介を頼まれたのです。親しくはありません。
どうしてかというと、もともと私は、必要以上に人と親しくしないからです。
電話があったときは、私は久しぶりだったので近況を伝えました。
すると岡田は、
・「歌舞伎町で風俗店をやってみないか?」
というのです。
岡田は、「店舗は、居抜きで貸す」とも言いました。
「男子従業員も紹介する」とも言いました。少し準備すれば営業もできるのでした。
岡田が私に風俗店の経営を勧めたのは、不思議には思いませんでした。
私が風俗に詳しいからだと思ったのです。
私は、岡田から店舗を借りることにしたのです。
このとき、岡田との間に賃貸契約書を交わしました。
賃貸契約書は摘発のときに押収されております。>
1枚を書き上げて、つぶやいて読み直してもいる。
人の繋がりについては、電話の発信と着信、会話の内容、それぞれの日時と場所、これらが重要視されるようだ。
いずれにしても、岡田とのことには全てが裏づけがない。
供述調書の整合性
供述調書は3枚目になった。
「なんかヘンだな」と大きくバツ印をつけて、用紙を二つ折りにして、新たに書き直してもいる。
筆圧が強いせいか、20分もすると「あぁ・・・、肩凝った」と顔をしかめて首を回している。
こんなときは昨日までは無言のままだったのが、どちらともなく雑談を交わすようにもなっていた。
「係長」
「ん」
「その調書って」
「ん」
「事前に書いておいて、んで、調べのときに読みあげて、署名に指印っていうようにはいかないんですか?」
「これはな、本人の目の前で書かないといけないんだよ」
「へぇぇ」
「だって、そうだろ。警察が勝手に調書作って、冤罪だなんてニュースでもいっているだろ?」
「ですよね。やっぱ冤罪ってあるんですか?」
「あるな」
「え、あるんですか?」
「昔はな。供述が重視されたし」
「今はどうですか?」
「今は、捜査方法が科学的だし、証拠重視だし」
「ほおお」
「でも、冤罪がないとはいえない」
雑談がひと段落すると、また黙々とがしがしと書いていく。
手が止まると、分厚いファイルを開いて目を通している。
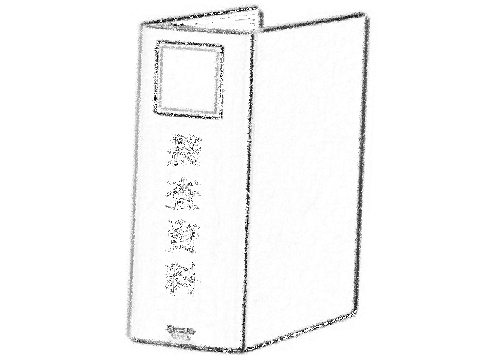
このファイルを開いて確認するのが多くなってきた。[編者註44-1]
“ 調書合わせ ” という言葉を、このときか後になってかの雑談で聞いた。
事件の調べが進み、供述や事情聴取などで複数人の調書が増えてくると、調書合わせに注意しなければいけない。
あっちの調書ではこう言ってる、こっちの調書ではこう言ってるとなると、全体の調書の信用が落ちる。
全体の調書の整合性を保ち、信用度を損なわないように確認を重ねるのだった。
警察官のサラリーマン化
調書合わせができてないのか、まとまりがつかないのか、書き途中の供述調書にはまた大きくバツ印がつけられて、シュレッダー行きのため二つ折りにされた。
顔をしかめて「あぁ・・・」と首を回して、ボールペンで肩を押している。
「係長」
「ん」
「ノートパソコンって使わないんですか?」
「あぁ、パソコンな。検事さんはパソコンだろ?」
「ええ、そっちのほうが訂正が簡単ですよね?」
「そうかあ?俺は手書きのほうがいいな。パソコンで調書なんてことになったら刑事やめるよ」
「ええぇ!」
「今はもう、なんでもパソコンだからな。ログインとかな。俺はログインなんてよくわからん」
「ログインなんて、ただ打てばいいだけじゃないですか」
「でもな、あれってな、紙に書いて貼っておくといけないっていうんだよ」
「そりゃそうですよ、パスワードの意味がないですよ」
そのパスワードが書いてある紙の貼り付けを、すでにやらかしたのだろう。
パソコンへの敵意の矛先は、現代の利器に向かっていって、携帯電話も邪魔だといいはじめた。
「ポケベルがいちばんいいな。あれ、放っておけばいいんだから」
「ポケベルですか?」
「ああ、やっぱなぁぁ・・・、ポケベルの時代がいちばんよかったな」
「もう何年前の話ですか。軽く10年以上はたってますよ」
「まだ、手錠が銀色のころだ。ピカピカ光るからな、ブレスレットだなんてふざけるヤツもいたなぁ」[編者註44-2]
なにか嫌なことがあって、鬱憤がたまっているのだろうか。
係長は懐古が止まらなくて、警察官になりたてのころに遡る。
最初は交番の前で立番して、怪しい者がいないか通行人を1日中見ていたと話す。
「昔はよかったですか?」
「そりゃよかったよ。正義の味方、スーパーマンだな。悪いことしたやつ、追いかけるだろ。コラッ、まてって」
「ええ」
「そしたら道を歩いている人が、おまわりさん頑張れって言ってくれたもんだよ」
「へえ、けっこう捕まえたんですか?」
「おお、バイクなんかは行儀が悪いと、コラッて追いかけていってな、とまれって警棒で頭ごんごん叩いて止めたなぁ」
「よく問題にならなかったですよね」
「今だったらなるな」
「ニュースに出ますね」
「今はなにやっても、こっちが悪いことしてるみたいだからなぁ。やんなっちゃうな」
「・・・」
「いい時代だった・・・」
今すぐにでも刑事を辞めそうな口調で、空を見つめている。
警察そのものに鬱憤がたまっているのだろうか。
「だいたい、最近はもう、警察官がサラリーマン化してきてる」
「サラリーマン化ですか?」
「そうだ。昔じゃ、考えられん」
「どんなところですか?」
「定時だから帰りますとかな、平気でいう若い者もいる。唖然だよ、唖然」
「係長、そういう時代なんですよ」
「そうだろうな」
「時代です、時代」
後日にも聞いたところをまとめると、後輩だった若い者が試験で階級が上がっていき、今では上司になっているという。
その上司となった後輩の、そのまた上司と係長は同期で気心が通じているという。
試験による階級の職制によって、ねじれ現象が起きているのだ。
その辺りが鬱憤の元の気がした。
取調室の内線が・・・
係長の上司となった後輩の身になれば、やりづらいのは察するに余りある。
パソコンも使えず、パスワードをその辺に貼り付けて、この時代にポケベルがいいなんて言いだして、直属の上司と仲がいい先輩が部下にいるのだから。
「あぁあ、そうだな、時代だな・・・」
「そうです」
「俺もな、もうちょっと勉強していたらな・・・」
「・・・」
「試験も通って星も増えたんだろうなぁ・・・」
「・・・」
しんみりとした空気になって、そんなときには自分はなんといっていいのか迷って、お互いに黙りこくっていると「さて、書くか・・・」と係長はボールペンを手にした。
係長を憎みきれないうちに、雑談のペースに巻き込まれてしまったようだ。
これも手口のひとつかもしれない。
捜査終了になってよかったと、自分は考えた。
そのとき。
壁掛けの内線が鳴った。
今までは一度として鳴ることがなかった内線が、いきなり鳴ったのだ。
緊急の連絡だ。
係長も気になってるらしい。
「なんだ?」と立ち上がる。
内線の受話器を取り上げた。
「どうした?え?おう、そうか。うん、わかった、で、どうなってる?・・・ん、・・・そうか、あそこか。・・・おう、そうか、んん、そうか、・・・ん、それはなんだ?・・・ん、・・・そうか、わかった。・・・そうかぁ、・・・うぅん」
即座に返事をしてからは、真剣な口調で応じている。
大きく息をついている。
心なしか深刻な横顔をして、首をかしげて少し考える素振りを見せた。
何があったんだ。
まさか、ここにきて状況が変わったのか。
だとすれば、悪いほうに向かっている気配がする。
捜査終了じゃないのか。
おいおい、やめてくれよ・・・と青ざめる思いだ。
「う~ん・・・。そうかぁ・・・、で、松は?おう、そうか、西京焼きかぁ・・・。だったら、唐揚げのほうがいいなあ。おう、やっぱそうだろ?うん、じゃ、俺も竹にしとくわ。おう、竹な。メシ大盛りにしてといてくれ。それで頼む」
なんてことはない。
昼飯の弁当は、松竹梅のどれにするかの連絡だったとは。
それをどれにするのか、ひとつひとつ内容物を確かめて真剣に悩んでいたとは。
この人は、どれだけメシを楽しみにしてるのだろう。
この前、どのように調書を書こうかと、メシも食べれないときもあるって言っていたのに。
自分の驚きに気づくことなく、係長はうれしそうにニコニコして席について、背もたれにのけぞっている。
「やっぱ新宿署のいいところは、メシのレパートリーが多いところだな」
「そうですか」
「コンビニ弁当が続く署もあるからな、あれ、あきるな。だいいち、コメがうまくないだろ」
「ええ」
「これで、もうちょっとヒマな署だったらなぁ、いいんだけどなぁ」
「・・・」
「あれ?さっき、俺、なんの話していた?」
「調書の続きを書こうとしてました」
「ああ、そうか!」
「・・・」
「じゃ、書くぞ!」
「・・・」
思いきり背もたれにのけぞっていた係長は、ぴょんとバネ仕掛けみたく前のめりになった。
唐揚げときいて、急に元気が出てきた様子だ。
ついさっき、勉強だの試験だの星だのつぶやいてしんみりしていたのに。
この係長には、手口などないのかもしれない。
そこそこのバカで、もしかしたらバカだからこそ警察官の鏡みたいな人かも。
なんにしても緊急の内線でなくてよかった。
一同で弁当を選んでいるところからすると、捜査は本当に終了したのだろう。
供述も証言も2人以上となると裁判では事実と認定されやすい
留置場へ戻ってから官弁の昼食が終わる。
しばらくすると調べ。
3番の取調室に入る。
いつものようにいつも笑顔の井沢君が、手錠を外して腰縄を結わえ直した。
スチールデスクを挟んで、係長が対面に座った。
「どうでした?唐揚げ弁当は?」
「ああ、・・・まあまあだな」
「よかったですね」
「まあな。・・・そういや、明日からオリンピックだな」
房内で官弁を食べているとき、係長は今頃は唐揚げ弁当か・・・と若干ではあるが腹も立ったので、つい嫌味に言ってしまった。
係長は嫌味に感ずいたらしい。
唐揚げからオリンピックに話を反らして、バインダーのメモと供述調書の束とボールペンをバックから取り出した。
ペンをとり供述調書を書きはじめた。
途中でファイルを見る。
自分と村井の調書合わせをしているのだ。
「でな」
「はい」
「村井君を、岡田君から紹介されたのは、何月くらいからだ?」
「んん・・・」
「1月くらいか?」
「はい、1月くらいからです」
「半ばくらいか?」
「はい、半ばだったと思います」
村井は1月の半ばと言っているぞ、と係長は暗に伝えてきている。
本当はヒロシからオーナーへの仲介があったのだが、供述調書では岡田からとなった。
供述も証言も2人以上となると裁判では事実と認定されやすい、と座談会でも話にあがっていた。
自分と村井の供述は事実となるのだ。
<村井君は、岡田君から紹介されました。
1月の半ばくらいに紹介されたと思います。店舗に行くと村井君がいたのです。
岡田君は、他に2名をアルバイトとして紹介してくれました。
しかし、1人は、3月の終わり辞めてしまったのです。
もう1人は、4月の末に辞めてしまいました。
ですので、私自身が店に出たのです。
常に人が足りませんでした。
どうしてものときは、友人にも手伝ってもらい、店の営業したのです。>
窃盗の常習で住所不定の岡田。
裏ビデオの名義人もやっていた岡田。
店落ちを持って歌舞伎町からトンだ岡田。
辻褄合わせは全て岡田に押し付けよう、盗んだ金の分のことくらいはしてもらおう、と岡田が物件を用意して、人を手配したことになっている。
<村井君は、最初はアルバイトでした。
しかし、私が頼んだので店長を引き受けてくれたのです。
4月になってから店長となったのを記憶しております。
村井君は、風俗店で働いていたことがあるので、任せても大丈夫だと思ったのです。>
裏が取れないことばかりだが、そもそもこういったものは裏のとりようがないので仕方ない。
日付については、係長がファイルを確認して「4月になってからか?」などとサインを出してきているのを「はい」と答えるのみ。
<私は、暴力団との付き合いはありません。
付き合うつもりもありませんでした。どうしてかというと、私は、暴力団が嫌いだからです。
個人的にも知り合いはいませんでした。
暴力団から、みかじめ料などの請求があったりもしませんでした。
もしものときは、警察に助けを求めるつもりでした。>
今日の供述調書は7枚。
村井もそうしているらしく、どこにもオーナーの名前がでることはなかった。
供述調書の最後の1行に署名と押印。
これで目的が完了した。
自動指紋識別システムの謎
係長は供述調書の最後にカーボン紙を挟んで署名をした。
時間があるようだ。
背後の窓の向こうからは、まだ日差しがある。
指紋がどうのこうのという話がはじまった。
「でも、あれだけ指紋をとられたら、もう悪いことできないですね」
「しなければいい」
「もう悪いことしたら、瞬間でわかるんですよね?」
「いや、そんなことはない」
「またぁ」
「隠したってしょうがない」
「だって、そういうシステムがあって、1秒間に何千何万とピッって指紋を自動で照合できるんですよね?」
「はははっ、そんなのは映画やドラマの中だけの話だ。ドラマと実際は全然ちがうぞ」
人の手で照合するという。
事件の現場で指紋を採取したとしても、誰のものなのか最初に見当がついてないと、人の手でひとつひとつ照合するので特定しきれないという。
そんなことはないのではないか?
現場から指紋さえ検出できれば、自動システムにより1秒で何千何万とはいわないが何千何百くらいは照合できて、データ登録された指紋から特定された人物がパソコンの画面にピッと自動で表示されて、捜査が進むのではないか?
警察の犯罪捜査だけではなくて、今や国が全国民の指紋をデータ登録して管理しようと目論んでいるのではないか?
だから、皆が皆、指紋をとられてデータ登録されたものなら個人の情報が筒抜けになると抵抗をしてるのではないか?
確か新聞の記事でも、何千何万何百万の指紋を照合できる自動システムを警察が運用していると読んだ気がする。
係長に訊いてみたのだが、それは記憶違いだと真顔で言う。
「指紋は記録として保管はしてある。でもな。そんなボタンひとつのシステムなんてないぞ」
「じゃ、これからそうなるって話だったんですかね?」
「でもな、この先10年20年くらいじゃ、そんなシステムなんてできないじゃないかな」
「たしかあるってきいたような・・・」
じゃあ、今はどのようにして指紋の照合をしてるのかというと、まずは勘である程度は人物を特定してから張り込みして、・・・いきなり刑事の勘で見当をつけてからの張り込みなのだ。
とにかく、アナログな方法で犯人らしき人物に見当をつける。
そして現場で採取した指紋と、用紙に押し付けられて保管されている指紋を、専門の指紋鑑識官が目視で確かめて照合しているという。
「え、パソコンがあって、照合するんじゃないんですか?」
「パソコンなんてつかわんぞ。みんな人の手だ」
「やっぱ係長。そのシステムって、市民には隠してるんですか?」
「あのな、そんなのは陰謀論だ」
指紋鑑識官は実績があるので、この人が照合したのだったら間違いないだろうという信用のもとで、指紋から人物の紐付けができるのだという。
指紋さえあれば、クリックひとつで瞬間でパソコンのウィンドウにぱっと照合の結果で出るのではないかと、自分の理解が間違えているのかと確かめたのだが、まずはアナログで人物の見当をつけるのが先で、そこからもアナログで指紋を鑑定して証拠とするのだという。
裁判でも、専門の鑑識官の証明書があるから指紋が証拠として採用されるのであって、データからシステムがはじき出したものを証拠とする裁判はないという。
言われてみればそんな気もする。
お互いの話がすごく大きく噛み合ってなかったのかもしれない。
が、調べの時間が終わってしまって、本当のところはどうなのかは結局わからないままになっている。
– 2020.12.21 up –