宣材撮り
夏の日の土曜日。
午前中にもかかわらず、猛暑を感じさせる強い日差し。
渋谷にあるAV事務所にスカウトバックを受け取りにいく。
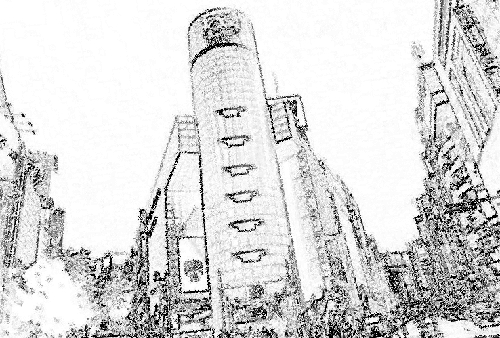
渋谷駅から歩いて10分のマンション事務所につくと、社長は宣材撮りのセッティング中。
宣材撮りとは、AVメーカーへの営業に使うヌード写真のこと。
どれほどのAV嬢となるのか、大きく左右される重要な写真だ。
社長の手が空くまで、マネージャーと雑談をしていた。
「田中さん、今日、宣材撮りやるんですけど、誰かいますか?」
「今日は予定がないです」
「そうですか。もし、いたらお願いしますよ」
「えぇ。電話します」
「だけど田中さんって、見た目うさんくさいですけど、以外に真面目ですね」
「そうかな?」
セッティングを終えた社長がデスクにつきながら「スカウトマンって、おかしい人がほとんどだからね」と雑談に入ってきた。
マネージャーが何度も頷きながら相槌を打つ。
「挙動不審だったり、目が泳いでいたり・・・」
「話が飛んだり、訳わからないのもいますからね」
「なんでかな。ホントに・・・。おかしいのばっかりだよ」
「ほんとですね」
確かに「オレはスカウトを5年やってる」「もう10年やってる」という人間の話しを聞くと、自分から見てもバカっぽい。
結局、スカウトマンだといっても、ただの使い捨ての兵隊でしかない。
やはり、兵隊を動かす側にならないと面白くない。
普段からそんな事ぐらいは考えてはいる。
スカウトバックを受け取ると、今から新しい場所でスカウトをしてみないかと社長が言う。
なんでも109に面したの路上の一角で、スカウトができるようになったとのこと。
公共の場所なのに、勝手にそんなことを決めている。
「なんとかやってみます」と、場所を確認して事務所を後にした。
初夏の109交差点
今日も暑くなりそう。
渋谷109の交差点についた。
その場所でスカウトをはじめようと、とりあえず人混みを見ながら一服する。
既に学校は夏休みにはいっており、若年の歩行者が目立つ。
すでにスカウトも何人かいた。
109の大画面から洋楽が流れて、イベントやキャンペーンの告知をする。
雑誌の撮影なのだろう、カメラマンとそのスタッフが立ち話してる。
脇にはギャル系の女のコの一団が歩道に座り込み、せわしく化粧をしてる。
テレビのインタビューだろうか、マイクを持った人間と機材を抱えたスタッフもいる。
インタビューを受けたガングロの女のコが、カメラの前で大声を上げておどけたポーズをとった。
豊かな社会は幼児化する。
テレビ番組で学者が言っていた。
学者のいうことはあまりアテにはしないが、この時はその言葉を思い出した。
この夏は渋谷でスカウトをしていたが、「ヤマンバが多いでしょう?」とよく聞かれた。
が、全然そんなことはない。
ヤマンバの女のコは、109の近辺に3、4人しかいなかった。
毎日、その女のコ達が来ては大声をあげてカメラに写る。
テレビや雑誌が繰り返し取材をする。
それを見て、渋谷にはヤマンバが多いと勘違いする。
マスコミに作られてるな、と実感する。
スカウトをはじめる。
人混みの中でのスカウトは、相手と歩調が会えば声をかける。
選り好みをしてる間ができない。
「ちょっとい・・・」
「・・・」
素通りしたデニムのミニスカートの女の子。
早歩きの後ろ姿を見送る。
ま、こんなもんか。
左に体の向きを変えると、肘にバックをかけた、お姉さん系が来るのが視界に入ってきた。
サラサラの長い髪に、パッツンに整えた前髪。
もう近い距離。
目を向けてると、あちらも目向けた。
目が合うと同時に、手を平を軽く挙げた。
「どーも」
「・・・」
手を挙げると同時に、目を伏せて、ヒールの音を立てて小走りに。
ものすごい敏感な反応。
ほおぉ。
前に向きなおすと、青になった横断歩道から人波。
素足にミュールの、元気に歩く脚が目に入る。
上半身までは見てないが、歩調を合わせて声をかけた。
「ちょっといいかな?」
「・・・」
まとめ髪にして、パッチリした目元だった。
黒地のワンピースには、白い花びらが浮かんでいる。
残念なことに、パッチリ目はこちらに向かないまま素通り。
歩調を合わせようにも、他の通行人が邪魔になってる。
そのまま人波にまぎれていく。
だめだぁ。
体の向きを変える。
薄いピンクのチビTにショートパンツの女のコが、足をブラブラさせながら来る。
目を向けると、すぐにこちらに気がついた様子。
ゆっくり歩を進めると、敏感にビクッとさせて目を反らした。
が、表情も歩調も変わらず。
彼女の視線の前に手の平を差し出して、軽く上下に振った。
「ちょっといいかな?」
「急いでるので!」
「いやいや、ヒマでしょ!」
「忙しいでーす」
「じゃ、あとでいいよ。待ってるから!」
「ダメでーす」
彼女は笑顔を向けながら、ヒラリと小走りになって距離が空いた。
後ろ姿を見送ると、また別のスカウトに声をかけられてる。
今度は完全無視して通り過ぎていた。
あのコはタイミングだな。
右側に向きを変える。
濃紺の白い水玉の、ひらひらしたワンピースの女のコが人の向こうに。
まだ大分先を歩いているが、こちらに向かっている。
つば広の帽子に、上がった口角に細い首元に浮き出た鎖骨。
雰囲気は今日イチ。
深めに被ったつば広の帽子で、目は合わせない。
こちらが声をかけようとしている気配は感じている様子。
まるで、時代劇の虚無僧みたいな女のコだ。
歩を進めると、やはり足早になる。
だめか。
「ちょっといい・・・」
「・・・」
そのまま声が届かないところまで、足早で素通り。
後ろ姿を見送る。
そんなことを30分ほど繰り返す。
直射日光がたまらなく暑い。
どこか、涼みにいくか。
いや、手応えあるまで続けようと・・・と、とりあえずビルの日陰で一服をする。
目の前には、小さな女のコを連れた母娘が信号待ちをしている。
品の良さそうな母親に手を引かれてる女のコは、お出かけの洋服でお人形さんみたい。
その女のコが不思議そうに他のスカウトを見て、母親に質問してるのが聞こえた。
「ネ~、なんであの人、声かけてるの?」
「あれはね・・・。いいのよ別に」
「ネ~、なんで?なんていってるの?」
「・・・お嬢さん、モデルになりませんかって声をかけているの」
「それでモデルになるの?」
「ううん。それで、おっかないことになるのよ」
「なんでなるの?」
「いいのよ。いろいろあるから」
「なんで?ネ~、なんで?」
「いいの!」
「ネ~、なんで?なんで?」
「おっかないことになるの!」
「どうして?ネ~、なんで?」
「いいのっていってるでしょ!」
「エ~、なんで?なんで?」
嗚呼・・・。
自分はこんなことをしていていいのだろうか?
今更ながら、何故、スカウトなんてしてるのだろうか?
食い扶ちのためとはいえ、ほんの一瞬だけ悲しくなった。
返事はいらない
人通りが多くなってきた。
もう何も考えないでおこう。
サクッといくか。
ブラブラと路上へ出てスカウトをはじめる。
「ちょっとい・・・」
「・・・」
「・・・」
黒い髪に黒い薄手のカーディガンの、細身の女のコにも声をかけた。
胸が膨らみが大きくて、タイトなワンピースを着てる女のコにも声をかけた。
背中まであるポニーテールで、お尻をプリプリさせて歩く女のコにも声をかけた。
その他、何人かにも。
「ちょ・・・」
「・・・」
皆、早歩きの素通りか少しの小走り。
女のコは多くて、ペースも早くて、目線と歩調のリズムがとれない。
向きを変える。
「ちょっといいで・・・」
「・・・」
レースのブラウスにスリムジーンズの女のコは、目は向けが人ごみにまぎれた。
胸までブラウスのボタンを外していた女のコは、足が止まりかけたが逃した。
集中、集中と心の中で言いながら向きを変える。
「ちょっといいですか?」
「・・・はい」
「・・・バイトしない?」
「まだ、高校生なんで・・・」
「やっぱり」
こっちも声をかけた瞬間、高校生だとわかった。
面倒だったので、すぐにバイバイする。
反対側に向いたときに、半ば適当に声をかけたときだった。
「ちょっといいですか?」
「・・・エッ、・・・ハイ」
早歩きの彼女は、すんなりと足が止まった。
足が止まるとは思わなかった。
逆に自分があせってしまった。
化粧っ気がない顔立ちが、幼いくらいに若く感じる。
陽に当たったことがないような白い肌。
艶がある黒髪が肩にもたれかかり、白い肌に黒目と黒い眉毛が清潔感がある。
「あっ、突然ごめんね」
「・・・はい」
一瞬だけ高校生かと注意した。
が、返事の様子では、そうではない気がした。
「今ね、ちょっと頼まれて、声かけているんだけど」
「・・・ハイ。なんですか?」
その清潔感には似合っている、シンプルでカジュアルな服装。
動物に例えればウサギという感じ。
「AVの事務所だけど」
「・・・」
AVなんていえば、ビックリして逃げていきそうな気がした。
が、言うしかないではないか。
「プロダクションね」
「・・・」
「ウチの仕事手伝ってくれないかな?」
「あっ、ムリです」
「なんで?」
「いま、仕事しているので」
「あっ、別にいまの仕事を辞めて、すぐにという訳じゃないんだけど」
「・・・」
AVのプロダクションという意味がわかってないのか・・・、と気がついた。
だから、最初から引く様子もなかったんだ。
「休みの日でかまわないから」
「・・・」
「月に1回でもね」
「・・・どういう仕事なんですか?」
幼いような若さがあるのだけど、仕事してるということは高校生ではないだろう。
「AVだから、脱ぎがメインだけど・・・」
「エッ、AVですか!、ダメです!ダメです!」
「あっ、あのね、AVは出来ないでしょ?」
「・・・はい」
「AVのプロダクションっていっても、AVだけじゃなくて、雑誌とか撮影会とか。最近では衛星放送とかインターネットとか、・・・ギャラは安くなるけど、テレビで胸とか背中だけとかね。・・・ヌード専門のプロダクションだから、できる範囲でかまわないよ」
「・・・」
この感じ。
AVの話を聞くのは初めてなのだろなという感触。
「ギャラと内容で、仕事を受ける受けないは自分で決めるし、ダメだったら断るのは自由だし。雑誌でギャラ6万からだね。撮影会は3万かな」
「・・・」
「パンチラ写真とかだったら、ヘーキでしょ?ギャラはちょっと安くなるけど」
「・・・」
渋谷にも、それほどきたことがないのだろう。
その位だったらいいか・・・とでも思っている気もする。
「名前はなんて言うの?」
「エッ、・・・藤井です」
「ああ、ちがう、下の名前は?」
「・・・みさきです」
「みさきって、呼ばせてもらうよ」
「はい・・・」
「で、ここ暑いからさ、こっちで話そ」
「あ、はい」
歩道脇の日陰に移り話を続けた。
21歳の会社員という。
何の会社かは、あえて聞かなかった。
通常の社会生活に、実直な性格というのがよくわかる。
ヌードモデルを全く考えてないという訳ではなさそう。
「今日は用事があって渋谷に来たの?」
「CDを買おうと思って・・・」
「じゃ、時間あるね」
「う・・・ん」
はっきりしないが、このあとの時間はある。
それだったら、今から連れて行こうか?
「それでさ、こうして話してるだけで、もう10分くらい経つでしょ」
「・・・ハイ」
「会社まで歩いて10分かからないから、行ってさ、マネージャーの話だけでも聞いて」
「今からですか?」
「で、お茶の一杯でも飲んで、よかったら所属だけでもしてみたら?」
「・・・」
「所属するといっても、別に費用がかかる訳じゃないし。登録用紙に記入するだけだから」
「ハァ・・・」
大丈夫だ。
着いてくる。
返事はいらない。
勝手に「いこう」といって、2歩3歩と足を進めた。
やはり彼女は着いて来た。
とりあえず撮影会
歩きながらマネージャーに電話すると、手は空いてるとのこと。
彼女には宣材写真は裸でということだけは、事前に言っておかなければならない。
いけるか?
「それで最初にマネージャー紹介して、ちょっと話も聞いてね。で、所属できるのなら、登録用紙に記入して写真とるから」
「はい」
「写真は宣材写真っていうけど、バストアップで撮るからね」
「バストアップ?」
「うん、上を脱いで撮るの」
「エッ、全部ですか?」
「そうだよ」
「エッ」
彼女の足は止まった。
上半身だけとはいえども、いきなり脱ぐのは抵抗あるのだろう。
ヘタすれば、もう動かなくなってしまう。
やはり、少し急ぎすぎたか。
「今日ね、ちょうどカメラマンきていて、撮れるっていうからさ」
「でも。・・・脱ぐんですよね」
「どうしてもっていう訳じゃない。そのカメラマンが機材持ってきていて、今日以外はなかなか予定がとれないからっていうだけだから」
「・・・」
「宣材写真を見てみればわかるけど、プロのカメラマンだから、やっぱり素人じゃ撮れないんだよね」
「でも・・・」
「じゃ、写真は今日じゃなくてもいいよ。別に急いでる訳じゃないから」
「・・・」
「さっき電話しちゃったから、今から止めますっていうと、オレ困るんだよ。・・・行くだけいこう」
「・・・ハイ」
彼女のハッキリしない態度に、少し強めに言ってみた。
真面目な性格なのだろう、自分が歩を進めると彼女はついて来た。
そのままの勢いで事務所にはいり、彼女をテーブルに座らせると社長がきて挨拶をした。
簡単な説明をして、少し雑談をしてから社長が切り出した。
「今日は宣材撮影は大丈夫なのかな?」
「・・・」
「ちょっと、見てくれる?」
宣材写真を何枚か見せた。
ヌード写真とはいえ、宣材写真は特にエロさは感じない。
それどころか、プロが撮るだけあってキレイに撮れている。
社長がうまいことやってくれそうだ。
「こっちの部屋でとるから、ちょっと、おいで」
「ハイ・・・」
隣の部屋は、小さなスタジオ風になっていた。
黒のバックシートにライトが映えて、それらをカメラマンが調整していた。
「こちらカメラマンさんね。この人と、2人だけでとるだけだから」
「・・・」
「全体的な雰囲気もみたいし、営業するのにどうしても必要なんだよね」
「ハイ・・・」
社長の気さくな雰囲気もあったのだろう。
もう1度テーブルに座り「お願いします」と登録用紙とペンを出すと、彼女は書き込みはじめた。
年確(年齢確認)のために、免許証をコピーする。
それから別室で、しばらく宣材写真を撮っていた。
登録用紙を見ると、彼女の勤務先は郊外にある都市銀行の支店。
かたい職業の代表格なのに・・・と驚いた。
少し無防備だなとも、真面目なんだなとも。
宣材撮影の後は『1度引き受けた仕事はキャンセルしません』『 フリー活動をしません』『やめる場合は3ヵ月月前に連絡します』という内容の誓約書にサインをする。
それから社長がマネージャーを呼んで、細かな内容を打ち合わせ。
まだわからないからと、ビデオ撮影はすぐにNGとなる。
雑誌撮りについて、マネージャーがいくつか成人誌を持ってきて説明をはじめた。
成人の誌とはいっても、そこはエロ本だった。
何気にパッと開いたページが、ハードなカラミのページだった。
本能剥き出しの淫らな表情の女が、大股開きで、アナルまで丸写し。
次のページにでは、胸には精液がほとばしってる。
『失神寸前!!恥部をガンガン攻め抜け!!』と雄雄しいタイトルも。
彼女の表情は上気した顔している。
色白な頬がピンクになっていた。
平静を装っていたが、明らかにカラミの写真を見て動揺している。
マネージャーが鈍感に言う。
「こんな感じのカラミはできますか?」
「エッ、・・・ちょと」
「そうですか。バイブはできます?」
「エッ、それは・・・」
「できませんか?」
「・・・はい」
「フェラは、できるでしょ?」
「エッ」
このやり取りを黙ってみていたが、口を出した。
通常マネージャーを建てるため、こういう時は口出しはしない。
しかし彼女の場合、これ以上は引いてしまう。
「マネージャー、彼女、タッチはせいぜい手ガラミしかできないですよ」
「そうですか」
「あと、土日しか休みがないので撮影会を中心にしようってことで」
「なるほど」
スカウトを知らないスタッフは、これだから困る。
街中で「私、脱ぎます」という女のコをスカウトできるものだと思っている。
彼女は、とりあえず撮影会のみにする。
これからAVデビューするかもしれない、というのが売りの撮影会だ。
カメラを持った男性が、雑誌の広告で以外に多く集まる。
色紙を持参してサインをください、と言う熱心な初物マニアもいる。
これだけの仕事量ならば、ギャラ売上はそれほどでもない。
しかし最初はこの程度でも、そのうちAVがOKとなる女のコも多い。
宣材撮りできたし、とりあえずはこれで彼女は動くだろう・・・と思った。
だけどマネージャーが彼女を動しきれるかどうか?
気にはなる。
成人誌の撮影は擬似ガラミ
2時間ほどして事務所をあとに。
道玄坂を下りながら、どちらともなく渋谷駅に向った。
「みさき」
「・・・ハイ」
「できそう?」
「ンー・・・」
「ちょっと、緊張しちゃったか?」
「ハイ」
「アイス食べてから、帰りなよ」
「・・ハイ」
公園通りのカフェに行き、アイスを注文する。
シンプルでカジュアルな服装が、チノパンのムチムチのヒップラインを強調させていた。
綿の生地が太ももの肉を包んで、横にシワになっている。
今度、マネージャーに彼女の宣材写真を見せてもらおう。
このチノパンを脱がすとどんなお尻をしてるのだろう、と思いながらカウンターに座る。
「ビックリした?あの雑誌みて?」
「うん。ビックリした」
「見たことあるでしょ?」
「・・・はじめてみた」
「全くはじめて?」
「うん、はじめて」
「カレシのうちにないの?」
「エッ、カレシは・・・、付き合い始めたばかりだから」
「ふーん。 男兄弟とかいる?」
「妹だけです」
「じゃあ、見たことないね。あのね、マネージャーはあのカットを見せたけど、他にもいろいろあるんだよ」
「・・・」
「ナンパ写真とか、素人ヌードとかね、聞いたことない?」
「・・・うん」
「写真ではスゴイなって思っても、実際に撮っている時は、キメ撮りといって動きがつく訳じゃないから」
「ウン・・・」
「感じてる顔してとか、恥ずかしそうな顔してとか。・・・ポーズを作ってるだけだよ」
「ウン・・・」
「雑誌はほとんどそうだよ。あの発射シーンだって、コンデンスミルク使ったりしてるんだから」
「そうですか?」
「そうだよ。みんな作り物だよ。どこそこのみさきさんが脱ぎました、なんてことで撮らないから」
「・・・ウン」
「メイクもすればガラって変わっちゃうし」
「・・・ウン」
「マネージャーも、編集者もカメラマンもみんなプロだから、その辺の素人じゃないからね」
「・・・ウン」
「みさきが心配することは、なにもないよ」
「・・・ウン」
「後はマネージャーから連絡くるから、しっかりと打ち合わせて、ダメなものは断っても全然かまわないからね」
「・・・ウン」
そんな話をしたら、少しは安心した様子を見せた。
早くも成人誌はOKになりそうだ。
実際、成人誌の撮影はすべて擬似ガラミ。
動きがつくわけではない。
メイクで別人みたいに変わるのも事実。
事務所のスタッフも、編集部もプライバシーと約束は守る。
それほど変な人はいない。
あえてプライベートのことは話題にしなかった。
こんな話に納得してしまう彼女をみて、社会人にしてはちょっと世間知らずだな・・・、という気がした。
しばらくして、電話番号を交換し「それじゃ」と別れた。
都銀の女子行員というのが、どこか自分の意識の中に引かかってはいた。
しかし後はマネージャーにバトンタッチするので、彼女と電話することも会うこともおそらくないだろう。
そう思っていた。
– 2001.6.25 up –