条件反射の断りは無視する

新宿駅東口。
夕方に差しかかる頃。
晴天と祝日が重なった気持ちがいい日。
声をかけるも、10人くらいは完全な無視。
さらに5人かは足早で素通り。
あと5人かは、横目の端で見てるだけで、せいぜいが「やらない!」という適当なあしらい。
10日ぶりのスカウトで、それらは足慣らしにちょうどよく思えた。
彼女には、いつものように声をかけた。
というよりも声は届かない距離から、軽く手を振ってみただけ。
「どーも」
「・・・」
すぐに視線は反らしたのだけど、彼女の緩んでいた歩調は変わらない。
3歩半ほど踏み出しただけで、合わせるようにして彼女の足が止まった。
向けてきた目元は、浜崎あゆみのようなゴテゴテ感。
くっきりとした警戒がよぎった。
「あやしい者ですけど」
「・・・キャッチですか?」
「うん」
「じゃあ、いいです」
彼女は首をプルプルと振って歩こうとする。
本当にあやしい者に見えたのか。
「あぁ、ちょっと!」
「・・・」
「まだ、なにも言ってないじゃん!」
「・・・」
かまわず前に回りこんだ。
手の平でストップのゼスチャーをすると、歩きはじめていた足はまた止まった。
「モノ売りじゃない」
「・・・」
「話だけでも聞いて」
「・・・」
「あやしいのは顔だけだから」
「フフ・・・」
どこか明るさが潜んでいた笑みだった。
ナンパ慣れしてそうなノリはある。
今までにも、スカウトされたのが何回かあったのかも。
「それでさ、エッチ系だけど」
「・・・」
「たのむよ」
「・・・どんなのですか?」
もうAVだと感ずいている様子で、警戒と好奇心が交じった目をしている。
聞いてくるのは経験者だからか。
「もう、エッチ系してるの?」
「してないです」
「フェロモンあるからさ」
「ハハ」
「いま、学校いってるんだ?」
「ハイ」
以外に明るく実直な返事で、見た目よりまじめそうな学生だった。
好奇心旺盛な未経験者というところか。
フェロモンは、ただ胸がでかいから口に出た。
「AVだけど」
「エ・・・」
「まあ、脱ぎ全般かな」
「・・・いいです」
「あっ、OKね?」
「イヤ、・・・ムリです」
「あー、そんなかしこまって、返事されたらこまっちゃうよ」
「・・・ハイ」
「ハイとかじゃくって、ウンでもいいし、もっと、気楽に聞いてよ。いますぐにってことじゃないからさ」
「・・・」
断りは全力ではない。
条件反射で断ってるだけだから無視していい。
「みんな、こっそりとやってんだよ。言わないだけでさ」
「・・・」
「いない?学校の友達で買い物とかハデなコ。いるでしょ?」
「・・・うん」
「でしょう」
考えるような返事をしながら『そうだね』と言いたげな目線と頷き。
足は完全に止まってるから、もっと押せる。
「今日は話だけだからさ。・・・それで、オレ、田中っていうんだけど、名前なんていうの?下のほう」
「・・・みか」
「みかって呼んだらずうずうしい?」
「ハハ」
「みかさんじゃあ、ヘンだし。みかちゃんはね、オレが言うと気持ち悪いでしょ」
「ハハ、みかでいいよ」
「よく新宿くるんだ?」
「たまに」
「今日は遊びに?」
「買い物」
授業でつかう教材を買いに来たとのこと。
学校は渋谷で、スタイリストの勉強をしてるという。
「あと、2、3分ぐらい、うーん、まあ5分かな。そのくらい話しても大丈夫?」
「うん」
「ちょっと、タバコ吸わせて」
「いいよ」
タバコを取り出した。
少し先のオフィスビルを指差した。
「それでさ、あそこの入口のところで話さない」
「・・・」
「ここ人通るし。ざわつくし」
「・・・うん」
「いこ」
なんとなく学生をして、なんとなく他人に左右されるタイプか。
そんな雰囲気が感じとれる。
普通といえば、どこにでもいる普通の女のコだ。
脱ぐ女性は豊かすぎる感性がある
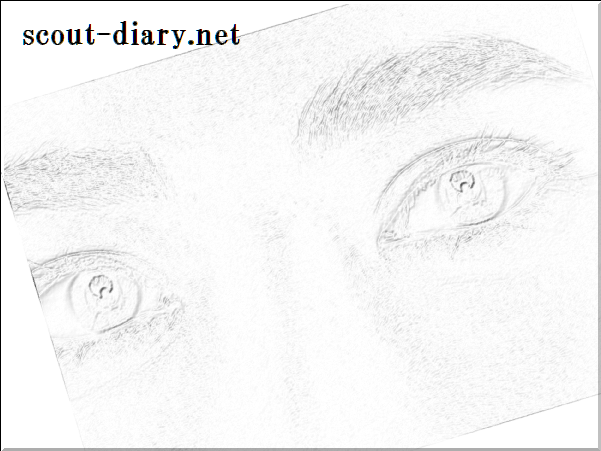
オフィスビルのエントランスは、すぐだった。
ポケットからライターを出して、ゆっくりと火をつけた。
頭は急いで一瞬考えたのだけど、口が先に動いた。
「なに、話していたっけ?」
「ハハ」
「アッ、そうそう、バーンと脱いでみよってことだったね?」
「・・・」
「オレ、バカなのかな、でも、ヘンな人じゃないから。いや、じゅうぶんヘンですよって言われれば、まあ、そうなんだけど」
「ハハ」
「でも、なんていうの、けっこう、モノわかりいいから。それで考えてみて、ダメならダメで、ぜんぜんかまわないからさ」
「・・・うん」
彼女は少しの笑顔をつくり、自分を見据えた。
悪いことがおこらないように、間の取りかたを注意している。
押せば逃げる感じがした。
「さっきさ、友達でいるっていったじゃん」
「うん」
「AVとか、いや、AVはいないか。風俗とか、キャバとかしてるコはいる?」
「キャバクラだったらいるかな」
「風俗はやらないほうがいいと思うな。やっぱりイヤでしょ?」
「・・・うん」
「キャバぐらいだったらヘーキ?」
「それくらいだったら」
自分を見据えながら、彼女は応える。
バイト感覚のキャバクラ希望か。
この場合は脱ぎの方向へは話せる。
「オレもさ、キャバも頼まれているんだけどさ、いま、すごく大勢いるのよ。やりたいってコ」
「・・・」
「それで、店長とか紹介するでしょ。歌舞伎町の●●とか、●●っていう店。知ってる?フロムエーにも募集広告でてるけど」
「ううん。知らない」
「それがさ、すぐ辞めちゃうからさ。やっぱ、けっこう大変なんだよ、バイトだと。思ったより、時給ださないし」
「・・・」
「けっこう、引かれるんだよ。何々費とかいってさ。ペナルティーだってあるし。だから、いまはクラブ調の店をね、レギュラーで入れるっていうコだけ紹介してるけど」
「クラブ調?」
「うーん。場所にもよるけど、銀座の場合だと、イメージできるような高級なところ。でも、そういうところって時給は、3時間か、そうだな、4時間ぐらいしか出ないな」
「なんで?」
「ホステスってさ、売上に対しての歩合だからさ。でさ、客とのプライベートの付き合いも必要だし」
「・・・」
「だから、バイトだとちょとムリになっちゃうね」
「・・・」
自分に都合の良いこじつけが半分。
しかし彼女は律儀にうなづく。
「やっぱホステスの器量ってさ、何年もかかって身につくものだと思うな」
「そうなんだ」
「うん。だから、まあ、キャバだったら、いろいろ調べてさ、店に電話したほうがいいと思うな」
「・・・」
「まあ、オレがこんなこと言うのはなんだけど」
「ウーン・・・」
脱ぐ女のコは、損得勘定よりも、良くも悪くも豊かすぎる感性がある。
熱っぽく動く情もある。
現実さよりも、非日常な感覚のほうが響く。
「だけどさ、オレはね、ぜひ、AVでがんばってほしいよ。なかなか脱いでもいけるってコいないからさ」
「・・・」
「みかには、健康的な若いキレイさがある」
「だって、・・・AVでしょ?」
うなずいてから煙草を最後にひと吸いした。
吸殻を円筒の灰皿に捨てた。
誰にAVがバレたらいけないのか訊いてみる

もう5分は経っているけど、彼女は時間の都合を言わない。
これから用事はないのだろうから、このまま話は続けても大丈夫だ。
「AVもやってるけど。あのね、AVのプロダクションだから、脱ぎだったらいろいろやってるよ。雑誌のパンチラ撮りとか、写真のヌードモデルとか。できることだけ受ければいいの」
「ン・・・」
「それでね、ちゃんとしたメーカーとか、出版社で撮るからさ。プロの人がね。その辺のブタみたいなオッサンがハアハアいって撮るんじゃないからさ」
「ハハ」
何気に通りを指さすと、ちょうど、さえない小太りの中年男性が通りかかった。
歩く姿が笑いを含んでいて、その間が自分でもおかしかった。
「いま、みかはAVっていって、ものすごいこと想像してるでしょ?パッケージにバーンとのるような」
「うん・・・」
「そこまでいけば、もうギャラはドカンだね。でもさ、みかだったら取れるな、そのぐらいのギャラ。いまのメイクいいし。スタイルいいし。ニコッてしたかんじもいいし。ウケはいいよ」
「・・・」
「すぐだよ、おカネ貯まるの。オレは貯金しろって言ってるんだけど、すぐベンツの1台は買えるよ」
「・・・」
「みかよりもさ、なんていうのかな、カワイクないコって言えばいいのかな、そういうコが、けっこうなギャラ取ってるからね」
「・・・」
軽く振ってみたギャラには、反応はまったくない。
数字の問いがでてこない。
どうしてもというほど、お金を必要としてない。
まだ、お金の話は早いか。
「きょう、いきなり撮りましょうってことはないから。祝日だからさ、メーカーも事務所も休みだから」
「・・・」
「あ、事務所ってプロダクションの意味ね。かんちがいしないでよ、あやしい事務所じゃないから。パーと明るい事務所ね、ちゃんと蛍光灯もついてるし」
「ハハ・・・」
いつも使っている単語が頭に浮かんで、相手の反応で区切られて隔てられて、いくつもの単語をいくつもの点線で繋いだ。
一本の実線で、ゆっくりと手繰り寄せた単文が、カスタマイズされて口からでた。
「それでさ、スタッフもいて社長もいるんだよ。アホみたいにさ。電話とかしてるの」
「・・・」
「所属するのに費用かかるわけじゃあないから。プロフィール作って、モデル名もつけてね。山田花子とか」
「ハハ・・・」
「でも学校もあるしな。月に2日か3日ぐらい予定してさ」
「・・・」
「マネージャーがいてね、まあ、そいつもアホなんだけど、連絡くるからさ、モシモシ~なんてさ。それでダメな撮りは断っていいんだから。断るのも仕事のうちだからさ」
「・・・」
久しぶりのスカウトのせいか、ちょっと話しすぎている。
彼女の目に好奇心があるのが、早口にもさせてもいる。
早口はいけない。
引かれてしまう。
「楽しくやるものだからさ、機嫌わるくするようなことはない。大事にされるよ、女のコは」
「・・・」
「ていうか、何の話してるかわかる?」
「エ・・・」
「わかんないよね。だってオレもわけわからないから」
「ハハハ」
「なに考えてんだろ。オレ」
「ハハハ」
ワンパターンにカスタマイズされた話も、なんだか今日は話していて飽きてくる。
自分で話のコシを折ってから、彼女の明るさのある笑いにぶつけてみた。
「バレたらイヤってことでしょ?」
「うん」
「彼氏に怒られるの?」
「え、・・・うん」
「彼氏がいない」というAV嬢や風俗嬢は、いないと言ってもいいぐらいだ。
10人中7人8人は彼氏持ちだ。
だから逆に追っていけば、彼氏がいる女の子をスカウトすれば、半々以上で当たりになる。
そして『彼氏』に『バレ』に、決して上級ではない感情の『怒り』を組み合わせて訊いてみるのが、いちばんに反応がわかりやすことに気がついてもいた。
とにかくも。
見開き気味になった彼女の目の奥に、影に近い筋が瞬間に差した。
明るさを放つ光源の前を、何かが走ったようにも見える。
途端に口元の笑みがミリ単位で潜んで、うなずいて答える声色には不思議さが含まれる。
疑問がある。
彼氏に。
彼氏の性に。
そう感じた。
「カレシと別れる予定は?」
「ないよ、そんなの!」
「別れちゃえば?」
「ダメ!」
「ていうか、座ろうよ」
「どこに?」
「アルタのウラにイタトマってあるんだけど、そこでケーキたべよ」
「ウーン」
「ダイエット中?」
「ちょっとね」
「ちょっとくらいいいよ、こっち」
「・・・」
かまわずに背を向けて歩くと、彼女はついてきた。
脱ぎへのアプローチはできる。
興味は持っているし、対して抵抗感も持っている。
彼女自身は気付いていないが、自分から見れば立派なAV予備軍だ。
このタイプは動かすことができれば、真面目にAV出演する。
隣席とケーキは話を交わせれることを保証させる
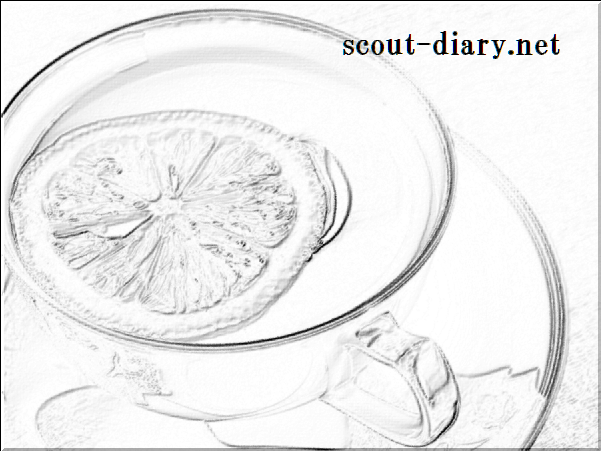
道路から見上げると、イタトマの2階席は空いていた。
アプローチを整理した。
彼女の持つ抵抗感は溶かせられる。
理性が好奇心に逆らって押し留めている。
「オレは、イチゴショート。みかは?」
「チーズケーキがいい」
「飲み物は?」
「どれにしようかな。・・・レモンティー」
「オレ、持っていくからさ。2階の窓際席とっておいてくれる?」
「うん」
オーダーして、トレイをカウンターに置く。
ここまではいいとして、気をつけなければいけないのは、溶かせられない抵抗感だ。
生理的に受け入れられない、という抵抗感。
この抵抗感を邪険に扱うと嫌悪に繋がる。
ヘタすると憎悪ある抵抗を受ける。
これだけには触れないように気をつける。
「ごゆっくりどうぞ」と、いつもの店員がニコリとしてトレイにレモンティーを置いた。
階段を上がり彼女の隣の席に座った。
「あ、おいしそう」と、ケーキを見た彼女が言う。
隣席とケーキは、互いに話を交わせられることを保証させる。
話す内容が、AVだろうが風俗だろうが、一律に保証される。
彼女はレモンを絞って一口つけた。
「それでさ、さっきの続きだけど。いい?」
「うん」
「みかさ、自分のハダカに自信ある?」
「ハハ」
「いや、マジで。どうだろ?」
「・・・」
「ただ、単純にあるか、ないかだけ」
「・・・ウン。・・・ある」
笑みが潜んだあと、ハッキリとした口調がでた。
目が挑戦的に感じた。
その小さく隠れた自信は、AV嬢の素質のひとつだ。
「みかはさ、脱ぎの仕事ってはじめてだからさ、やっぱ、明るいところで脱ぐって抵抗あると思うよ」
「まだ、やるっていってないよ」
「うん。そうだけど。・・・あのね、バレるパターンって決まっているんだよ」
「そうなの?」
「うん。それほど気にするものじゃない。そうだなあ、友達から広まったりとか、彼氏へのアリバイがヘタとかね」
「ふーん」
「プライベートを曝け出すわけじゃないからさ。たとえパッケージにバーンと写っていてもわからないものだよ」
「えぇ、わかるよ、わかる」
「メイクしてプロが撮れば別人みたいになる。いま手元になにもないからさ、そうとしかいえないけどさ。実際に見ればわかるよ。もちろんパッケージNGとか、コンビニ雑誌NGとか、ちゃんと決めてから撮るからさ」
「ふーん」
ウソではない。
ウソではないが、少しごまかしてる。
罪悪感は誰でもある

言い訳はさほど必要としてないようだ。
バレにも、これ以上は触れなくてもいいとも感じた。
「バレたからヤメますってコは、いないなあ」
「・・・」
「バレるというよりもさ、なんだか罪悪感があるんでしょ?」
「・・・うん」
もうちょっと感情的に話したほうがいいのか。
感情的に話すといっても、静かにゆっくりと。
咄嗟に罪悪感に話を振った。
AVにとって罪悪感もキーワードになる。
しかし、こんな言葉に実態も意味もない。
彼女が勝手に想像して、勝手に思い浮かべてるものごとにすぎない。
良識な理性が俗悪な印象を作ってるだけだ。
「カレシにわるいってさっき言ってたよね」
「うん。・・・やっぱりね」
「カレシと結婚するんだ」
「・・・うーん。・・・どうなんだろう?」
またレモンを絞って、手を拭いていると「・・・でも、結婚はしたいなあ」と彼女が言った。
そんな美意識には、触れないほうがいい。
でも彼女の美意識は、危うい感じがする。
危ういバランス感覚でグラグラしてる。
「ちょっと悩ませるかもしれないなあ。こういうのって」
「・・・」
「わるいっていうのはわかるけどさあ、いいじゃん、それでも」
「エ・・・」
「わるいのはオレだからさ」
「・・・」
彼女は、気のない返事のように小さくうなずいた。
小さなうなずきがあれば、あとは小さな約束。
それできれれば、スカウトの半分は完了だ。
「オレ、口ベタだからさ、その辺、うまく言えないけど」
「・・・うん」
「まあ、女って強くってさ」
「うん」
「強いんだよ、なぜか。今までのことから言ってもさ、AVの1本や2本は、まあ、3本や4本ぐらいさ、サラッとこなせる」
「・・・うん、それっていくらくらいなの?」
やっと、その質問が出てきた。
金額は相手から訊いてくるのがいい。
そのほうが、話の主導権が維持される。
「みか次第だけど、パッケージができれば、半年で500あたりはいきたいね」
「え、半年で?」
「うん」
「そうなんだ」
AVのスカウトと風俗のスカウトで違う点は、お金の話し方だ。
AVの場合は、まとめた金額で話すほうが受け入れられやすい。
半年で500万とか、1年で1000万とか。
一方の風俗では、半年後のことなど話してると、そっぽを向かれてしまう。
もっと刻んで、1日単位で話したほうがいい。
理性と感情の領域
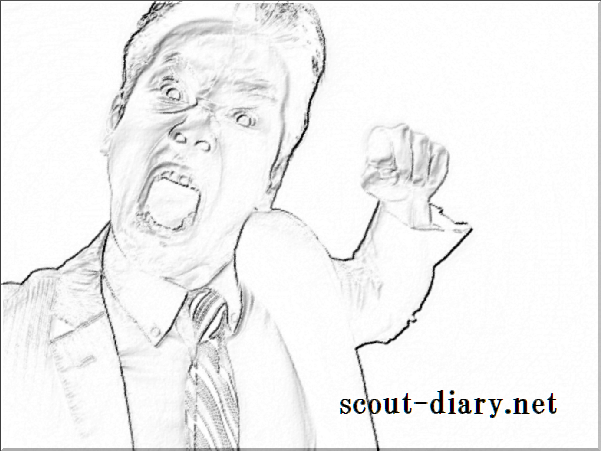
内容と金額の話をひととおり終えると、彼女が話を変えるようにして逆に訊いてきた。
若干の前のめりで。
「こういうの、どのくらいしてるの?」
「んん・・・、3年になるかな」
「ふーん。ケンカとかならないの?」
「ははは。彼氏とかと?」
「うん」
すぐに彼女が不思議に感じていることはわかった。
彼氏がいる女のコを、脱がしてAV出演させたり、風俗に入れ込んだりしてるのだ。
考えてみれば、殴られるはないにしても、彼氏連中から文句のひとつくらいはあっても当然だ。
「オレ、それほどわるいことしてないからさ。ウソついたりとか、ムリやりとかさ」
「そうなの?」
「冗談であやしいですっていってるけど、根が正直者だから」
「ホントに?」
実際、その彼氏とやらからは、文句のひとつも出てこない。
本人の自由意思です、気持ちを尊重してます、契約に基づいてます、違法ではありません、AVも風俗も立派な仕事です。
そのような社会規範を、理性で理解できてしまう男性は文句は言わないものだ。
世の中には、理性に満ちている男性がよほど多いと思われる。
「ホント、ホント。千葉県の田舎出身だから、わるいことできないんだよ」
「ハハハ」
「オレはいつでも携帯でつかまるからさ。この携帯だって、もう8年使っているんだよ」
「ふーん」
「適当なことしてないってわかるでしょ?」
「うーん」
人の女に手を出しやがって・・・などと熱くなる者などなかなかいない。
昭和じゃないんだから。
それでも絶対に守らなければいけないのは、男の感情の領域は侵さないということ。
感情といっても、好きとか嫌いなんかの情愛ではない。
そんな浅い情愛は、いつもつまんで放り投げている。
男は誰でも、女性に対しての絶対的な感情ってある。
理性などでは納得などできない、胸がザワザワッとするような、原始的な強い力のある感情というのか。
その感情の領域に入っている女のコをスカウトするとトラブルに繋がる。
とはいっても、その領域に入っている女のコの場合は、事前に「彼氏がやばい」とか「彼氏がまずい」とか、なにかしらを口にするものだった。
ヒロシなどは、そこをわざわざ侵してまでスカウトしてAVプロダクションに所属させたはいいけど、怒り狂った彼氏から「ぶっ殺す!」という電話がきた。
ほとぼりが冷めるまでと、ここ1週間ほどスカウト通りに姿を見せてない。
「だから、みかさ」
「うん」
「ゆっくり考えてみて」
「やらない」
「いいんだよ、それで。気が変わったときでいいから」
「変わらない」
「彼氏と別れることもないからね」
「別れない」
「でも、ちゃんとこうして十分に話し合って、納得してもらって、おねがいしてるのはわかってもらえた?」
「うーん、どうかな・・・」
彼女は不思議そうな目をしたままだった。
すでに様子からは、彼氏は理性ある男側とは伝わってきている。
その種のことは自分はわからないが、理性がありすぎる男ってのも、それはそれで女のコってある種の疑問を抱くらしい。
『バレ』に『彼氏』に『怒る』の組み合わせの反応でも薄々とわかところは、そんなところだった。
スカウトが面白くない
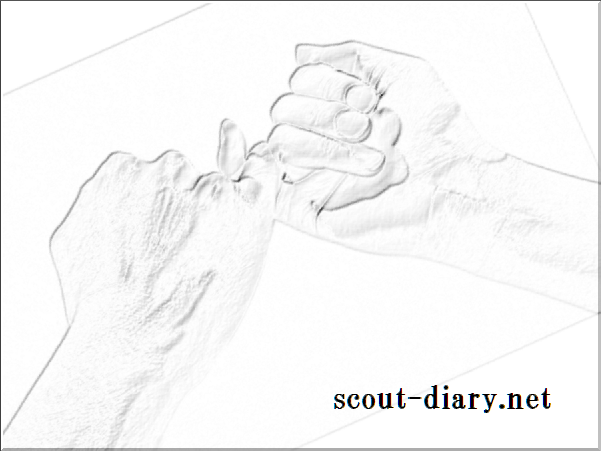
「ありがとうございました」いつもの店員がいい、「どうも」と自分が言う。
トレーを片付けて、彼女とイタトマを出た。
腕時計を見た。
あと1時間もすれば日が落ちる。
新宿駅で彼女とバイバイしたら、次の女のコが現れるまで声をかけよう。
「来週になったら電話する」
「うん」
「みかも、いつでも連絡ちょうだい。新宿でヒマなときとかでもいいし」
「うん」
「オレから電話したときさ、もし彼氏いたら敬語つかって。バイト先からってことで」
「うん」
「そしたら、すぐ切るから」
「うん」
女のコって秘密が大好き。
交わされた小さな約束が秘密めいたものなら、いたって楽しそうでもある。
「何時ぐらいだったら都合いい?」
「夜だったらいいかな」
「10時過ぎでも?」
「うん」
「もし口もききたくないってときは、もう着信拒否でもかまわないからさ。でも、それだと悲しいなあ」
「ハハハ」
中央線沿いに住んでいる彼女とは、新宿駅の東口交番前まで一緒に歩いた。
彼女は手を振りながら階段を降りていった。
「じゃあ、またね」
「うん」
「それじゃ」
「うん、じゃあね」
この段階から、面接を経て宣材までいくのは10人中1人はいる。
多くて3人はいる。
彼女は見込みはあるほうだ。
いやここは、余計な先入観を持つことなく、お祈りするのみ。
一服しながら辺りを見渡すと、人妻風というのか、タイトスカートにヒールが歩いてきた。
実際に人妻かもしれない。
向こうも目を向けてきた。
お互いに目合うが、手も足も動かないままだった。
さっきまでの勢いが落ちている。
どこか苛立っているのか、誰とも口をききたくない気分になっている。
スカウトがうまくいっても、なんだか面白くないと、最近はよく思う。
訳がわからないままやっていた、何年も前のほうが面白さはあった。
でも、仕事なんてつまんないものなんだ。
こんなときは、気分転換にメシをがっつくのがいい。
あっさりとスカウトをするのを諦めて、歌舞伎町のつるかめ食堂に向かう。
食うことが、自分の今の日常の筈。
スカウトの目的でもあり、条件でもあり、理由でもある筈。
食うことに集中したい。
噛み込んで、満腹になれば、気分も落ち着くだろう。
が、気がつけば、ボーと定食を食べている。
周囲の音は耳を通り抜けていて、1点を見ながら、なにも考えてなかった。
ただ、息をして、メシを口に運んでいるだけだった。
メシがうまく感じられない。
さっきは空腹だったのだろうか。
どうしようもない空疎な感じが、胸の中に広まっていた。
広まりに、得体のしれない占有者が乗り込んで居座っている。
占有者は正当さを主張する。
そして、インチキとキレイゴトを同じくらい貴重に取扱っている。
いや貴重ではなく、同じくらいに見下げているだけかもしれない。
見下げるというのも当てはまらない気がする。
見下げるのには気力がいる。
ただ、しらけてるだけだ。
あれだけドキドキした女のコの裸も、最近は鮮やかに目に焼きつくこともなくなった。
あれだけ好きだった放たれる色彩が、薄くしらけて見える。
– 2003.10.22 up –
