彼女との出会いのきっかけはキャラクターグッズ

あの日。
冬の羽田空港。
青森行きの飛行機に乗り込むところだった。
用件はキャラクターグッズの義理売り。
納品業者の社長が、今回の同行人として連れてきたのが、従業員の大野真由美だった。
この社長は、そのキャラクターグッズを大量に抱えて困っていた。
倉庫代わりの雑居ビルに同行すると、3フロアーにぎっしりとダンボールに積まれて置いてあって、在庫を見せる社長は困り顔をしていた。
問題は、キャラクターの版権と販売権が複雑なこと。
仕入れて1年経っても、納入先が思ったように開拓できてない状況。
そして資金繰りの問題から、バッタ(定価の1割)で、他業者に引き取られるという段階まできている商品だった。
それを●●党の代議士の手塚先生の口利きで、青森の●●村にあるサンタクロース村が、義理買いをすることに。
その納品で自分がいくことになっていた。
グッズも既にサンタ村に発送してあったので、あとは検品をして受領印だけの仕事だった。
その手塚先生と社長と自分とのつながりは、原という50代半ばの男を介してあった。
原は会社を経営していた。
しかし会社とは看板だけ。
実態はバブルの遺産のような、海千山千の不動産ブローカーだった。
そのときの自分は自営業。
スーパーやデパートでの店頭販売の下請け。
いいようにコキ使われていた、さえない自分だった。
その時に知り合った原から「会社を買わないか?」と持ちかけられた。
会社といっても、休眠会社で事業をしてる会社ではない。
無学な自分にも、収益など無いのはわかった。
ただ、それを買うことによって、“ 代表取締役 田中賢一 ”という登記ができることはわかった。
個人事業主の自分は、何度も法人の謄本が欲しいと思うときがあった。
それに原も仕事を回すという。
世に言うトンネル会社というやつだ。
休眠会社には負債があることもあるというし、売買には不安があった。
しかし結局は、現金で100万円を原に支払い、その会社を買った。
約束どうり議事録を変更した原は、自分の態度を気に入り、いろいろと目をかけてくれた。
そして会社売買の代金は政治献金となり、手塚先生のパーティー券となったことがわかった。
議員の私設秘書の仕事
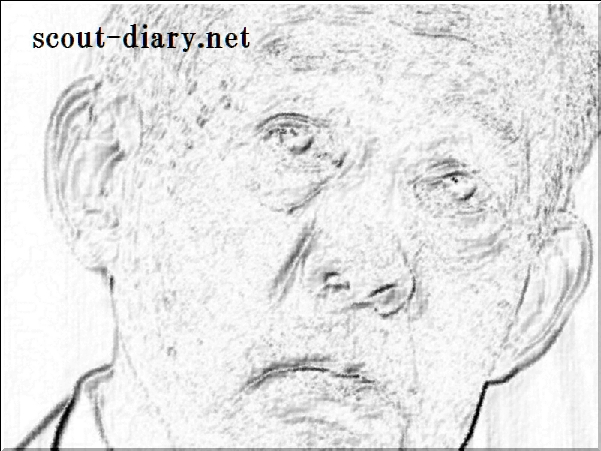
手塚先生は、70代半ばの老人だった。
●●党の傍系の派閥のさらに下に位置している。
そして、この任期で引退するから、それまでに存分に金儲けをしたい・・・という意向で秘書は動いていた。
代議士の秘書は、公費で雇う第一秘書、第二秘書がいる。
強い代議士先生になると第三の政策秘書を雇う。
が、手塚先生は第二秘書まで。
その第二秘書は、恰幅がいい40代。
そして、今回の手塚先生の元で金作りの実績をつくれば、今度はもっと派閥の上の先生から声をかけてもらえる・・・、と様々な案件の取りまとめをしていた。
原は、第二秘書の金作りに協力する見返りに、手塚先生の私設秘書の肩書きを得ていた。
行政への“ 口利き ”や“ 斡旋 ”には、私設秘書の肩書きが効く。
そのための私設秘書だった。
原の運転手として、議員会館に行ったのが最初だった。
国会議事堂に向かって、左側に議員会館がある。
議員会館の脇にある駐車場に車を入れると、警護の警官が敬礼をした。
ロビーには陳情で並ぶ人々。
その人々の脇を特別発行のパスを見せて通り抜ける。
階段を上がり、すぐ右手のエレベーターを上がる。
代議士の国会事務所は、大物、新人の差が無く平等に廊下の両側にある。
手塚先生の名前がある事務所のドアには、選挙用ポスターが立派に貼ってあった。
事務所は2室。
多少手狭さを感じるが、ここに第二秘書がいる。
第二秘書の元には私設秘書が出入りし、秘書会があり、後援会があり、つながりからできたグループは、合法、脱法、非合法にかかわらず●●党と手塚先生の名前で金集めに取り組んでいた。
どんなことをやっていただろか・・・。
政治資金パーティーの準備、覚書付きの取引契約、損切り交渉、パテント売買案件の交渉、空リースの斡旋とリベートの実行、福永法源やKKCや許永中の詐欺マネーの導入、暴力団幹部がからんだ手形詐欺や会社整理・・・。
今回の義理売りは、その中でも小さな案件だった。
卸し値で300万円程の商品を、サンタクロース村に3000万円で買わせる。
サンタ村が金を出したとしても、出費にはならない。
出入りの業者10社に、それぞれ300万で引き取らせればいいだけのことだ。
その業者も、さらに下請けや孫受けの出入り業者に買わせるかもしれない。
最終的には、キャラクターグッズなどは、子供や奥さんにプレゼントすれば喜ばれる。
可愛らしいキャラクターグッズは、義理売りに最適の商材といえた。
粗利の2700万円は、手塚先生を中心にそれぞれ分配される。
そのとき手塚先生は、コノ手の取引の金には細心の注意をしていた。
代議士の“ 口利き ”や“ 斡旋 ”というものには法に抵触する場合もあるからだ。
必ず「私設秘書が勝手にやった。私は知らない」という逃げ道を作っておく。
嬉しそうな彼女が話しかけてきて

羽田空港からの機中で。
彼女は、同行者が以外に若かったので以外だったのだろう。
うれしそうに話しかけてきた。
「わたし、いまの会社に入って、はじめての出張なんです」
「あ、そう」
「でも、よかったです。こんなにも商品が売れて」
「うん」
「かわいいから、先方も気に入ってくれたんですね」
「うん」
義理売りなど知らない彼女にとって、大口の取引でもあるし、半分は旅行感覚かもしれなかった。
自分は意識して親しさを見せなかった。
取引先の社員でもあるし、立場を分からせるためだった。
それ以上、会話が弾むということはなく、青森空港に到着した。
青森空港は山際の空港だからなのか、雪が吹雪いていた。
ゲートを出ると、サンタクロース村の支配人が迎えにきていた。
販売業者から、私設秘書、手塚先生、そして村長、支配人と、からくりがすでに出来あがっていた。
サンタ村は現村長に依り、ゼネコンの●●と●●村が、1億2000万の資本金で、第三セクター方式により設立された。
●●村の財政は7割が中央からの地方交付税に頼っており、元々、“ 県の人間 ”だった村長は中央の金を引っ張るのがうまく、予算の工作に力を入れていた。
この義理売りは、手塚先生と村長の、今後の付き合いの手始めの取引なのだろう。
今回、原の取り計らいで、自分が間にはいることになった。
自分にとっては、間に入ることで、会社の口座に入金される大事な仕事だった。
支配人は、ゼネコンからの出向で東京からきている50歳絡み。
独身者。
なるほど・・・と、うなずくことができる冴えない中年男。
サンタクロース村への車中では、歓迎の意を示す愛想のよさがあった。
支配人も何かしら村長との約束で潤うところがあるのだろう・・・と容易に想像できた。
●●村は、海沿いの漁村だった。
おそらく村の中心部なのだろうか。
国道沿いの、昔ながらの商店街に差しかかる。
既に日が落ちており、小雨が降っていたので閑散とした印象が残っている。
コンビニもなければ、人通りもない。
人口は3000人程の村とは聞いていた。
サンタ村のおかげで50名の雇用が生まれ、それがそのまま親戚、縁者を含めて800票に繋がってることを秘書と話す村長の自慢気な顔も思い出された。
田舎の村長というイメージとは程遠く、東北訛りもなく、そつのない社長という感じの村長からは、この寂れた●●村は想像できなかった。
そして、村のイメージと不釣合いな立派な建物が国道沿いにあったが、それは村役場だった。
村長は東京と●●村の2重生活で、恵比寿のマンションに愛人がいることも、そのときに思い出した。
車は村を抜けて、国道を外れて、坂道を登はじめた。
「ホント、山奥に造ったものだから、遠くてすみませんね」と支配人がいう。
登りきると、森が切り開かれ、点在する木々にイルミネーションの電球が連なっている。
そして、木造風のコテージが現れた。
ここがサンタクロース村の事務所だった。
車から降りると、ツンッとする寒さ。
サンタクロースの雰囲気は出ている。
事務所で改めて挨拶を交わしたが、細かな話は明日ということにして、食事をして、案内されたコテージで寝た。
彼女が無言でうつむいてから

翌日。
この日は祝日で、よく晴れていた。
イベントが開催されていた。
サンタクロースの格好をしたノルウェー人が歩く。
家族連れの人出もかなりあった。
商品の荷ほどきをし、検品を彼女に任せ、やがて土産物が置いてあるコテージにも陳列された。
夕方になった頃、「オー、田中クン。終わったんかー」と秘書会に出入りしてる後藤が姿を見せた。
50代前半の村長の姿も。
スーツは若向けな村長だった。
人当たりが良さそうに「皆でレストランで夕食をとりましょう」と村長はいう。
後藤、支配人、自分、彼女の5人でテーブルを囲んだ。
村長がニコニコしながら、緊張気味の彼女に話しかけた。
村の活性化について、ざっくばらんな意見を求めたようで、はっきりと意見をいう彼女だった。
「このサンタクロース村に、もっと人を呼べたらと思ってね」
「とてもキレイな所ですしね。もっと若者を呼べばいいとおもいます」
「ウン、ウン」
「清里みたいに、マグカップとか、記念品とか、そういうのを置いたらどうですか?」
「ウン。今、ヨットハーバーを造ろうとおもってね。そしたら、夏と冬でもっと人呼べるからね」
「あぁ、いいとおもいます。想い出作りができれば、若い人がみんな来ます」
いかにも若い女の子らしい意見を、後藤が顔をしかめて遮った。
ボリュームがでかい声だった。
「村長。そんなコップなんておいてもしゃーないやろ」
「んん」
「記念のペンダントなんて売れても知れとるで」
「んん」
「それに、村長、ヨットハーバーなんか儲からへんで。想い出作りなんてどうでもええがな」
「んん」
このような関西弁だったろうか。
彼女は息を飲むようにして黙って、後藤が続けてしゃべりだした。
「本州で日本海と太平洋に面しているのは、山口県と青森県でっしゃろ?」
「んん」
「山口県は、日本海と太平洋側が50分で行ける道路が何本も通ってんねんで。海岸もテトラポットだらけや。毎年、予算組めますからな」
「んん」
「やっぱ総理を2人も出してる県はちがいますやろ」
「んん。そうだな」
「道路は県に持っていかれるから、テトラポットか、せやな、砂浜なんか簡単でええな。ダンプで砂もってくれば、後は海が持っていってくれるやろ?毎年そのために予算組めますやろ。」
「そうだな」
「ああ、あとアホな若者が溺れて、2人か3人死ぬやろから、これも毎年、ごっつい対策費も計上できますな」
「そっか、そっか」
「対策費を削ることはできへんからな。阪神大震災なんて同一地区であんなにも死んでくれたから、自治体は堂々と予算組めとんのやで。国は80兆円集めとんのやから、何でも予算にしたらええんや」
「対策費か。この辺りは、死体がロシアまで流れていくから、捜索しても見つからないからな」
「エッ、ホンマですか。それやったら自殺の名所作りなはれ。看板1つでできますからな」
「ほう」
「そうや。ホトケさんが近隣に打ち上げられたら、そこにも対策費まわさなあかん。カネばら撒くようなもんや。せやけど、ここにそんなもん打ち上げられても気色わるいしな。ロシアまで流れていけば、あとは哀れなイメージだけが残る、いい自殺の名所になりますからな」
「そっか。看板だけだったら金かかなくていいな。宣伝もいらないしな」
「あの自殺の名所の東尋坊なんて、えっらいカネが落ちてんやで」
その日の新聞には、青森県の自己破産件数が、過去最大になったという大見出しがあった。
すばやく頭を働かせた村長の表情は、にこやかさが増していた。
「そしたら遺書さえ残して飛び込めば、村から金一封出すようにしてもいいかもな」
「そうしなされ。その辺でアホに首つりされるよりは、よっぽどええで」
「フフッ、順番で飛び込むかもな」
「はっ、はっ、はっ、はっ、はっ」
さえない支配人の「ぶっひゃっ、ひゃっ、ひゃっ、ひゃっ」という、なんとも下品な笑い声を上げたが、えらく機敏に見えた。
彼にとっては、お追従の笑いなのだろう。
つられるように、村長も後藤も高笑いをした。
自分も仕事の一部と咄嗟に判断したのか、少し笑うことで追従の意をみせた。
彼女だけは無言のままうつむいて、決して笑おうとはしなかった。
「あの和歌山のカレー事件だって、同一地区で1度に4人が死んでくれたんやで。首長はホクホクですわ」
「ああ、あれも予算とれるな」
「ごっついですわ。そうでもせんと予算引っ張れへんでぇ」
「ははははっ」
この種の人間にとっては、快感が伴う笑いだということを、自分は既に気がついていた。
高らかに笑うことで、快感が増すことも気がついていた。
利権が笑わせる。
辞書に利権とは、利益を得るための権利とある。
利益を得る側の人間の欲望も、人間の営みすべても、清濁合わせて飲み込んで延々と動いていく。
個人的に悲しいことがあっても、社会的な悲劇であっても、あるいはどんなに立派で崇高な行為でも、ひっくるめて飲み込んで動いていく。
自分が納得してればいいだけのことかもしれない。
しかし自分はこの種の仕事をしたとき、冷静な外面の内側の奥で憤り・・・というのか、ぶつけようのない怒りを自覚したことがあった。
行動と意識が矛盾してる。
この矛盾は自分の何処か遠い意識の奥で、軽く衝突を起こしているのも気がついていた。
そして、仕事上でバランスを保つ為に、作為的なエネルギーが必要だった。
そのなんとも言い様がないエネルギーは、大きな緊張感を生み出していた。
彼女を大事にしたいとは思ってはなかった
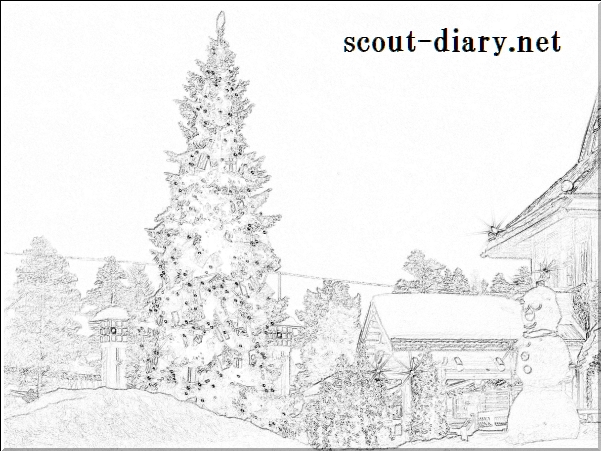
夕食が終わり。
彼女とコテージに向かう。
暗い遊歩道は、イルミネーションに囲まれていた。
所々に設置されているスピーカーから、ノルウェーの歌なのだろうか、女性とも男性ともわからない、ソプラノの歌声が流れていた。
メロディーが寒さと静寂さに併わさり、歌声がとても澄んだ声に聞こえたのを憶えている。
2人でその中を歩いていると、彼女が「キレイですね・・・」と言う。
しかし、自分は残念なことに、キレイだとは実感できなかった。
今回の仕事は、簡単な実務に過ぎなかったが、あのオヤジらに自分の存在感を明かにし、今後の流れに対して言葉と行動を少しでも強くしたいと考えていた。
それでもこのときは、たまには自分が見せる意味の無いサービス精神が働いたのか?
「そうだね・・・」と答えた後は、彼女を自分のコテージに誘った。
山奥すぎてNHKも映らないほどだった。
早々と寝るだけと、お互い分かっていたからか、彼女は応じた。
コテージは、オイルヒーターで既に暖かく、ホッとする感じがする。
ビールを出して、ソファーに座り「おつかれ!」と飲んだ。
そんな自分が以外だったのか。
彼女からいろいろと話しはじめた。
相槌を見せると、明るく自身のことや会社のことなどの話も続ける。
そして、少し会話が途絶えたとき、「あの人達、・・・なんだか、・・・黒い」と悲しそうな表情をした。
夕食の件だろう。
伏目がちに悲しそうな表情をしてる彼女は、聞いた内容にショックを受けたのがわかった。
なにも疑いもなく、自分を信頼してるかのような表情は純真ともいえて、また隙にも感じた。
そんな彼女を見て、なんだか自分も緊張感がほぐれてきている。
食欲が充たされると性欲が刺激される、とはよく言われる。
それと同様に、強い緊張感がほぐれた後も、性欲が刺激される。
具体的にいえば、そこにある女体という肉塊に対して、本能の衝動が起きた。
感情というのではなく、ただの衝動だった。
彼女の作り方などまったく分かってもなかった

彼女の隣に座り、背もたれに手を回す。
何がおこるかを察したかのように、ソファーの上で体育座りをして、黙って俯いている。
自分は当然のように、背中に手を回して抱きしめて、ソファーの上に寝かせた。
着衣のままの少しだけの前戯で、足を高くあげて生で挿入。
力いっぱいに腰を打ち付ける反動で、向こうにずれていく彼女の軽い身体。
その身体をソファーに押さえつけて、感じている彼女を見ながら、さらに激しく身体を突き抜いた。
射精した瞬間。
彼女に重なり肩に手を回し、背中に回した手で強く引き付け密着した。
衝動が急激に下がっていくのが、自分自身でわかった。
ビクンビクンと陰茎が射精してる状態で、既に後悔をしてる自分に驚いていた。
預かった従業員に中出ししてしまったこと。
脆い自分がわかったこと。
このようなことから後悔の念がでたのだろうか?
しかし翌日の彼女は、それまでとは違う親しさを見せた。
サンタクロース村を出て、羽田に到着して、車で自宅に送り別れるまで観光旅行のようだった。
自分も悪い気はせず、サービス精神は発揮した。
彼女と会うのはそれ以来。
度々は電話したりかかってきたりで、お互いの近況は話してはいる。
キャラクターグッズの会社は見事に倒産していた。
彼女は八王子の実家に居り、洋服屋のバイトの毎日。
自分は商売がヘコんで無職ということになっている。
スカウトで食い扶ちを稼いでいることは、彼女には言えない。
スカウトというのは、まだ、自分にとって虚業だった。
『残念会』ということで渋谷で待ち合わせたのは、お互いの笑いがあった。
居酒屋に行き、自分は明るくなり、彼女も笑う。
かわいいな・・・と感じたのは確かだった。
– 2001.2.14 up –