風俗嬢は化粧に手をかけない

平日の夕方。
新宿駅東口にある映画の看板前。
午後からスカウトをはじめていた。
が、感触は掴めなかった。
3人にはアプローチしたが、どうにもならず。
いずれも番号交換もせずバイバイしていた。
スクランブル交差点の信号が青になると、ヒールの女のコが渡ってきた。
黒いトートバックを肩にかけているOL風。
目を向けていると一瞬だけ目が合った。
彼女はすぐに反らしたが、そのまま歩いてきている。
通行人を避けながら、歩調を合わせながら、距離が詰まってからは手の平を軽くあげた。
こちらを見ないままだけど、気配は感じている様子。
「ちょっと、いい?」
「・・・」
声をかけたとたん。
猛ダッシュ。
これはだめだな、と東口方面を向き直った。
すぐにデニムの学生風の女のコが歩いてくる。
テクテクといったふうに。
2歩ほど踏み出して手を軽く挙げると、こちらに気がついた様子だった。
かすかに眉根が曇った。
「ちょっと、いい?」
「・・・」
とたんに凄まじい早歩きをして彼女は去る。
これもだめ。
向きを変えた。
アルタ前広場をブラブラ歩いてみる。
地下出口から姿を見せたのは、明るめの茶髪。
目がパッチリの女のコ。
少し歩み寄ると、こちらに敏感に気がついた様子だ。
同時に手を軽く挙げた。
「ちょっと、いい?」
「・・・」
「・・・歌舞伎町いくんだ?」
「・・・」
「ちょっと、聞いて」
「・・・」
無表情の完全無視。
3歩ほど声をかけるが、彼女の歩調は変わらない。
だめだこりゃ。
この場合は、何を言ってもムダになる。
立ち止まり、ピタパンのヒップラインを見送った。
それから目に入ったのは、青になったスクランブル交差点を渡ってきた女のコ。
髪をひとつ結びして、ナチュラルメイク。
人の流れの中にいて、それが壁になっていて歩いているから、こちらに目は向かない。
2人ほど通行人を追い抜いてから、斜め後ろから二の腕をチョンと突付く。
彼女はチラッとこちらを向いたが、歩調は変わらない。
もう1度突付いてから横に並んで「ちょっといい?」というと、歩調が速くなった。
猛烈な速さ。
ムリだ。
見送ってから深呼吸。
スクランブル交差点を渡ってみた。
今度は、お姉さま系ファッションといのか、派手な女のコが歩いてきた。
歩調を合わせて向かった3歩ほどで、こちらに気がついた様子で目を向けてきた。
表情は明るく、警戒はしてない。
目が合うと同時に、軽く手を挙げながら近づくと、彼女の歩調は緩んだ。
これはいけると、思わず手を振った。
「ちょっと、いい?」
「・・・」
「あやしい者なんだけど」
「ハハ、なにそれ」
「だって、あやしいでしょ?」
「うーん、ちょっとね」
彼女の足は自然に止まった。
声をかけられるのには慣れている止まり方だ。
「どう?お話を聞いてみない?」
「キャッチ?」
「うん。あやしい者だからあやしい話するけど」
「じゃー、ダメ!」
「少しだけ聞いてよ、10秒でいいから」
「ハハ」
目元のメイクがきまっていて、ゆるい巻き髪してるあたりは、これから仕事だとすればキャバ嬢か。
風俗嬢はこれほど化粧に手をかけない。
「AVなんだけど」
「エエエ!!やらない!やらない!」
「そうだね、オレなにいってんだろ。実は1回だけ出演したことがあるとか?」
「ない!ない!ない!」
「そう、雰囲気あるよ」
「なにそれ」
「変な意味じゃない。考えてみてよ」
「ぜったい、やらないよ!」
この驚きが含まれた断り。
今までにAVスカウトの話を聞いたことがない感触がする。
以外だ。
声をかけられるのには慣れているというよりも、今は気分がいいだけかもしれない。
「きょうは、これから店?」
「店って?」
「んーとね。キャバクラ?」
「まえ、やっていたけど」
「やめたんだ」
「それがね、ツブれちゃって」
「エッ、なんて店?」
「●●●●」
「知らないな」
「小さな店だよ」
「そうなんだ」
「サイアクでしょ」
「ううん。ウケる。おもろいね」
「そういうこというんだ」
「うん、以外にマヌケなんだね」
「あ、ムカつく」
「ごめん、ごめん。名前なんていうの。オレ、田中だけど」
「・・・キョウコ」
「キョウコって呼んでいい?」
「フフ・・。いいよ」
最初から下の名前で呼ばせてくれるのはいい。
あと少しは話せる。
彼女は19歳の大学生。
歯科大学に通っているという。
話すと明るく活発な性格がわかり、 笑うと目がなくなり愛嬌がある。
黙ってると、ちょっとばかり怒ってるような顔立ちになる。
「キャバクラだったら」は多い
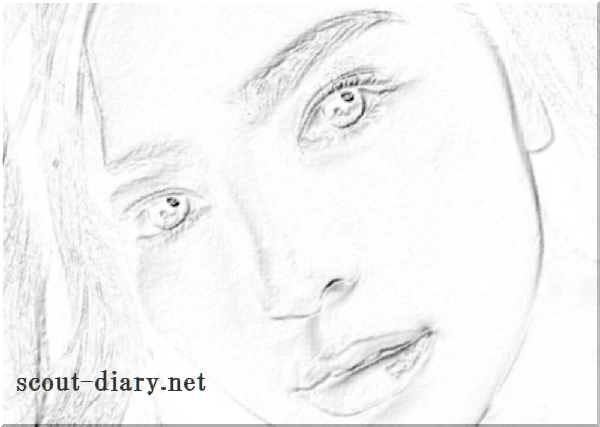
今日は、友達と会って帰る途中とのことだった。
時間はあるよ、と伝えてきた気がした。
「キャバクラだったらいいよ」
「オレもあちこち頼まれていてるけどね。だけど、キャバは大変だよ。それだったら、月に1回AVの予定いれてさ」
「なにいってるの!」
「キャバは、週何日入れるの?」
「2日か3日」
「5日は?」
「うーん、つぎの日が学校だからちょっとムリ」
「●●●ってお店しってる?」
「あ、知ってる」
「そうなんだ、いい店だからどうかなって思うんだけど」
「●●●か」
「とりあえず、ケーキ食べない?」
「おごってくれるの?」
「うん。それで佐々木っていう担当よんで、あいさつさせるから。こんど時間があるときに店をみてよ」
「・・うーん」
バイト感覚のキャバクラ希望のコは多い。
だから、いちいち相手にしないし、お茶すら飲まないでバイバイする。
だけど、彼女は「まあ、いいか」と一瞬思ったから「ケーキ食べよう」と言った。
ちょっと休憩もしたかった。
「もちろん今日どうのこうのでなくて、店の雰囲気とかシステムとかスタッフの感じとかあるから、それは事前に確かめて、ダメならそれでかまわないから」
「AVはナシだよ」
「それは半分冗談だから」
「半分ね」
ケーキをおごることに喜んだり、AVの件は断りの念を押してきたり、以外に真面目そうな彼女だった。
決まったことは、ちゃんとやるだろうとは感じた。
「うん。半分は本気だよ。オレの本業だからね。だけど店とはぜんぜん関係ないからさ、あとはその佐々木に聞いてさ」
「ウン」
「電話してみるね」
「ウン」
とはいっても。
1つだけ気になったのが、彼女の容姿と条件の折り合いで入店が決まるかどうか、ということだった。
容姿はとびきりではないが、面接は楽に通るだろう。
ちょっとばかり派手なのが、活発な性格がストレートに出させている。
キャバクラとはいえ、客をもてなす仕事ということを考えると、店によっては通らない気も。
とくに佐々木の店は高級なので、落ち着いた女のコのイメージを重要視していた。
高級店は明るい髪に派手なメイクって通らない
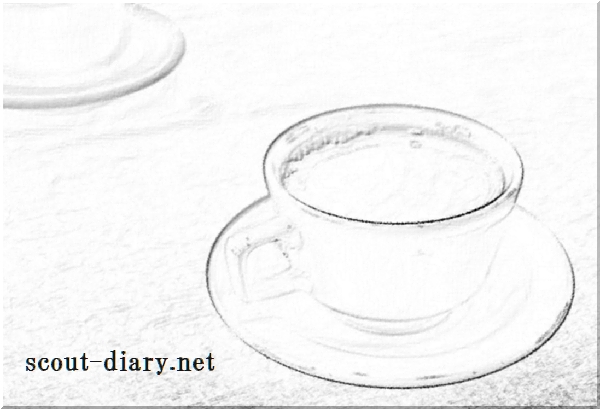
イタトマにいると佐々木が来た。
おどけて見せて笑顔を確かめたり、仕種をチェックしてるのがわかる。
さりげなく席を替わって、立ち姿をチェックしてるのも。
結果的には断られた。
「今、レギュラーで入店できる方を探してるんですよ」
「ハイ」
「それなので週3日だと厳しくなってしまいます」
「そうですか」
週3日だからと断ったが、この場合、イメージが引っかかったのだろう。
場の雰囲気を壊すことなく、佐々木は退席した。
彼女と2人でコーヒーをお代わりする。
「やっぱり週3日だときびしいね。ゴメンな、手間かけさせて」
「ううん。いいよ」
「大きなグループだから融通がきかないんだよ」
「うん」
そのうちに、どちらともなく「AV事務所ってなに?」みたいな話になった。
そういう話は嫌いではない、と彼女は少し笑う。
「AVってね、面白いんだよ」と話すと「ウン、ウン」と興味深そうに聞く。
以外だった。
もしかしたら、脱がせられるかもしれない・・・という気がした。
AVは頭の片隅で考えておく、という当てのない約束ができた。
またいつでも新宿で時間があるときに電話くれれば、今日のお詫びにケーキをおごる約束もして東口まで歩いて別れた。
電話がくるのは半々くらいか。
歩道の脇の鉄柵に腰掛けて、歌舞伎町に向かう女のコを眺めながら、佐々木に電話してみた。
「どーも、さっきは手間かけてすみません」
「あー、田中さん。こっちこそすみません」
「やっぱりダメでしたか。ギリギリだと思ったんだけど」
「ちょっと田中さん。彼女、ギリギリでなくて通らないよ。あの明るい髪で派手なメイクって高級店はまず通らないですよ」
「そっか」
「あと、にぎやかすぎるのと、顔立ちキツイっていうのか、もうちょっと柔らかい感じってうのか、落ち着いていたらいいんだけど」
「そう。おかしいな」
「田中さん、また、やっちゃいました。どうも時々ズレるなぁ」
「そうかな」
「でも、ああいう感じのコが好みなんだな、というのはわかりますよ。ちょっとキツイ感じというか」
「よく、いわれますね」
「田中さん、前にも言ったけど、けっこうブスフェチ入ってるよね」
「いや、いや。彼女はブサイクじゃないでしょ」
「そうだけど、商品としてはズレてるよね」
「わかってます。店でウケる女のコは」
「ハハハ」
こんなことが、前からちょくちょくある。
自分がいいな・・と感じるコでも、佐々木は「ちょっと・・」というのが。
娘にAVやらせたいという理由

それから1週間ほどは、ずーと天気が悪かった。
曇ったり、雨が降ったり。
それで週末になって、久しぶりに智子のウチに泊まった。
付き合い始めた2年ほど前と比べて、2人の子供とのぎこちなさは、大分なくなったという気がする。
それに、智子の子供といっても17歳と19歳だから、物分りのいい対応をしてくれる。
『お母さんのカレシの田中さん』という微妙なスタンスで接してくれる。
智子は自分と2人だけでいる時はやさしくて、オバサンだけどカワイイなと思うときがある。
だけど、智子は家で子供といる時は変わってしまう。
母親になってしまう。
無意識のうちに、子供を気遣い守ろうとする。
子供も自然に智子に甘える。
ごく普通の母子の姿だけど、それを間近で目にするとなぜかイライラしてくる。
当初は子供に当たったこともあるし、それで智子を泣かしたこともある。
決して子供が憎いという訳ではない。
智子の子供に対するやさしさというのか、まあ、ハッキリいえば、自分と一緒のときには見せることのない、智子のにじみ出る母性にヤキモチを焼いているのがわかった。
このことは智子と話していてわかった。
男のヤキモチはみっともないと、10代のころ年上の女に教わった自分。
なんだか情けない気がして、すすんで智子の家に泊まりに行くことはなかった。
その日も、東西線の西葛西駅で待ち合わせたときは、まるで小娘みたいにきゃっきゃしていた智子だったが、1歩家に入り子供の顔を見たとたんに、母親がにじみでてきてるのがわかった。
どこかおもしろくない。
智子が自分の顔色を見て、気を遣ってるのがわかった。
寝る支度をしながら智子は言う。
「この前ね、本を読んでいたらね」
「うん」
「母親に甘えられなかった子供は、性格が不安定になるって書いてあったよ」
「だから?」
「あなたを見てるとよくわかる」
「そんなことは知らん」
「あなたのお母さん厳しいからね」
「・・・オレは、甘やかすとダメになると思ってる」
「そんなことないよ」
自分を子供扱いした口調だった。
見透かされたような気がして、つい智子を困らせてしまう。
「智子は子供を甘やかし過ぎだぞ!」
「いいじゃない、それでも」
「ふーん、オレと子供だったら、子供のほうが大事なんだ」
「なんで、そういうこというの?」
「ねえ、●●(娘)、AVやらせようよ」
「どうして、そういうこというの?」
「だめ?」
「当たり前でしょ!」
それ以上は、言い合うのをせずに、無言のまま布団に押し倒しただけだった。
「あのコたちが・・・」と嫌がる智子の下半身だけ脱がす。
すぐさま膝を割って腰を進めて挿入。
思い切り身体を突き上げた。
物分りのいい子供たちに、母親のいやらしい喘ぎ声を聞かせてやると、力まかせに腰を打ち付けた。
チンコの先にコリコリとした子宮が当たっている。
目をきつく閉じて、両手で口を押さえながら、必死に喘ぎ声を堪えていた智子だったが、やがて途切れ途切れに喘ぎ声が漏れはじめた。
久しぶりの海と観覧車

翌日。
早起きするとものすごくいい天気だった。
智子は仕事が休みなので、今日は2人でゆっくりしようと決めていた。
皆で朝メシを食べようとしたのだが、智子が声をかけても子供たちは部屋から出てこなかった。
昨晩の、漏れた喘ぎ声は聞こえたんだ。
自分としては、この家の主になったようで気分はよかった。
なんとなくワイドショーを見ていた。
浅草で起きた『レッサーパンダ事件』を取り上げていた。
コメンテーターが『母親の死が1つの原因になってる』とも。
不気味で、全く理解できなかった事件だったが、そのコメントを聞いて、智子に昨晩に言われたこともあって、なんだかわかるような気がした。
幼児虐待の事件も取り上げていた。
交際相手の年上の女性の連れ子を虐待した、という事件。
ドキッとしてしまう。
もし智子の子供が小さかったら、自分もそうしてしまうかもしれないと自身を疑った。
森首相のコキ降ろしもやっていた。
なぜか、森首相には親近感が湧く。
体が大きい割には気が小さく、田舎の町長風で、国民には嫌われるし、キレ者という感じではない。
しかし、腹黒い政治家というわけでもなく、以外に真面目だったりもする。
そんな森首相を見てると、なぜか親父を思い出す。
大柄の体躯で、誰よりも一生懸命に働いて、正論を通し、そして人には嫌われ、農業団体の管理職を辞めたことのある不器用な親父にダブった。
だいたい、ワイドショーなんて『コイツらバカだ!』『世の中狂ってる!』と思いながら見るからスカッとするのであって、犯人や鈍宰に共感していたのでは朝から悲しくなってしまう。
いつからこんな風になったのか。
スカウトを始めてからか。
いや、ただ単にオヤジになったのだろう。
テレビを消した。
ジャージとサンダル姿でママチャリに乗り、智子と2台で葛西駅周辺まで買い物に行く。
今日は母の日だった。
といっても、自分はなにもしたことがないのだけど。
久しぶりの自転車が、すごく気持ちがいい晴天でもあった。
「ともこ」
「なに?」
「きもちいいね。自転車」
「そうだね」
「このまま、どこかいこうか?」
「臨海公園いく?」
「遠い?」
「ううん。15分くらいで着くよ」
「近いんだ。じゃ、行ってジュースでも飲もう」
「うん」
「1回しかいったことないよ、5年くらい前かな。なんにもなかったな」
「いまは観覧車できたんだよ」
「よし、観覧車のろう!」
「フフ・・・」
葛西臨海公園に近づくと、風の匂いが変わったのが感じた。
ちょうどいい風が吹いている。
髪をなびかせて自転車を扱ぐ智子が若く見えた。
公園に入ると海が見えてきた。
かもめが飛んでいる。
想像よりも大きな観覧車も現れた。
家族連れやカップルが、すでに多く歩いていた。
海が見える芝生の上に座ると、なんだかリゾート地に来たような気分になった。
「こんなに近くにあるとは知らなかった。それに変わったね」
「近いでしょ?」
「うん。・・・考えてみたら3年振りだよ。こうして、海に来たのも」
「ふだん、どこにもいかないからね」
「ちょうどいい風だね」
「そうでしょ、あっちの方に行く?」
「もう少し風に当たりたい」
「・・・」
「あぁぁ、・・・なんか、ベリベリっとアカがめくれて飛んでいく感じがする」
「いつも悪いことしてるからね」
「それほどはしてないよ」
「フフ」
しばらく風に当たっている。
目を閉じた。
海からの風で垢がめくれて、本当に飛んでいく気がした。
AVやるかもしれない

智子がバックをゴソゴソして、預けていた携帯を取り出して「着信あるよ」という。
履歴を見るとキョウコだった。
まさか、電話があるとは思わなかった。
海が見えるカフェテリアに場所を移してから、彼女に電話をした。
「どーも」
「あー、田中さん。きょう新宿いくけど」
「何時くらい?」
「7時くらいかな?」
「そう、じゃあ7時くらいにスカウト通りあたりで電話して。体空けとくから」
「ウン」
いいのではないか?
多少はAVをやる気があるということになるのではないのか?
智子は脇を向いていたが、電話を終えても不機嫌そうだった。
「このコさ、AVやるかもしれないんだよ」
「そう」
「きょう、新宿に来るっていうからさ」
「それでいくの?」
「夜になってからね」
「・・・」
「・・・このまえ佐々木にいわれてわかったんだけど、オレってさ、キツイっていうのかな、冷たい感じのコが好きみたいだね」
「そう」
「自分で納得したんだけど、ブスフェチ入ってるっていわれてさ」
「あなたのコは、みんなそうでしょ?」
「・・・うーん、みんなじゃないけどね」
「写真を見ても、カワイイって女の子いないわよ」
「そう?」
「どのコも、カワイくない!」
「・・・」
「・・・」
「でね、やっぱりさ、無意識のうちに、タイプのコにググッとチカラが入るからだなっておもった」
「・・・」
「不思議だね。人の好みって」
「あなた、お母さんが好きなのよ」
「エ・・・」
「あなたのお母さん、そんな感じじゃない」
「オフクロは好きじゃないけど・・・」
「エリちゃんの写真みたときも、似てるなって思ったよ」
「・・・よくわからない」
「やっぱり、お母さんが好きなのよ、あなたは」
「・・・オフクロは嫌いだよ」
「母の日になにかプレゼントしたの?」
「・・・いいじゃん、べつに」
「なんで?してやりなさいよ」
「・・・・」
今度は自分が不機嫌そうな顔をして、智子は黙った。
が、すぐに智子は口調を変えて「観覧車のろうよ」と笑顔で指差している。
観覧車に向かって歩きながら「お母さんが好き・・・?」というのが、ずーと引っかかっていた。
自分では認めたくない。
理屈でなく、“ おふくろが好き ”というのは“ 自分の負け ”というような感覚があり、絶対に認めたくない。
16歳のときに家出してから14年経つが、この気持ちは変わってない。
智子は違う話題にしようとしてか、「あの観覧車は日本で一番大きいんだって」とニコニコしながら話しかけてくる。
観覧車はそれほど待つこともなく乗れた。
見晴らしがいい。
いつ以来だろう、子供のころに乗ったな、と思いながら遠くまで眺めて、ゆっくりと上がっていくと同時に気持ちも晴れた。
「今日、この公園で何人も結婚しようって会話するんだろうな」
「そうだね。・・・ね、・・・キスしようよ」
「なにいってんだよ」
「ね、いいじゃん」
「やだ、そういうの。だったらフェラしろよ」
「ヤダ」
「ここで仁王立ちするから」
「フフフ」
動くのが怖いくらい観覧車は高く上がった。
ゆっくりと一周した。
観覧車を降りてからは、また自転車で公園をあちこちを乗りまわした。
途中でネコにエサやったり。
波うち際までいったり。
芝生に寝転んで抱き合っているカップルを観察したり。
妙に単独男性がいる場所をハッテンバだと断定してみたり。
ママチャリのベルをチリンチリンと鳴らして疾走する姿をみて「とても30のオヤジにみえない」と智子が笑う。
こんなに爽やかに笑えたのは久しぶりだった。
海からの風が冷たくなってきたのは、夕方にさしかかっていたからだった。
『夕焼けこやけ』のメロディーが鳴り響いたのが17時。
綺麗な夕焼けは、久しぶりに見た。
いつもはこの時間に、人混みだけで空気が澱んでいるばかりのあの新宿にいるのか・・・と、ふと思う。
気がつくと、観覧車には沢山のライトが燈いていた。
大きな円の内側に、赤、青、黄と点滅し、日が落ちると花火が広がってるみたい。

「花火みたいだ」と観覧車を見上げると、笑みながら頷いた智子は「暗くなったし、風も冷たいし、そろそろウチに帰ろ」と目尻にシワを浮かべた。
「また、いこうね」と話しながら、荒川沿いを自転車で走った。
2人で自転車で走ってるだけで楽しく感じた。
「わたしは、あなたのお母さんじゃない!」

智子のウチに着いた。
玄関のドアを開けたとたん、子供たちが待っていたかのように「おかえりなさい」と顔を見せた。
そして母の日のことを口にした。
子供たちに向けられた智子の横顔には、すでに母親が滲み出ていた。
それから息子のほうが「ゴハン食べたい」といいだした。
智子は母親みたいに、といっても実際に母親なのだが・・・、ゴハンを作りはじめた。
ウチに帰ろうと言ったのは、日が落ちて暗くなったからではなく、子供たちにゴハンを作ってあげるためだったのか。
それが当たり前なのはわかってはいる。
自分が間違っているのは自覚している。
だけどキッチンに立つ智子に、笑顔で話かける子供たちに対して、どうしてもイライラが止まらない。
このままキッチンのテーブルに座ったままだと、なにかの拍子で、思いっきり子供たちを怒鳴りつけてしまいそうだ。
智子の部屋にいく。
時間より少し早かったが、ジャージから普段の服装に着替えた。
「ともこ、そろそろいかないと」
「ふーん」
「駅まで一緒にいこうよ」
「いま、作ってるでしょ」
「おこってるの?」
「・・・1人でいけば」
「ともこ、駅まで一緒にいこうよ」
「・・・」
「ね、ともこ」
「・・・」
「ねえ」
「わたしは、あなたのお母さんじゃない!」
「・・・」
智子はキッチンに立ち、背を向けながら、冷たく叱るように言い放った。
その様子を見て娘のほうが気を遣ったのか、2言か3言ばかり話しかけてきたが、余裕がある大人の男みたいに気にもしない素振りを見せて「それじゃ」と表に出た。
西葛西駅の周辺は、行楽帰りの親子連れもいるせいか。
日曜日の夕暮れという空気だった。
だからだろうか。
このときは自分にとっては、なんだか1人でいるのが物寂しいという気持ちが珍しくあった。
そして、あの新宿にいくのかと思うと『オレ、なにやってんだろ・・・』と気が滅入った。
改札口を通り、ホームに上がり、電車を待つ。
今日は楽しかったな、また観覧車のりたいな・・・と思ったり、素っ気なく家を出てきたから智子は怒ってるかな・・・とも気にもなった。
ホームに入線してきたのは、長い電車だった。
機械音が耳に入り、鉄の匂いがする風圧が顔に当たった。
同時に、智子にあんなことを言われたが、自分は決して母親になど甘えてはいけないんだ、と強く念じた。
すると。
強く念じた一方で、涙が少し滲んできた。
こんなことは初めてだったし、不思議だった。
なんでオレ泣きそうになってんだよ、気持ち悪いなと、下を向いてきつく瞬きすると、涙はこぼれ落ちそうになった。
– 2003.3.8 up –
