面接落ちも、もちろんある

早番で店を上がったその日は、西武新宿駅前通りの個室ビデオに直行。
すぐさま全裸になって、オナニーに耽っていた。
仕事が終わった直後のオナニー、とくに全裸オナニーには開放感がある。
直後の全裸だ。
繰り返すが、直後で全裸でなければならない。
帰宅してからのオナニーとは別の気持ち良さがある。
再オープンして以来、人出不足のために休日なしだった。
オナニーくらいは存分にしたいではないか。
すると、遠藤から電話があったのだ。
「店長!遠藤です!」
「ああ、おつかれ」
「今から面接って、だいじょうぶですか?」
「ん・・・、10分後はどうだろう?」
店長と言っているから、すぐ隣に女の子がいるのだろう。
ローションまでつけた後だったが仕方がない。
こういうのはタイミングが大事。
すぐに面接した方がいい。
「じゃあ、そのくらいに店に行くっす」
「あ、やっぱ、20分後のほうがいいな」
「わかりやした、じゃあ、そのぐらいで」
「裏の入口をノックして」
「はいっす」
「じゃ、のちほど」
今は面接が最優先か。
再生を止めた。
股間のローションを、ティッシュで拭き取った。
個室ビデオを出た。
冬になりかけている街路を歩いた。
気がつけば、陽が短くなり、12月の手前となっている。
年末が迫っている。
1年でいちばんの入客が予想される時期を前にして、在籍の女の子が足りてなかった。
遠藤のスカウトは勢いがついてきていて、期待はしていたが、今ひとつ空回りしていた。
再オープンの前には第1号の面接もあった。
が、どういうわけか、ドンキホーテで売っているピカチュウの着ぐるみの2人組を連れてきた。
とりあえず「話をきくだけ」と面接に連れてくれば、くわしい説明はこっちですると言ってはいた。
まだ、遠藤は風俗の説明もよくできないし、相手も風俗をやるのに迷っているくらいの状況だったらそのほうが早い。
だからってだ。
ただその辺を歩いている女の子を、ただ連れてくればいいってもんじゃない。
「話だけっていうんできましたっ」と着ぐるみ2人組は面白そうに笑っているが、いくらなんでも、風俗といえども、面接だというのはわからせてからきてほしい。
簡単に面接だけはして「やる場合は電話くださいね」と、着ぐるみの2人は帰した。
面接第2号は、風俗歴7年のベテランだった。
「いまの店って稼げないっ」と不満顔をしている25歳。
髪も目元も、唇も肌も、ぱさぱさしていた。
「わたし、18歳のころは毎月100万以上は稼いでいたのに」という彼女に、遠藤は「すごい稼げるから!」というノリと「1日10万はいくよ!」というオーバートークで面接に連れてきていたのだった。
彼女は、あっさりと初日でトビとなっていた。
悩んでいるのだったらやめ、迷うならやれ

店への路地裏に入ったくらいに、遠藤からメールがあった。
< 前のロシアの女す。まだ迷ってるんでムリだったらすいません! > とある。
自分と遠藤の間でロシアの女といえば・・・。
先月スカウト通りで遠藤と勝負したときの、あのハーフにも見えた、身長高めの色白の巨乳の女の子か。
ロシア料理店でバイトしていて、地元が小手指で、20歳の学生というのも覚えていた。
店では人感チャイムが鳴っていて、有線からのキューティーハニーが終わりかけていて、竹山がリストに指を置いて待ち時間を確めていた。[編者註73-1]
遅番で出勤人数が5名では、すぐに待ち時間がでる。
「あれ?田中さん、どうしたんですか?」
「これから面接する」
「面接ですか?よかった!女足りないですもんね」
「うん。そこそこいいのがくるよ。まだ、迷ってるっているらしいけどな」
「いやぁ、やっぱ待ちでこぼしますね。連続こぼしですよ」
「5名じゃ、きびしいな」
現状、入客は21名、こぼし7名。
木曜日の今くらいで、こぼし7名は多い。
シフト表を開いて目を通して、有線のボリュームを少しだけ上げているうちに、裏口のドアがノックされた。
連れてきたのは、やはりロシアの女、いや、その女の子だった。
チークなのか、寒い外気なのか、わずかに頬には赤みがさしていた。
彼女の少しの目礼で、自分を覚えているのがわかった。
「こんにちわ、よくきたね」
「あ、はい」
「じゃ、2人ともこっち座ろうか」
「あ、はい」
「そんな、かしこまらないで」
「はい」
彼女はソファーに座り、膝を揃えた。
頬の血色からいって体の肌質はよさそう。
陰毛が薄めのイメージがしたのは、生足のすねの毛穴が埋まっていたからだった。
「田中と申します。よろしくおねがいします」
「あ、はい。よろしくおねがいします」
以前に、街中の彼女を目にしているせいなのか。
挨拶しながらも、いつもよりも妄想力がほとばしる。
「えっと、なにから話せばいいかな?」
「あ、はい」
お辞儀をしてからの彼女は、髪に手をやって少し笑んだ。
この肉感と毛感をしながら、ほんのりというのか、ふんわりというのか、ほんわりしたこの笑み。
これを見せてくる女の子は、サービス精神が旺盛。
風俗向きだ。
ジンクスみたいなものだけど。
「なにか聞きたいことあるかな?」
「エッ、と・・・」
「なんでもいいよ」
「う・・・ん・」
「気になることでも、わからないことでも、遠慮なく」
「あ、はい・・・」
いくら稼ぎたい、どのくらい稼げるか、といったのが口から出てこない。
それが口から出てきたら話が早くて、こっちから条件をつけるところまでいくのに。
そもそも、お金が必要という目もしていない。
稼げると煽らないほうがいい。
「風俗をやったことないって聞いているけど」
「あ、はい」
「こんなことするってイメージってつく?」
「あ、はい」
とりあえず面接だけと遠藤は言っていたが、あれから1ヶ月もスカウトとして連絡を取り合って、風俗というのを承知の上で来てるのだから十中八九やるだろう。
「じゃ、だいじょうぶかな」
「んんん・・・」
好奇心はある。
が、迷っているようでもある。
また人感チャイムが鳴って「いらっしゃいませ!」という西谷の声が入口のほうから聞こえてきた。
なかなか慌しい。
「いま女の子が足りなくてね。ウチでがんばってくれないかな」
「あ、はい・・・」
迷ってはいるが、気持ちは固まっている。
抵抗感は見えない。
もっと、グイグイと決めていっても大丈夫か。
「ムリがないようにやっていこうね」
「あ、はい・・・」
「じゃ、今日からにする?」
「え、え、今日はムリです!」
悩んでいるのだったらやめで、迷うならやれだ。
どこかの占い師がそんなようなことを言っていた。
風俗未経験からしてみれば

どこの誰だろう。
今日は早番から、倖田來未がよくリクエストされている。
また誰かがリクエストしていて、有線からはテークバックが流れた。[編者註73-2]
手にしたファイルから、従業員名簿の用紙を見せつけるように取り出そうとしてみると、遠藤が放り込んできた。
「店長」
「ん」
「彼女、バレたらカレシに怒られるそうっす」
「ええぇ、怒られるの?」
意図は不明だが、このまえスカウト通りで教えたことだろう。
遠藤は、自分なりに噛み砕いて実践してるようだ。
従業員名簿の用紙は脇に置いて、話を合わせて大袈裟に彼女に聞いてみた。
「なんだって、怒られるの?」
「うん・・・、たぶん・・・」
目が、ぱちくりと瞬きをした。
下がった語尾の口調は考え途中である。
見たところ、親しい間だからこその怒られではない。
「なんて怒られるの?」
「なんてって・・・」
すでになんらかで、彼氏の怒られのやりとりが、複数回あった状況が見て取れた。
彼氏に怒られたのが、疑問に転化している。
「なんていわれる?」
「それはわからないけど・・・」
彼氏の怒りに萎縮しているのはない。
怖がっているのでもない。
別れを意識しているのでもない。
だいぶ前には、その状況は彼女の中では受け止められなくなっていて、疑問に転化している。
「バレたら別れるとかなるの?」
「わからないけど・・・」
彼女を通して感じられるのは、彼氏の我の強さ。
好意ある怒られかたは受け止めれても『俺が俺が』というばかりの我が強い怒られかたは、好きだからこその疑問を生む。
「もう別れちゃいなよ」
「ダメですよ」
風俗をやる以前に、まずは彼氏への疑問というのか、男の性への疑問を抱いている。
「じゃ、別れる予定で」
「別れないです」
瞬間の間で、隣に座る遠藤が「店長にいっちゃいな」と彼女を肘で突ついた。
彼女は首を振っていたが、また肘で突かれて、口ごもりながら明かしてきた。
「あの・・・」
「うん、どうしたの?」
「あの・・・、いままで、付き合った人が少なくて・・・」
「いいじゃん」
「でも・・・、できるのかなって・・・」
性の事情を明かした彼女は、目に熱がある。
スカウトのときも、風俗の面接でも、女の子が時々向けてくる目。
疑問が擦れて熱が出ている。
「いまのカレシで何人目?」
「2人目です・・・」
「2人は少ないな、でも、だいじょうぶだよ、心配ない」
「そうですか・・・」
男性経験2人でも、20歳だったら少なくないのではないか。
清い交際もして、失恋も経て、1年も2年もかけて付き合っていれば、2人でも妥当だろう。
が、少ないことにしておいた。
「うん、できるよ。だいじょうぶ」
「はい・・・」
「オレは女の子がか弱いなんておもってないから。ぜんぜん心配してない」
「そうですか?」
「そうだよ、女の子って実は強いんだよ。すぐにお客さんを右から左にさばけるようになる」
「さばけるって・・・」
「でもムリはさせない。そのあたりは様子みながらやっていこうね」
「あ、はい」
『やります』と口にできないだけか。
この感じだったら続く。
いい風俗嬢となる。
「なにか年齢を確認できるものある?」と、さっきまでオナニーしていたままの手で、彼女の免許証を受け取りコピー。
あとは従業員名簿の記入だけして面接は終了とした。
実家なので、遅い帰宅はできない彼女は、土曜日の早番から体験入店。
シフト表を開いて、さっき決めた店の名前を記入して、あさっての日付に<9:00~>と時間を記入した。
ロシア料理店のバイトはやめたという。
セクハラがひどいといっていたが、詳しくは聞いてない。
帰り際の遠藤に、こっそりとお茶代で3000円を渡すと「あざすっ」とうれしそうに言っていた。
やっと1名、スカウトバックにつながる在籍ができそうだ。
入客数の平均

店舗型から受付型へ移行するのに、オープン前の予想とは違うことばかりだった。
要領を得ずに、後手の対応ばかりが目立った。
そのバタバタも、1ヵ月過ぎるころには解消してきていて、全体としてはスムーズとなってきていた。
1日の入客数は、30名を超える日もあった。
以前の店舗型の、1日の平均入客数は35名だったから、再オープンしてから1ヵ月足らずで、以前の平均の手前まで近づいていた。
これは、なんのかんのいっても、以前からの在籍の女の子の力が大きかった。
いや、大きいどころではない。
すべてが女の子の力だった。
もし在籍が、新しい女の子のみでオープンしていたのだったら、1ヵ月ほどでスムーズに以前の平均の手前まで辿りつかなかった。
少なくとも3ヵ月か4ヵ月、もしかすると半年はかかったのかもしれない。
この古参の女の子たちは、・・・女の子のことを古参というのは違う気もするが、頼もしさも込めて古参の女の子たちとすれば、癖が強いし、頑固だし、わがままもぶつけてくる。
店の不手際の度に、遠慮なく文句も言ってきてたが、客に対してだけはきちっとやることはやって上手に喜ばせて帰していた。
細かなことはなにも言ってないのに、やってる店側がまごついているのに、女の子たちはどんどんと優良店の方向へとやってのけた。
予想していたよりも本強はなくて、早くも本指名の客が来店したり、出勤の問い合わせの電話もきていた。
女の子のサービスさえよければ、客にとっては店舗型であろうと受付型であろうと関係ない。
店舗型には店舗型の良さが、受付型には受付型の良さがある。
早い時点で、女の子たちがそれらをわからせてくれたのは大きくて、まだ売上は伸びるという強気な手ごたえに繋がった。
女の子たちが来店客の後のことを一切を引き受けてくれたことで、店側は集客に対応して、受付を改善して、日々の雑用にと手をかけることができた1ヵ月だった。
しかし、これ以上に入客を増やすのには、どうしても在籍の女の子が足りない。
いったんオープンすれば以前の店の在籍も戻るだろう・・・という見込みとおりに、最初の8名から12名までは増えてはいた。
在籍は12名でも、以前の5つの個室だけの店舗型だったらなんとかなった。
しかし受付型では、在籍12名でも足りない。
レンタルルームで7つの個室、それにラブホテル利用もある。
回転も落ちている。
なんとかできる状況ではなく、明らかに足りなかった。
感覚としては、倍の在籍が必要だ。
せめてあと3名ほど。
いや、2名でも新参の女の子が現れれば、以前の店と入客数が並ぶとの手ごたえは感じてはいた。
商売繁盛の熊手といえば
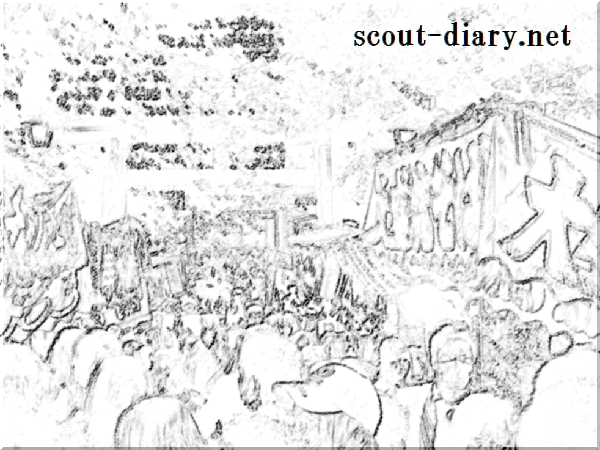
面接を終えて、遠藤と彼女は帰っていった。
入客の慌しさも、ひと段落している。
女の子たちにも変わった様子はない。
個室ビデオに戻ろうとすると、代行が張り切った声で電話をかけてきた。
熊手の件だった。
花園神社で酉の市がはじまっていたのだった。
「いつでもいいよ」と代行はいうが、ちょうど体が空いているので、代金の5万円を持って受け取りにいく。
靖国通りの歩道には、裸電球が連なっていた。
たこ焼き、ベビーカステラ、などの露店がぎっしりと並ぶ。
人々もぎゅうぎゅうになっている。
新宿に10年ほど住んでいて、今の時期には酉の市があることも知ってはいたが、普段は人気がまったくない花園神社がこんなふうに賑わっていたとは知らなかった。
ぎゅうぎゅうのまま鳥居をくぐる。
境内は連なった裸電球で明るくて、露店には大小の熊手が並んでいて、半纏を着た人達の売り声が飛び交っている。
中ほどの露店に大柄な代行が立っていて、手振り身振りを交えて冗談を放っているのか、一同をどっと笑わせているのが見えた。
気のいい性格なのだ。
普段の代行は、ワンちゃんなどがプリントされたジャージ上下なのに、今日はめずらしくノータイのスーツ姿。
挨拶すると「おっ、ありがとな!」と特大サイズで “ 商売繁盛 ” と札のある熊手を持ち出した。
5万円だけある。
見栄えがいい飾り物が、たくさんついていた。
手渡されてからは「お手をはいしゃく!よーお!」と、一同から手拍子を浴びると悪い気はしない。
升酒を勧められて1杯飲む。
意志の弱い自分は、あとちょっと、あと1杯だけと、裸電球の境内を眺めて飲みたくもなるが、たぶんちょっとでは済まない。
それに、代行とはむやみに親しくしたくはないので、1杯だけでお礼を述べて、早いところ店まで帰ろうと熊手を肩にかけて花園神社を出た。
人出のある靖国通りを避けて右折して、ゴールデン街を抜けた。
ヌード劇場の前を通ると、年末のリズムが乗った微風が歌舞伎町方面から吹いてきた。
うかうかしてると年末になるのだ。
在籍を増やさなければだが、そこだけはどうやっても計画通りにいかないものだった。
再オープンして以来、店のことで気が抜けない。
このあと個室ビデオにいきたいが、ミサキが個室の毛布が足りないとか言ってたし、今のうちにドンキホーテに買いにいこうかと悩みながら、待機所に入ったところの壁にネジを打ち込んだ。
特大サイズの熊手は、見る人が見れば暴力団との付き合いを疑われる。
あえて、それをする必要がないので、熊手は客の目につく店内ではなくて待機所の壁に掛けたのだった。
殺風景な待機所でもあったからなのか、戻ってきたナナは、特大サイズの熊手にはしゃいだ声を上げた。
条例はわりあいと簡単に変えることができる
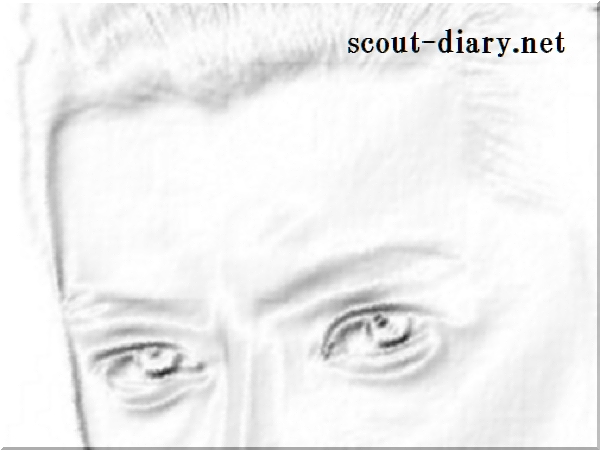
熊手の翌日の早番だった。
出勤は2名。
金曜日の早番はそれほど混まないが、2名はギリギリの出勤人数だった。
ダミー出勤を4枚も交ぜていて、常に30分以上の待ちがある状況が続いていて、こぼしてはやきもきしながら受付している状況のときに人感チャイムがピンポーンと鳴った。
「いらっしゃいま・・・」とカーテンをめくり、相手の姿を見て『あれっ』と動きが止まった。
店舗型のときの警告と摘発に姿を見せた刑事だ。
四角い顔のオールバックの。
刑事は、捜査対象者には最初からは名乗らないもの。
こっちもそうなのだろうと確めてもないので、本当の名前は知らない。
西郷隆盛というあだ名は勝手につけていた。
にこりともせずに、スーツ姿で、口元を締めてバッグを手に立っている。
1人ということは、捜査ではないか。
まばたきもしない目は、すでに正義感の光が発されているようだ。
「ちょっと・・・」と西郷は『外で話そう』と手振りをした。
小泉に声をかけてから店の外に出ると、階段の踊り場まで下りている西郷は、足元にバッグを置いて立っている。
また警告なのか。
愛想なく、軽く頭を下げて挨拶くらいはした。
西郷は、こちらの内心を察したらしい。
「今日は、そういうのじゃないから」
「あ、そうなんですか?」
「うん。もう、本庁に戻ることになってね」
「本庁っていうと?」
「ああ、今回は、警視庁からの出向という形で来ていたから」
「へぇぇ」
「もう、歌舞伎町からは離れるんだよ」
「そうですか。その節は、お世話になりました」
出向で歌舞伎町に来ていたといわれても、歌舞伎町から離れるといわれても、なんと返せばいいのか。
こんなときに揉み手でもして『へへっ、ダンナ・・・ 』とさらりと勉強会でも一席設けて、帰りがけには『お車代です』といったことができる大人になりたい。
それらが、そつがなく出来る大人こそが、警察がらみの大きな商売を手がけることができると自分は信じているが、突然には出来ないものだった。
わずかに表情が緩んで、口元に2ミリばかりの笑みが浮かんだ西郷は、踊り場の壁面に取り付けた看板に目をやって続けた。
「今、届出してやってるんだね」
「ええ、これで大丈夫ですよね?」
「うん。ちゃんと係と相談してやってるでしょ?」
「はい」
「だったらね」
「ああ、よかった」
「まあ、前回は、ああいうことになったけど、警告を無視したからね」
「これで問題ないですね?」
「でも、エスカレートすると、また条例も変わってしまう」
「ええ!条例がですか?」
「うん。条例って、わりあいと簡単に変えることができるから」
「そうですか・・・」
「風俗店が好き勝手やって、若年層の性モラルの低下、社会風紀の乱れ、そういうことに繋がるとなれば、また取締りにもなる」
「・・・」
なんだよ、わざわざ説教に来たのか。
性モラルなんて行政目線で決めつけるな、この隆盛よぉ、と内心で毒づいたが、表情は変わってないはず。
「まだ、後ろ指を差されているうちは、まだいいんだよ」
「はぁ・・・」
「それが、誰からもいわれなくなったら、また同じことの繰り返しになる」
「はぁ・・・」
正義の反対は悪ではなく、別の正義だと心の中でいってみる。
誰かのパクリだけど。
悪徳不動産屋の情報提供

隆盛は、用件を思い出したかのように訊いてきた。
「ここの物件は、どこの不動産屋で借りた?」
「サンライズっていう会社の仲介です」
「うん・・・、じゃ、だいうじょうぶかな」
「どうかしたんですか?」
隆盛は3社の名を挙げる。
それらを知っているかと問うてきたが、いずれも聞いたこともなくて、関わりもない社名だった。
隆盛いわく、その3社は悪徳不動産屋だから、気をつけたほうがいいとのこと。
店舗の賃貸契約のときに支払う保証金についてである。
歌舞伎町の店舗の賃貸契約では、違法営業で摘発された場合、保証金は大家の没収とする条項が盛り込まれるのがほとんだ。
そこで、店舗の保証金の早めの没収を目論んで、悪徳不動産屋と大家が組む。
営業がはじまってから、悪徳不動産屋が警察に情報提供するケースが目立つそうだ。
「でも、それって店は困るけど、警察からすれば違法営業がなくなるからいいんじゃないですか?」
「だからといって、違法営業するのを知りながら契約すること自体が問題だ」
「そういうもんですか」
「んん。本当はなぁ・・・、そういう悪徳な不動産屋も、これから取り締まらないとだけど・・・」
「・・・」
「もう、これで本庁に戻らないとだから」
本庁に戻るのが不本意なのが、口ぶりからは伝わってきた。
秋の終わりの、さらに終わりの寸前の空気だからか、しんみりとも聞える。
店を借りたのがその3社の絡みではないのをまた確めて、そのときだけは「よかったね」と職業的態度を崩して、親切にも感じる笑みと口調もした。
もし、店の賃貸契約に悪徳不動産屋が関わっていたら、違法行為には気をつけるように忠告するつもりだったのかもしれない。
この人。
もう歌舞伎町を離れるのに。
少なからず、この店のこれからを気にかけてくれているんだ。
警視庁にいるような上級の公務員というのは、自身の評価のための職分さえ無事に果たしたなら、あとのことは我関せずではないのか。
「じゃ、田中君」
「はい」
「もう、これで、会うこともないんじゃないかな」
「そう面と向かっていわれると、ちょっとさびしいじゃないですか」
「そうか」
「そうですよ。またどこかでってくらいはあってもいいとおもいますよ」
「ははは・・・、うん、でも、このまま、真面目にお店を続けてください」
「あ、はい、わかりました」
「田中君が風俗を変えるくらいに、お店のほうがお客さんを教育するくらいに、そのくらいしっかりやってください」
「はい、しっかりやります」
「田中君が、風俗で成功するのを願ってます」
「あ、あ、りがとうございます!」
いきなり改まって丁寧語できたものだから、自分もつい営業調で答えて一礼したのがおかしかったのか。
口元に笑いをつくりながら、足元のバッグを持ち「それじゃあ」と目礼をして階段を下りていった。
ひとまず、脱法うんぬんは大丈夫なんだと、小さく万歳したい気分もある。
どういうつもりで来たのかはよくわからないが、いいやつかもしれない。
内心で毒づいたのを取り消した。
せめて街路を歩いていく彼の姿を見送ろうと、階段の踊り場から外に目を向けると、待機していたらしい黒いセダンに乗り込むところだった。
– 2023.04.02 up –